古い文章を整理していたら、10年前に書いた文章を見つけた。
ずいぶんと青臭い意見だが、それなりに気負いもあった。
今、多くの若者が挫折していく中で、このような書生っぽい文章も役に立つことがあるのだろう。
参考までに掲載する。

*******************
研究者は、原則的に個人主義である。
独自性がなければ研究という職業を続けることは困難である。
なぜなら、常に研究成果としてオリジナリティが要求されるからである。
個人主義であることが、オリジナルな発想を維持できる手段でもある。
個人主義者は、自分のことに口を挟まれることを極端に嫌がるから他人のことにも口をはさまない。
無干渉を好むのである。
そういった、扱いが困難な専門家の集まりを束ねて上手にコーディネートすることが研究リーダーの役割である。
達成しなければならない目標があって、それが個人の技能に著しく依存しない場合は号令だけで仕事ははかどるだろう。
一般的な業務では、そうした形で仕事が進められていくことが多い。
しかしながら、研究には明確な目標がない。
成果という漠然とした目標はあるかもしれないが、明確な目的地があるわけでもないし道順を示すガイドブックがあるわけでもない。
研究という職業は、地図を持たないで山に登るようなものである。
その山にしても、標高がわかっているわけでもない。
頼りになるのは、自分の体力と判断力と経験を生かしながら進んでいくので、自分で自分に責任を持つしかないのである。
だから、研究グループといっても、全員の意見が一致しているわけでもない。
琵琶湖の場合、それは水質であったり生態系であったりする。
文字で書くのは簡単だが、それらを説明することは非常に困難を伴う。
このような漠然とした水質や生態系を保全するのだが、具体的な達成目標は個人によって異なる。
環境問題一般に言えることだが、望ましい環境というのは一人一人によって微妙に異なる。
皆が同じ意見なら個性のない世界になってしまう。
だから、研究者が個性を保つことを否定するわけにはいかない。
創造的な仕事をする研究者が個性的であることが、将来の科学に対する保険だからである。
複雑で多様化する環境問題の中で人類が生き延びていくためには、多様な考え方、多様な生態系といったリスク分散が不可欠なのである。
かつてそのようなことがあったように、仮に現段階では誤りだろうと思うことでも、10年先には常識になっているかもしれない。
そういう意味で、研究のリーダーは難しい舵取りをしなければならない。
牛を水のみ場まで連れていっても、水を飲んでくれるかどうかわからない。
飲みたい気持ちにさせることが大切である。
本人の意識が高まらなければ、成果は何一つ期待できないからである。
最小努力の最大成果というのが資本主義社会の鉄則であるとするならば、研究では最大努力の最大効果を求めつづけなければならないことがたいへんな点であり、やりがいのある点でもある。
研究のリーダーとして、共同研究に参加する研究員と適度な距離を置いて、適度にエールを送りながら限られた人員と経費の中で最大限の研究成果が上がるように努めなければならない。
だんだんと予測が難しい時代になってきている。
それだけ社会そのものの変動が大きく、あわせて人間の考え方も多様化してきている。
その中で、硬直化した考え方を押し付けることがとても困難なものとなってきている。
また、環境の激変に対する予測もできないことから、柔軟で多様な考え方を許容するリーダーシップが求められているのだと思われる。
ずいぶんと青臭い意見だが、それなりに気負いもあった。
今、多くの若者が挫折していく中で、このような書生っぽい文章も役に立つことがあるのだろう。
参考までに掲載する。

*******************
研究者は、原則的に個人主義である。
独自性がなければ研究という職業を続けることは困難である。
なぜなら、常に研究成果としてオリジナリティが要求されるからである。
個人主義であることが、オリジナルな発想を維持できる手段でもある。
個人主義者は、自分のことに口を挟まれることを極端に嫌がるから他人のことにも口をはさまない。
無干渉を好むのである。
そういった、扱いが困難な専門家の集まりを束ねて上手にコーディネートすることが研究リーダーの役割である。
達成しなければならない目標があって、それが個人の技能に著しく依存しない場合は号令だけで仕事ははかどるだろう。
一般的な業務では、そうした形で仕事が進められていくことが多い。
しかしながら、研究には明確な目標がない。
成果という漠然とした目標はあるかもしれないが、明確な目的地があるわけでもないし道順を示すガイドブックがあるわけでもない。
研究という職業は、地図を持たないで山に登るようなものである。
その山にしても、標高がわかっているわけでもない。
頼りになるのは、自分の体力と判断力と経験を生かしながら進んでいくので、自分で自分に責任を持つしかないのである。
だから、研究グループといっても、全員の意見が一致しているわけでもない。
琵琶湖の場合、それは水質であったり生態系であったりする。
文字で書くのは簡単だが、それらを説明することは非常に困難を伴う。
このような漠然とした水質や生態系を保全するのだが、具体的な達成目標は個人によって異なる。
環境問題一般に言えることだが、望ましい環境というのは一人一人によって微妙に異なる。
皆が同じ意見なら個性のない世界になってしまう。
だから、研究者が個性を保つことを否定するわけにはいかない。
創造的な仕事をする研究者が個性的であることが、将来の科学に対する保険だからである。
複雑で多様化する環境問題の中で人類が生き延びていくためには、多様な考え方、多様な生態系といったリスク分散が不可欠なのである。
かつてそのようなことがあったように、仮に現段階では誤りだろうと思うことでも、10年先には常識になっているかもしれない。
そういう意味で、研究のリーダーは難しい舵取りをしなければならない。
牛を水のみ場まで連れていっても、水を飲んでくれるかどうかわからない。
飲みたい気持ちにさせることが大切である。
本人の意識が高まらなければ、成果は何一つ期待できないからである。
最小努力の最大成果というのが資本主義社会の鉄則であるとするならば、研究では最大努力の最大効果を求めつづけなければならないことがたいへんな点であり、やりがいのある点でもある。
研究のリーダーとして、共同研究に参加する研究員と適度な距離を置いて、適度にエールを送りながら限られた人員と経費の中で最大限の研究成果が上がるように努めなければならない。
だんだんと予測が難しい時代になってきている。
それだけ社会そのものの変動が大きく、あわせて人間の考え方も多様化してきている。
その中で、硬直化した考え方を押し付けることがとても困難なものとなってきている。
また、環境の激変に対する予測もできないことから、柔軟で多様な考え方を許容するリーダーシップが求められているのだと思われる。










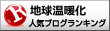

 Michio Kumagai @KumasanHakken
Michio Kumagai @KumasanHakken









