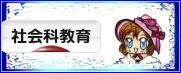今日の赤ちゃんは、台風で落ち着かないのか、寝つくのに時間がかかりました。
初めての台風なので、わけがわからなかったんだと思います。
実家に帰ると猫ちゃんがいます。
この猫ちゃんなんですが、私たちと一緒に子育てに参加しております。(笑)
赤ちゃんが泣いたら、心配して「にゃーにゃー」と声をかけ、
娘が夜に寝ると、1時間は近くで見守っております(寝ては娘を見て、そして寝て・・、という形で。同じ布団内ではありません。一定の距離は置いています。)
娘を抱いて庭のお散歩をしていると、猫ちゃんもついてきて離れません。
そして、「ここはこんなのあるよ。」と娘に教えてくれます。
こういう話をすると信じてくれない方がほとんどですし、猫によって違うので一概には言えませんが、
うちの猫ちゃんは、娘をうっとおしいな、とは思いつつも、愛してくれている

と感じております。
うちの猫ちゃんは、娘を遠くで見守り、絶対に娘を触らないし、ましてや攻撃なんて絶対しません。
娘のオモチャも触らない、娘のいる布団も端っこを歩く。
娘が起きている間は私たち(私と実母)を娘にゆずり、
娘が寝たら、私たちに甘えてくる、というとっても良い子です。
猫ちゃんは、十分遊んでもらい、たっぷり愛情をうけて三年間育ったから、
今、赤ちゃんが時々遊びに来て、騒がしいのに、赤ちゃんを愛おしいと思ってくれるんだと思います。
三年間、猫ちゃんとの散歩と格闘は大変で、寒い日も暑い日も付き合い、
遊びのケンカで私はよく血も流したが、大切なことだったんだな、と。
だから、うちの猫ちゃんや私たちが頑張っていることを何も知らないのに、
「猫は、赤ちゃんをひっかいたりするんじゃない?」
とか、
「赤ちゃんはミルクのニオイがするから猫が噛んだり、ミルクを食べたりするかもよ!」
と言われると、相手が赤ちゃんを心配して言っているのはわかるけど、ムッとしてしまうんです。
確かに、万が一のことがあるので、私のやり方が良いとは思えません。
アレルギー体質の子供だったら大変ですし、猫による圧迫や、ねこひっかき病なども心配です。
だから娘と猫ちゃんを二人きりにはしないし、
衛生上・ねこひっかき病のこともあり娘を猫ちゃんには触らせない、
食べ物・食器関係は猫ちゃんが触らないように密閉容器にしまう、
寝具も猫ちゃんしか部屋にいないときはシートをかぶせる、など配慮はしてます。
育児書にも、赤ちゃんと猫は別室に、と書いてあります。
しかし、元々猫ちゃんの部屋を間借りしているのは私たち親子なんだから、
こちらの都合で猫ちゃんを追い出すのは、教育者(母親)として、どうかと思ったのです。
猫ちゃんも大切な家族として3年間育てたんです。
それなのに、新しい家族が出来たから、と言って、家族になら到底しないことを猫ちゃんにはできるか?
いや、できません、私には!
自分勝手な教育をして、私は娘をしっかり育てられないと。
だから、大人である私たちが創意・工夫して努力して、
猫ちゃんも娘も大切な家族として接するべきだと。
幸い娘にはアレルギーもなく、
7か月間、猫ちゃんとの生活(・・といっても、実家にいるときだけですが)をしたおかげで、
動物が大好きになったようです。
猫ちゃんにも話しかけるようになりました。猫ちゃんのおかげで泣くのがとまったことがもあります。
これは情緒教育として良いことだと思います。
実は見えないところで、娘にも猫ちゃんにも気を遣い、
かなり努力した結果なのですが、何も知らない人に猫のことを批判されると怒ってしまいがちです。
相手が心配しているのはわかるのですが・・。
でも人に褒められるために教育(育児)をしているわけでなく、
家族みんなが幸せになるよう教育(育児)をしているわけなので、
自分は自分なりに頑張ればいいかな、と思います
※私のやり方が良いわけではありません。やはりケースバイケースなので・・。
※猫によっては攻撃的な子もいますので、その場合は別室の方が良いです。
※アレルギー体質の子とは別室が良いです。
ーーーーーーーーー
ランキングに参加しております。ぽちっと押して頂けるとうれしいです。
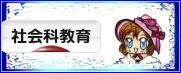
にほんブログ村






















 一つは、
一つは、 もう一つは、ワード打ちよりも
もう一つは、ワード打ちよりも

 (テストで出た内容を教えられない生徒たちにも悲劇ですし・・)
(テストで出た内容を教えられない生徒たちにも悲劇ですし・・)