11月23日道志山塊の主峰、「御正体山」を歩いてきた。
「御正体山」興味をそそる山名だ、少し 調べてみた。
調べてみた。
御正体山、御祖代山、御僧体山、三社台山、御相醍山、三僧大権現、三将台山、御招待山、
三正体山、三将大山、美生台山、味生台山、禊台山、見潮台山など。
読み方もミショウダイ、ミショウタイ、ミソタイ。
これだけ異字があるということは、何かにつけ里の人との関わりが深かったという証拠であろう。
 という結果でこれといった決めてはなかった。
という結果でこれといった決めてはなかった。
個人的には、地名・山名とも、” 納得いく理由はない”というのが結論だと思っている。
納得いく理由はない”というのが結論だと思っている。
ここは素直に「日本山名 辞典」から抜粋した。
辞典」から抜粋した。
頂上をマコゼンノ丸ともいう。かって信仰登山で栄え、山頂近くに寺院があったが、
明冶廃仏稀釈によりさびれ、頂上近くにこわれた峰宮を残すだけとなった。
 富士山を背に従えた、「
富士山を背に従えた、「 立地条件」に恵まれた山の一つだ。
立地条件」に恵まれた山の一つだ。

 :道坂隧道
:道坂隧道
左がバス停(終点)今倉山の登山口でもある。
9:08 バス停標識の裏を登って行く。
 :稜線
:稜線
 :御正体分岐
:御正体分岐
9:20 左←今倉山、右→御正体山
 :紅葉
:紅葉
落葉樹は多いが 楓や紅葉は少ない、林床はスズタケ?
楓や紅葉は少ない、林床はスズタケ? クマザサ?
クマザサ?
 :今倉山
:今倉山
アカマツ越しに見た今倉山
 :菰釣山
:菰釣山
道志山塊の山々、菰釣山、後ろは丹沢山塊
 ・御正体山
・御正体山
御正体山の肩越しに富士山が 顔を出していた。
顔を出していた。
:アザミ : トリカブト :・・・
トリカブト :・・・
 :尾根道
:尾根道
 がふりそそぐ尾根道。
がふりそそぐ尾根道。
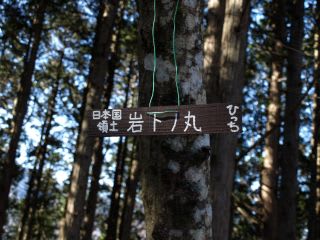 :岩下ノ丸
:岩下ノ丸
10:17 岩下ノ丸(1303m)、” 手製の個人看板が”
手製の個人看板が”
 :牧ノ沢山
:牧ノ沢山
10:45 牧ノ沢山(1292m)少し りました。
りました。
11:15 鞍部に白井平分岐か?(標示なし)南に下る道があった。
 :八合目
:八合目
白井平分岐から登りがはじまる、11:35 八合目の標示は 倒れていた。
倒れていた。
 :雪が
:雪が
富士山が雪化粧しているのに、先週登った三頭山で 気付いた。
気付いた。
山は雪がふっているのだ、北側の斜面にはかなり残っていた。
 :ブナ林
:ブナ林
一旦緩やかな道に、山頂かと思いきや、最後の登りが 待っていた。
待っていた。
 :ブナの実
:ブナの実
赤いのはブナの実です。
 :山頂
:山頂
12:00~12:35 あっけなく山頂、予定より1時間も早い、
 昼食。
昼食。
ブナやミズナラの原生林に囲まれているので 眺望はない。
眺望はない。
 :皇太子登山記念碑
:皇太子登山記念碑
12:35 予定より早いので”

 今後の対応”を、このまま降りてバスに乗らずに駅まで歩く事に。
今後の対応”を、このまま降りてバスに乗らずに駅まで歩く事に。
樹間越しの富士山です。
 :峰宮跡
:峰宮跡
13:00 「抱付岩」をトラバースし、少し登ると峰宮跡、山頂に寺院があった 痕跡だ。
痕跡だ。
小さな祠と二つの石灯篭、オブジェにしか見えなかったが・・・。
 :鹿留分岐
:鹿留分岐
13:05 鹿留分岐、唯一富士山の展望地でもある。
平成16年10月15日、皇太子が歩くために設置された標識だろうか?
各自がそれぞれの思いで富士山と会話し、シャッターを押してきた。
 :
: 虻
虻
 :下山道
:下山道
我々は 三輪神社へ降りる、単調な
三輪神社へ降りる、単調な 下りが続いた。
下りが続いた。
 :上り登山道
:上り登山道
 上り登山道、白井平分岐からの登りだろうか?
上り登山道、白井平分岐からの登りだろうか?

14:20 林道への標示
 :今倉山
:今倉山
 :鞍部が分岐
:鞍部が分岐
 :林道へ
:林道へ
 :ススキが
:ススキが
 :
:
北側の山並み、三つ峠(正面)~清八山~本社ケ丸への 稜線
稜線
 :アカマツ
:アカマツ
 :旧登山口
:旧登山口
この沢を渡り、登るが道が崩壊し、今は林道経由が メインになっている。
メインになっている。
 :三輪神社
:三輪神社
14:40  三輪神社に着いた、都留市駅へのバスは15:22発、
三輪神社に着いた、都留市駅へのバスは15:22発、 迷わず
迷わず 歩いて下る事に。
歩いて下る事に。
 :登山口
:登山口
ここが御正体入口バス停からの 登山口だった?(今は歩く人はいない)
登山口だった?(今は歩く人はいない)
 :紅葉
:紅葉
バスに乗っていれば見れなかった紅葉、
 見事でした。
見事でした。
バス停ごとに 時刻表を確認しながら歩いた、
時刻表を確認しながら歩いた、
15:18 「 熊井戸」バス停で
熊井戸」バス停で バスに乗ることにした。(バス運賃で210円分歩いたことになる)
バスに乗ることにした。(バス運賃で210円分歩いたことになる)
当初の予定通り、15:40 都留市駅着、 ホリデー快速富士山2号は16:34発
ホリデー快速富士山2号は16:34発
駅で
 時間をつぶし、帰途に着いた。電車は
時間をつぶし、帰途に着いた。電車は


 混んでいた。
混んでいた。
*

 行程:標高差682m、15km、5.5時間
行程:標高差682m、15km、5.5時間 

8:10 富士急都留市駅バス =9:08 道坂隧道登山口 ⇒9:20 御正体分岐
⇒10:17 岩下ノ丸 ⇒10:45 牧ノ沢山 ⇒11:15 白井平分岐
⇒12:00~35 御正体山:昼食 ⇒13:00 峰宮跡 ⇒13:05 分岐(富士山展望地)
⇒14:20 林道 ⇒14:40 三輪神社 ⇒⇒⇒15:30 熊井戸バス停 =都留市駅
**

 常緑樹の選択
常緑樹の選択 

 :シイの実
:シイの実
マツ、スギ、シイ等の常緑樹は1年以上枯死しない葉を持っている。
葉の表面を 光沢コートで覆った分厚く丈夫な
光沢コートで覆った分厚く丈夫な 葉で、冬も葉を落とさず、光合成を行います。
葉で、冬も葉を落とさず、光合成を行います。
そのかわり、常緑樹の 成長は、あまり速く
成長は、あまり速く ありません。
ありません。
夏の間もまわりの草木が急成長するのに比較し、 地味な成長しかしません。
地味な成長しかしません。
一年中、 長く
長く 地道に
地道に 堅実に、それが常緑樹の生き方です。
堅実に、それが常緑樹の生き方です。




























