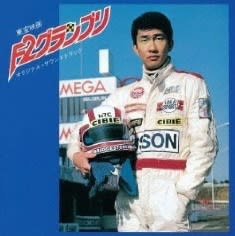(原題:STRUL )2024年10月よりNetflixから配信されたスウェーデン製のサスペンス編。面白い。何より筋書きがよく練られている。ヒッチコック映画でもお馴染みの“追われながら、真犯人を突き止める話”という普遍性の高い基本線をキッチリとキープしつつ、散りばめられたネタを上手い具合に回収。キャラクター設定も申し分ない。観る価値はある。
主人公のコニーは,ストックホルム郊外の大型家電量販店に勤務している冴えない中年男。離婚した元の妻には未練たっぷりだが、彼女はすでにエリートパイロットと再婚していた。小学生の娘とたまに会うことだけが彼の唯一の楽しみだ。ある日、配達先でテレビを設置している間に殺人事件が発生。犯人と間違われて逮捕され、有罪判決を受け、服役するハメになる。ところが刑務所内で密かに進行中だった脱獄計画に偶然関わってしまったコニーは、思わぬ形でシャバに出ることになり、自らの無罪を立証しようとする。

悪の首魁は麻薬組織なのだが、それに加担するのが警察内の腐敗分子で、捜査に紛れてコニーを抹殺しようとする。対してコニーは顔見知りだった警官のディアナの助けを得て危機突破を図る。主人公が電器店のスタッフであるという設定が出色で、重要証拠であるスマートフォンや大型テレビの扱いをはじめ、その方面のスキルに通じていることが事件の展開に大きく影響してくる。
刑務所内にはすでに外部と繋がるトンネルが掘られていたというモチーフこそ無理筋だが、それ以外はプロットは強固に構築されている。ジョン・ホルムバーグの演出は闊達かつ手堅い。展開はスムーズで淀みが無く、サスペンスの盛り上げ方も上手い。特にクライマックスのホテル内でのチェイスには瞠目させられた。また、随所に効果的なギャグが挿入されており、これが作劇にメリハリを付けている。
主演のフィリップ・バーグは当初はショボいのだが、映画が進むごとに応援したくなるほどイイ男に見えてくる(笑)。ディアナに分するエイミー・ダイアモンドは、失礼ながら普通の娯楽映画ではとてもヒロイン役に選ばれないほどの太めの外観だが、愛嬌たっぷりで魅力的だ(キャスティングの妙である)。エヴァ・メランデルにモンス・ナタナエルソン、デヤン・クキック、ヨアキム・サルキストといっ顔ぶれは馴染みは無いものの、皆的確な仕事ぶりを見せる。エリック・パーションのカメラによるストックホルムの風景も美しい。
主人公のコニーは,ストックホルム郊外の大型家電量販店に勤務している冴えない中年男。離婚した元の妻には未練たっぷりだが、彼女はすでにエリートパイロットと再婚していた。小学生の娘とたまに会うことだけが彼の唯一の楽しみだ。ある日、配達先でテレビを設置している間に殺人事件が発生。犯人と間違われて逮捕され、有罪判決を受け、服役するハメになる。ところが刑務所内で密かに進行中だった脱獄計画に偶然関わってしまったコニーは、思わぬ形でシャバに出ることになり、自らの無罪を立証しようとする。

悪の首魁は麻薬組織なのだが、それに加担するのが警察内の腐敗分子で、捜査に紛れてコニーを抹殺しようとする。対してコニーは顔見知りだった警官のディアナの助けを得て危機突破を図る。主人公が電器店のスタッフであるという設定が出色で、重要証拠であるスマートフォンや大型テレビの扱いをはじめ、その方面のスキルに通じていることが事件の展開に大きく影響してくる。
刑務所内にはすでに外部と繋がるトンネルが掘られていたというモチーフこそ無理筋だが、それ以外はプロットは強固に構築されている。ジョン・ホルムバーグの演出は闊達かつ手堅い。展開はスムーズで淀みが無く、サスペンスの盛り上げ方も上手い。特にクライマックスのホテル内でのチェイスには瞠目させられた。また、随所に効果的なギャグが挿入されており、これが作劇にメリハリを付けている。
主演のフィリップ・バーグは当初はショボいのだが、映画が進むごとに応援したくなるほどイイ男に見えてくる(笑)。ディアナに分するエイミー・ダイアモンドは、失礼ながら普通の娯楽映画ではとてもヒロイン役に選ばれないほどの太めの外観だが、愛嬌たっぷりで魅力的だ(キャスティングの妙である)。エヴァ・メランデルにモンス・ナタナエルソン、デヤン・クキック、ヨアキム・サルキストといっ顔ぶれは馴染みは無いものの、皆的確な仕事ぶりを見せる。エリック・パーションのカメラによるストックホルムの風景も美しい。