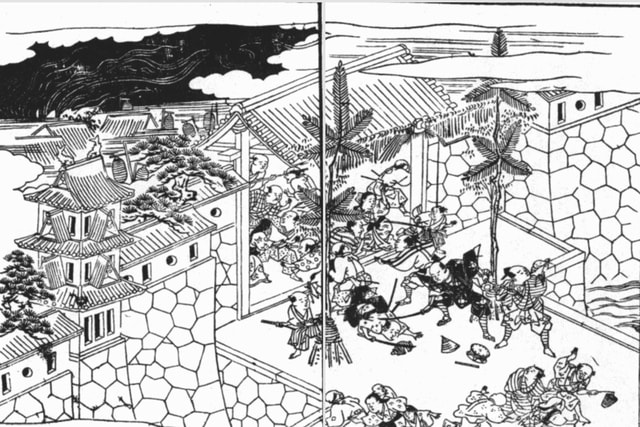稽古場の茶掛に「脚下照顧(きゃっかしょうこ)」の言葉がありました。師走のあわただしさに、我を忘れないようにという戒めなのだと思います。
これは道元禅師の言葉で、自分の足元をよく見よ、という意味から転じて、人のことをあれこれ言う前に、自分自身を振り返ってみよ、という風に解されたりします。
道元は、しかしもっと即物的な意味で「脚下」を捉えていたようで、履き物をきちんとそろえることを、日々の修行のなかに取り入れていたのだそうです。自らの履き物もそろえることができないのは、心が乱れている証拠なのだと。
忘年会の季節ともなると、たくさんの靴が並べられた景色を見ることになります。
並んだ靴を見ていると不思議な感覚にとらわれます。ついさっきまで履いていた本人と行動を共にしており、本人の「今」を体現していたものが、玄関先で突然「今」から切り離されて、そのまま黙って他の靴たちと並んでいます。
他の靴もついさっきまで「今」を体現していたのだとすると、靴たちは、それぞれの「過去」を背負ったまま仲良く並んでいて、その様子は、まるで並んで立つ墓標のようだと思ったりします。
履き物を脱ぐという行為は、そうしてみると自分の過去を、ひと様の前にさらけ出すということにも等しいのではないか。脱いだ履き物をそろえることは、さらけ出す自分の過去に、きちんと向き合うことになるのではないか、などと考えます。
以前勤めていた会社に、元ホテルマンという人がいました。その人が、外回りに出かける上司や同僚に対して大きな声で「いってらっしゃいませ」と声掛けするのです。私はついに、この掛け声に唱和する勇気がなかったのですが、その人の「人に会ったら必ず靴を見る」という言葉は忘れられず、30年以上経った今でも出かける前に、靴に布を当てるようにしています。靴の手入れを小まめにする人は、身だしなみ全てに気を配る人だからだ、と捉えていたのですが、「脚下照顧」の言葉について考えるうちに、もっと別の意味合いも込められるような気もします。
靴をきれいに保つこと、きちんとそろえて置くことは、いずれひと様に見られる過去の姿からさかのぼって「今」を丁寧に生きることではないのか。「脚下照顧」とは、今の自分自身を省みなさいという意味にとどまらず、ここに至るまでの過去に責任を持ちなさいという意味も込められているのではないか。茶掛に触発されて、そんなことを考えました。