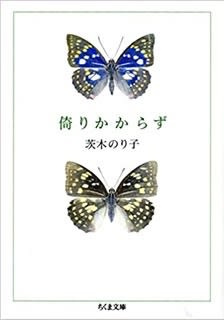1992年に刊行された『食卓に珈琲の匂い流れ』という茨木のり子の詩集に、「問い」という詩が収められています。
問い
人類は
もうどうしようもない老いぼれでしょうか
それとも
まだとびきりの若さでしょうか
誰にも
答えられそうにない
問い
ものすべて始まりがあれば終りがある
わたしたちは
いまいったいどのあたり?
颯颯の
初夏の風よ
私はこの詩を、希望の歌としてとらえていました。「颯颯(さつさつ)の/初夏(はつなつ)の風よ」という最後の呼びかけによって、詩全体が大きなものに包まれている印象を与えるからでしょうか。
老木に若葉が芽吹き、花々が一斉に顔を覗かせるこの季節の、力強く誠実な自然の営み、円環を描くような堂々とした成長を前にして、「それでは人類は?」と詩人は問うたのだと、いま改めて思います。
目を覆う悲惨を前にして、人類が営々と築いてきたはずの何もかもが機能しない今というときに、「もうどうしようもない老いぼれ」という言葉が、むしろ正しく人類を言い表しているように感じます。
哲学者の長谷川宏は、茨木のり子との共著『思索の淵にて』(近代出版)のなかで、茨木の「問い」に寄せて次のように述べています。
核戦争による人類死滅のイメージは、個人の自然死にともなう安らかさや静けさがかけらもない。あるのは、陰惨きわまる集団的な殺意と殺害行為ばかりだ。
否定一色に塗りつぶされた陰惨な人類の死でも、しかし、死は死だ。まがりなりにも人類の死が想定できるなら、人類の一生も考えられるのではないか、漠然とそんなことを考えているとき、歴史家の衝撃的なことばに出会った。さきごろ亡くなった網野善彦の最晩年の著作『「日本」とは何か』(講談社・日本の歴史第00巻)の書きだしの一節である。「人類社会の歴史を人間の一生にたとえてみるならば、いまや人類は間違いなく青年時代をこえ、壮年時代に入ったといわざるをえない。」(192-123頁)
長谷川じしんは人類が壮年時代に入ったという断言には賛同できないものの、どこからか肌寒い風が吹いてくるようで、それに耐えながら地に足をつけて歴史を考えなければ、と文章を結んでいます。
私も現下の状況のなかで「問い」の詩を読むときに、肌寒い風が吹いてくるのを感じますが、それが「颯颯の初夏の風」にふっと置き換わることも夢想するのです。人類が滅んだあとも初夏の風が吹き抜ける様子です。
かろうじて人類がその壮年期を生き抜き、老年期を生き切ったとして、最後まで静かにその風を感じているのならば、それも受け入れるべき一生なのかもしれないと、そう思います。