唐松林の中に小屋を建て、晴れた日には畑を耕し雨の日にはセロを弾いて暮したい、そんな郷秋<Gauche>の気ままな独り言。
郷秋<Gauche>の独り言
考える人、1962年を語る
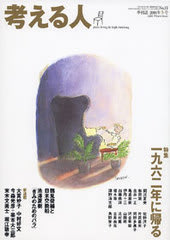
発売のたびに紹介しているが、またまた新潮社の季刊雑誌『考える人』の2006年冬号の話題だ。またか、と思われる方もおいでかとは思うけれど、暮れの30日にも予告めいたことを書いてもいるのでお待ちの方のためにも書かざるを得まい(ホントにいるのか?待ってる人って)。
29日の夜に冬号が発売になっているのを思い出して駅前の書店に買いに行ったのだが、ちょっと驚いた。一時はほんの数冊しか置かれていなかった『考える人』が創刊号の時ほどではないにしても、平積になっていたのだ。毎回予告の通りに次号が出るのか、あるいは休刊と言う名の廃刊のお知らせが出るのではないかハラハラドキドキしていたのだが、ようやく固定客を掴んで売り部数が安定したということなのだろうか。そうだとすれば同慶の至りである。
さて、今号の特集は10月にも書いたとおり「1962年に帰る」である。1964年ならば東京オリンピックが開催され新幹線が開通した年として、つまりそれまでの古き良きものを捨て、今の日本に通ずる道を一気に走り出した年として記憶されているが、1962年とはいかにも中途半端である。しかし、決して奇を衒ったわけではなく「1962年」の必然性がそこに潜んでいることは、幾つかの記事を読めばお気付きになることができるだろう。
1962年、それは60年安保と64年の東京オリンピックの狭間であり、ビートルズが下手クソな歌でデビューした年、マリリン・モンローが死んだ年だ。テレビの普及率が48.5%に達し、NHKテレビが昼の放送休止をやめたのもこの年だ(それまでは午後2時頃から4時頃まで放送を休んでいた、はず)。大学文学部の女子学生比率が87%になり「女子大生亡国論」が起きたのも、小沢征爾がN響からボイコットされたのもこの年だ。
いかにも『考える人』らしい切り口は都野海太郎氏が「時代の空気」と出して書いた4ページの記事である。「花森安治が半世紀前につくりあげた雑誌のかたちは、マネできない。それは花森の天才性と思想を生んだその時代の空気というものがあるからだ。」
お気づきになられたであろうか。津野氏は『暮らしの手帳』をテキストにして1962年と言う時代性を読み取ろうとしているのだ。
特集記事以外も見ておこう。写真家今森光彦氏はご自分のフィールドである琵琶湖畔から離れ新しい連載「ファーブルの地で昆虫を追う」を始めた。赤瀬川源平氏の「大和魂」は今号が最終回となる。小谷野敦氏の「売春の日本史」、小林照幸氏の「中村悟堂の空」、山川みどり氏の「六十歳になったら」は好評(?)のうちに連載継続。
平松洋子氏の二本の連載「季節には味がある」と「台所でにっこり」を読むと、先にも出た『暮らしの手帳』をいつも思い出す。目次の中で連載記事をふた色に分けているが、その一方が「high thinking」もう一方が「plain living」となっているが、後者は『暮らしの手帳』が目指したもの、そのものではないか。思い出して当然なのである。
2006年冬号は(大手書店にて)ただいま発売中。
季刊誌「考える人」2006年冬号 新潮社
B5判 302頁 定価1,400円(税込み)
コメント ( 0 ) | Trackback ( )






