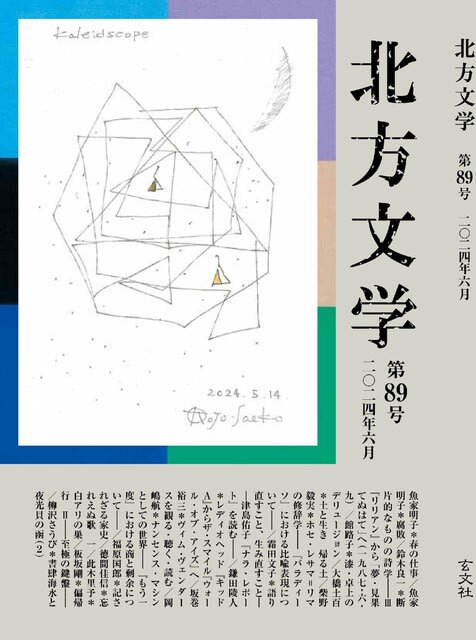「北方文学」第90号を発行しましたので、紹介させていただきます。今号は90号記念号なのでしたが、その割にはボリュームがありません。80号記念号などは300頁以上でしたのに、少し残念な気がします。
評論が多いのが「北方文学」の特徴ですが、今号もロック評論あり、紀行文あり、音楽エッセイありといった具合で、文学のジャンルにとらわれない内容になっています。しかもいずれも力作で、文学のおまけとして雑誌の片隅に載っているというようなものではありません。
巻頭は鈴木良一の「断片的なものの詩学――Ⅳ」「エフェメラを手に、幼年期の回想」です。エフェメラとは一時的な印刷物のことだそうで、昔の演劇のチラシなどを繰るうちに、作者の中に詩や幼いころの思い出などが生起してきます。鈴木が生まれる前、一九二六年木崎村小作争議の思い出も、母の語りで甦ります。
次いで魚家明子の詩2篇。「白」と「壁」です。最近の魚家の作品は文が短く、息が短いのが特徴。ついにタイトルまで短くなってしまいましたが、そこにあるのはある種の切迫感に他なりません。平易な言葉で書かれているのに、不穏な気配が漂っています。
三人目は館路子の「晩夏・楽曲の彼方へ蝶を見送る」。魚家とは反対に息の長いのがこの人の特徴。数千キロの海を渡るアサギマダラをモチーフにして、蝶と自身との息の長さを共有していきます。蝶の美しさもまた、詩文の美しさの中に共有されています。
批評はまず、霜田文子の「パサージュ、遊歩者あるいは夢」です。パリのギャルリー・ショワズールでの個展を機に書かれたものです。導入部のパサージュ散策など断片的で、まるでヴァルター・ベンヤミンの『パサージュ論』そのものみたいですが、徐々に議論が深まっていきます。ボードレールのコレスポンダンスの詩学に影響を受けたベンヤミンに寄り添い、散策の中で間断なき思考を続ける筆者には、ベンヤミンが乗り移ったかのような印象があります。
鎌田陵人は前号でも、スマイルの「ウォール・オブ・アイズ」ついて、本格的な評論を書いていますが、今号は今年10月に出たスマイルの新アルバム「カットアウツ」について論じたものです。Cutoutは切り取られた部分の意味ですが、映像や音楽ではいきなり消える手法を意味しています。「切断の美学」というタイトルもそこから来ていますが、全10曲のそれぞれについて〝切断〟をキーワードに分析していきます。最後にはバンド名Smileのもとになったと言われている、イギリスの詩人テッド・ヒューズの作品にも触れています。
次は徳間佳信の「忘れ得ぬ歌(2)」。音楽エッセイとして始まられたこの連載は、2回目にしてすでに本格的な文化論、社会論、政治論としての輪郭を見せつつあります。取り上げられている歌は、一青窈カバーの「雨夜花」、テレサ・テンカバーの「何日君再来」、平原綾香カバーの「蘇州夜曲」の3曲。いずれも台湾・中国に関係する曲です。「蘇州夜曲」だけが日本人の作詞・作曲になるものです。「雨夜花」と「何日君再来」は政治的理由から不幸な履歴を辿った歌で、政治の愚劣さが名曲を貶めるという経緯を著者は語っています。
坂巻裕三の「荷風と二人の淳 Ⅱ(上)」が続きます。一人目の淳は石川淳でこれまでに済ませてあります。二人目の淳は批評家・江藤淳で、この人の荷風評価を巡っての議論が2回続くことになります。江藤淳は『漱石とその時代』などを読めば、私小説的な批評家であったことがよく分かります。そのような視点から江藤の生涯を追っていますが、まだ荷風評価の部分には進んでいません。(下)でそれが展開されるのを待つことにしましょう。
霜田のパリ個展応援のために渡仏した一人として、柴野は一日だけ単独行動を行います。フローベールの故郷ルーアンの、ルーアン大聖堂にある彫刻を見るために行ったのですが、他にも様々な教会とその塔を見ることになりました。ルーアンの街は歴史的景観の保存状態が素晴らしく、すっかり気に入ってしまいました。そんな紀行文です。
福原国郎の「旧制長岡中学の戦時」は、現長岡高校に残された資料によるもので、講演にやって来た山本五十六に触発されて予科練に進み、飛行機乗りとして戦争を体験した何人かの同窓生(この中には特攻して戦死した者もいます)と、学徒動員で名古屋の工場で働き、空襲を体験した多くの同窓生のことが記されています。戦後新制高校となった長岡高校の講堂に掲げられた、山本の肖像の左胸にナイフが突き刺されるという事件があったという記述は興味深い。
今号の小説は3本あります。最初は小説初挑戦の海津澄子による「見よ、それはきわめて良かった」です。いわゆるLGBTの問題を身近なものとして取り上げた作品で、カトリック教会批判をも含んでいます。作者の好きなノーベル賞作家、アニー・エルノーの問題意識に近いものを感じます。
2番目は板坂剛の「偏帰行」連作の3作目になる「神戸の空の上で」。前作で大人のメルヘン的な要素が垣間見られましたが、今作ではさらにそういった要素が強まっているように感じます。なにせ、自らの葬儀に立ち会い、神戸の空の上にいる父親と再会し、次に生まれ変わるべき胎児を幻視して終るのですから。
最後は柳沢さうびの「書肆海水と夜光貝の函」の3回目です。柳沢の小説はずっと舞台や時代を特定できないものでしたが、この作品は明らかに柏崎市が舞台で、時代は昭和30年代あたりということが分かるようになっています。このまま終わるとすればかなり異色の作品ということになりそうですが、何か仕掛けがありそうな予感もします。いずれにせよあと一回で連載は終わります。
目次
鈴木良一 断片的なものの詩学――Ⅳ「エフェメラを手に、幼年期の回想」
魚家明子 白+壁
館路子 晩夏・楽曲の彼方へ蝶を見送る
霜田文子 パサージュ、遊歩者あるいは夢
鎌田陵人 切断の美学——ザ・スマイル『カットアウツ』——
徳間佳信 忘れ得ぬ歌(二)
坂巻裕三 荷風と二人の淳 Ⅱ(上)
柴野毅実 塔の町ルーアンへ
福原国郎 旧制長岡中学の戦時
海津澄子 見よ、それはきわめて良かった
板坂 剛 偏帰行Ⅲ 神戸の空の上で
柳沢さうび 書肆海水と夜光貝の函(3)
玄文社の本は地方小出版流通センターを通して、全国の書店から注文できます。