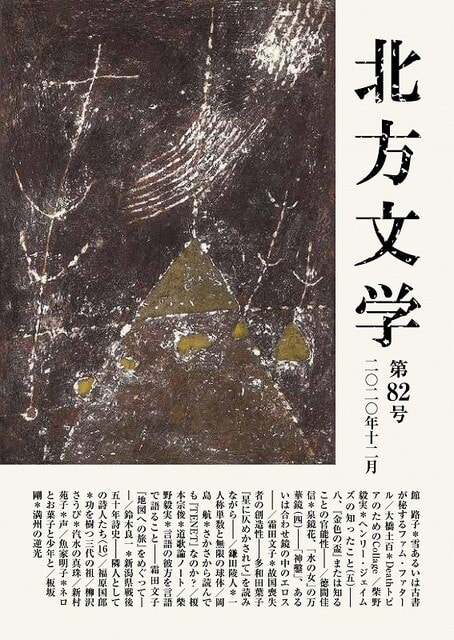
「北方文学」第82号が発刊になりましたので、紹介させていただきます。80号、81号と同人の死が相次ぎ、追悼特集を余儀なくされましたが、今号は幸い追悼の必要はありませんでした。それにも拘わらず264頁の大冊となり同人の旺盛な創作意欲を感じさせます。
巻頭に館路子のいつもの長詩。このところ動物をモチーフとした作品を書き続けてきましたが、今号の「雪あるいは古書が秘するファム・ファタール」では動物は登場せず、谷崎潤一郎の「細雪」と「春琴抄」がモチーフとなっています。しかも大正生まれの母親が残した昭和24年の粗悪な紙質のそれらの本は、母の記憶をも呼び起こします。なにか書評を思わせるような一編です。
詩がもう一編。大橋土百の「DeathトピアのためのCollage」。いつもの俳句ではなく現代詩で、大橋独特の土着的精神は感じられず、意外な面を見せています。本人によれば、若い時に西脇順三郎の作品を読んで大きな影響を受けたのだそうで、それを知れば意外でもないのかもしれません。ちょっと古い感じの現代詩的な言葉使いが全編を覆っています。
批評が6本続きます。それぞれテーマはバラバラですが、批評の比重が高いのが「北方文学」の最大の特徴ですから、本来の姿と言えるでしょう。文学論がほとんどですが、映画論も一本あり、対象は何であれ批評精神の発動こそ大事にしなければならないものと思っています。
最初は柴野毅実の連載「ヘンリー・ジェイムズの知ったこと」の5回目で完結編。『金色の盃』を取り上げます。これまで論じてきたセクシュアリティということの論理的な展開のために、ミシェル・フーコーの『性の歴史Ⅰ 知への意志』とスティーヴン・マーカスの『もう一つのヴィクトリア時代』を参照して、議論を進めていきます。作品に即しながらヘンリー・ジェイムズにおけるセクシュアリティと知との関係に迫ります。これまでの総集編ということで長い論考となっています。
次は徳間佳信の「泉鏡花、「水の女」の万華鏡」の4回目。今回は「神鑿」を取り上げます。いつも鏡花のマイナーな作品ばかりが出てきますが、メジャーな作品にも共通するエロティシズムの論理の追究が行われています。今回は人形というものに対するフェティシズムがその対象となっています。
次に掲載された霜田文子の「故国喪失者の創造性」は、多和田葉子の『星に仄めかされて』についての批評です。越境の文学ということが言われますが、霜田はベンヤミンの翻訳論を借りて、言語と言語を媒介するものとしての純粋言語について語ります。それこそが故国喪失者の創造性を生み出すのだという議論です。
鎌田陵人の「一人称単数と無限の球体」は村上春樹の最新短編集『一人称単数』についてのいささか意地の悪い批評になっています。鎌田は一人称単数ということについて、シュレーディンガーの「意識の単数性」という疑念を持ち出して嗾けていますが、勝負は言うまでもないでしょう。村上の思わせぶりな円についてのなぞなぞについても、パスカルの『パンセ』に出てくる無限球体の概念を対峙させていますが、こちらも同様。
岡島航は前号に引き続いて映画論。2020年のアメリカ映画で最も話題となったクリストファアアー・ノーランの「TENET」における、時間の逆行についての議論を展開しています。逆行にあっても主観時間は常に巡航しているというパラドックスを解く鍵はしかし、ノーランの映画それ自体の中にはないのかも知れません。
批評の最後は榎本宗俊の「道歌論ノート」。いつものように仏教論であり、結論は「南無阿弥陀仏」ということになるのですが、これもまた自らの精神史に即しての批評なのであります。
書評が一本。11月に玄文社から刊行された、霜田文子の『地図への旅』についての書評です。題して「言語の彼方を言語で語ること」。言語ならざる世界を言語で語る美術批評の宿命的なあり方のみならず、この本の中核をなすアール・ブリュット的な絵画に対する著者の対峙の仕方についての本質的な議論を展開しています。
以上批評、以下は研究ということになります。鈴木良一の大連載「新潟県戦後五十年詩史」の今回は1981年から1985年の後半を取り上げています。1980年から1986年まで新潟市に居住した福田万里子が、新潟県の詩の世界に果たした役割について書かれた部分が今回の中心でしょうか。
福原国郎の「功を樹つ三代の祖」は小千谷市旧真人村の庄屋であった先祖の功績を、福原家に伝わる古文書等を読み解いて実証的に検証する試みです。先号のテーマであった長岡高校の歴史から、彼本来のテーマに戻っての、いつもながら見事な研究です。
最後に小説が4本続きます。小説が4本並ぶというのも久しぶりのことではないでしょうか。最初は柳沢さうびの「汽水の真珠」。ある女性に寄生する何ものかの語りとして小説は進行していきます。それがいったい何なのかという謎は最後まで明かされません。ただし「汽水に生息するくじゃく貝」の作り出す虹色の真珠が、何ものかの象徴として機能しているとすれば、真珠の元となる異物こそがその正体かも知れません。つまり女性の肉体と精神に関わる異物、つまりは自己同一性を阻害する何か。濃厚な小説です。いつもながら見事なタイトル。
大ベテランの新村苑子の「声」が続きます。強姦され祝福されざる子供を産み、その子を失った女性と、ベトナム戦争から日本に逃れてきた、祝福されざる存在としてのあるベトナム人神父との出会いを描く。設定がいいですね。宗教小説として読むこともできます。
一番の若手である魚家あき子の「ネロとお菓子と少年と」は、彼女独特のファンタジーの世界になっています。口からお菓子が出てくる女性と、不思議な少年と犬との出会いをファンタジックに描いています。会社の同僚との関係の中で口からお菓子が出なくなり、少年も犬も消えていなくなってしまいます。
最後は板坂剛久々の作品「満州の逆光」です。「満州国再興計画」なるものをめぐっての謎に満ちた探索行。歴史幻想小説と言っていいかも。通俗的なプロットかも知れませんが、最後まで飽きさせずに読者を引っ張っていきます。2号前の「幕末の月光」に似た手法ですね。
目次を以下に掲げます。
館 路子*雪あるいは古書が秘するファム・ファタール
大橋土百*DeathトピアのためのCollage
柴野毅実*ヘンリー・ジェイムズの知ったこと(五)――八、『金色の盃』または知ることの官能性――
徳間佳信*泉鏡花、「水の女」の万華鏡(四)――「神鑿」、あるいは合わせ鏡の中のエロス――
霜田文子*故国喪失者の創造性――多和田葉子『星に仄めかされて』を読みながら――
鎌田陵人*一人称単数と無限の球体
岡島 航*さかさから読んでも『TENET』なのか?
榎本宗俊*道歌論ノート
柴野毅実*言語の彼方を言語で語ること――霜田文子『地図への旅』をめぐって――
鈴木良一*新潟県戦後五十年詩史――隣人としての詩人たち〈16〉
福原国郎*功を樹つ三代の祖
柳沢さうび*汽水の真珠
新村苑子*声
魚家明子*ネロとお菓子と少年と
板坂 剛*満州の逆光
お問い合わせはgenbun@tulip.ocn.ne.jpまで。











