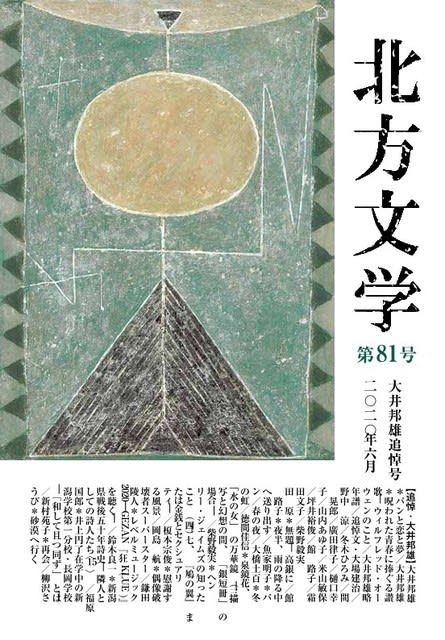この小説の最初に出てくるのは印刷業界である。ダヴィッドの父ジェローム・ニコラ・セシャールは無学の印刷工で、フランス革命恐怖政治の時代に、死んだ親方の後を引き継いで免状を取得し、印刷屋の経営者となる。セシャールは貪欲でずるがしこい男であり、職人を酷使し、息子に対しても厳しい扱いをするのだった。
「学校の休みの日は《お前を育てるのに骨身をけずってはたらいた気の毒なおやじに恩がえしできるようにしっかり世渡りの道をおぼえろよ》といいながら、息子に活字ケースにむかってせっせと働かせた。」
バルザックは印刷業界内部における階層についても詳しく書いている。印刷工は文字が読めなくてもできる仕事であり、文選工はそうではないから、自ずからそこにインテリジェンスの違いというものがある。確かに現代の日本においても50年くらい前までは活版印刷が主流であったから、文選工は印刷工を馬鹿にしていたし、印刷工は文選工に対してコンプレックスを抱いていたように思う。
文選工は植字工を兼ねることもあったし、校正さえ自分でやっていたケースもあったから、頭の良いダヴィッドは父にとってこき使うのにはまことに重宝な息子であったに違いない。このように1775年頃のフランスの田舎の印刷業界も、それから200年後の日本の印刷業界もそれほど大きな違いはないということを、『幻滅』の冒頭部分は教えてくれるのである。
活版印刷は15世紀にグーテンベルクによって発明された技術であるが、つい最近まで基本的にはテクノロジーに大きな変化はなかったのである。どんな業界でもそうであるが、画期的にテクノロジーが進展していくのは20世紀中頃からであり、それまでは労働集約型の産業が主流であったのだ。またその後、印刷業界は革命的なテクノロジーの進展の波に洗われることになるが、それをもたらしたのはもちろんコンピュータの進化であり、その点でも他の産業と大きな違いはない。
いずれにしても『幻滅』の冒頭部分は、田舎の印刷業界の実体を手に取るように教えてくれるのである。セシャールのダヴィッドに対する言葉は、しかし尋常ではない。父親としての扶養の恩を働いてしっかり返せというのはわかるとしても、「気の毒なおやじ」という言い方には何か冷酷なものがある。しかも《しかり世わたりの道をおぼえろよ》というのだから、息子にも自分のように世渡りがうまくて商売上手な人間になれと言っているのである。
このような父子の関係を、実は私も経験している。私の父も印刷屋の社長であって、世渡りがうまくて商売上手だった。印刷業というのは官公需が主体であったから、役人にうまく取り入って仕事をもらうというのが、印刷屋の経営者の最も重要な仕事であった(そこに飲食の接待も含まれるのは当然である。現在では許されないことだが、時効だろうからあえて書いておく)。
したがって、学問などというものは無駄なぜいたくでしかなかった。ダヴィッドの父も学問を馬鹿にしていたが、高度な印刷術を学ばせるためにだけ息子をパリに修行に出す。私も印刷屋の手伝いを小学校3年生の時からやらされ、実業高校に進学するよう父に勧められたが、そんなあり方も19世紀のフランスの田舎の事情と大差はなかったのである。
私は幸い普通高校に進学し、大学で文学を学ぶというまったくの無駄(あるいは家業のためにはマイナスであったかもしれない)な時間を与えてもらったが、家業を継いでからある時期までは、比較的従順に父親の言うことに従い、とても厭だった役人接待などの仕事もこなしてきた。私は世渡りはうまくなかったが、結構商売上手だったのである。
しかしダヴィッドには実業の素質が全くと言っていいほど欠落していたし、父親との不当な契約によって高い家賃やおんぼろな機械の賃貸料を実の親に払うことを強いられ、経営は逼迫していく。この親父は『ウジェニー・グランデ』の父グランデ氏によく似ているが、グランデ氏が娘の将来を考えようとしない以上に、息子に足枷をはめ経営が成り立たなくさせてしまうのだから、こちらの方がたちが悪い。
しかしダヴィッドは従順で気の優しい男である。次のような台詞は彼の素性をよく表している。
「《働こう》と、彼は心にいった。《とにかく、今のおれは苦しいが、親父だって、苦労したんだ。それに、自分のためにはたらくのじゃないか?》」