
南魚沼市出身の文芸評論家井口時男氏の講演会が、
7月1日南魚沼市浦佐の池田記念美術館で開催されます。
東京の同人雑誌「群系」と新潟の同人雑誌「北方文学」、
柏崎市の文学と美術のライブラリー「游文舎」の共催です。
チラシをご覧ください。

南魚沼市出身の文芸評論家井口時男氏の講演会が、
7月1日南魚沼市浦佐の池田記念美術館で開催されます。
東京の同人雑誌「群系」と新潟の同人雑誌「北方文学」、
柏崎市の文学と美術のライブラリー「游文舎」の共催です。
チラシをご覧ください。

「北方文学」86号紹介
「北方文学」第86号を発行しましたので、紹介させていただきます。先号発行の直後の7月7日に、古くからの同人米山敏保氏が胆嚢癌からの転移で亡くなりました。これで創刊61年を迎えた「北方文学」の第1次同人すべてが鬼籍に入ってしまいました。追悼特集を組むことにしました。米山氏がまだ20歳代だった頃の短歌作品と中期の小説作品を再録し、略年表を編集し、追悼文を数編載せてあります。老成した米山氏しか知らない我々にとって、若い時の短歌は目の覚めるような瑞々しさを持っています。また女性を描いて名人の域にあった米山氏の小説もお楽しみください。
巻頭は魚家明子の詩2篇、「骨」と「さびしい石」です。彼女の短い詩作品は緊張感に溢れていて、詩人としての生きにくさを「ひりひりと」感じさせるものがあります。どの1行も無駄がなくて、完成の域に達していると思います。
二人目は館路子の「幽かな秋の時間の、狭間」。いつもの長詩で、魚家の作品とは対照的です。動物や植物が総出演でにぎやかですが、執筆者紹介に「庭の松に鳩、鵯、雀が来てそれへ語り掛けるように家猫が啼く。家に近い用水路には白鷺、アオサギを時々は見る。詩の素材はおのずと空から来て呉れる」とあるので背景が分かります。詩の言葉が動物の鳴き声のように空から降って来るのだとすれば、なんと幸福な。
続いて大橋土百の俳句「海境のゆらぎ」。一年間の思索ノートからの俳句選であるため、作風は様々ですが、土百らしい諧謔に満ちた句もあり、シリアスな句、時代と切り結ぶ句もあって、いつものように楽しく読むことが出来ます。
昨年6月11日に柏崎の游文舎で開かれた、高橋睦郎氏と田原氏の対談録を載せました(本文は6月22日となっていますが、間違いでした)。俳句と短歌との違いから始まって、世界における俳句の独自性、「和魂漢才洋識」という視点から見た日本近代文学のあり方、さらには高橋氏の世界の文豪たちに問うという姿勢など、充実した内容でスリリングな対談となっています。同人雑誌にこのような講演録を載せることが出来ることを、誇りに思ってもいいのではないでしょうか。
批評はまず、昨年東京国立近代美術館で開催された、ゲルハルト・リヒター展の、霜田文子による展覧会評から始まります。題して「「描かれた《ビルケナウ》」の向こう——ゲルハルト・リヒター展を観て」。ナチスドイツのユダヤ人収容所ビルケナウで、ゾンダーコマンドが隠し撮った写真をもとにした、リヒターの《ビルケナウ》という連作についての分析が主体となっています。ベンヤミンの「絵画芸術あるいはツァイヒェンとマール」という論考を参照している部分で、〝媒質としての絵画〟に言及しているところがあり、ちょっとびっくりさせられるような視点で書かれています。リヒターの最高傑作とされる《ビルケナウ》への評価に、やや疑問を呈しているところも興味深いのではないでしょうか。霜田でなければ書けない一篇です。
次は柴野毅実の「『テラ・ノストラ』のゴシック的解読――カルロス・フエンテスの大長編を読む――」です。このところ柴野が追求しているゴシック論の一端で、メキシコの作家フエンテスの最高の問題作とされる『テラ・ノストラ』を、ゴシック小説の視点から解読しようという試みです。完読されるのをフエンテスが嫌がったといういわくつきの作品ですが、ゴシック小説、特にチャールズ・ロバート・マチューリンの『放浪者メルモス』を参照することで、糸口をつかむことが出来ます。今回は前半まで、後半の展開が待たれます。
岡嶋航の「backrooms――あるいは無限の空間について——」が続きます。ネット上に拡大再生産されるbackroomsという動画に最初に触れ、無限というもののもたらす不気味な恐怖について論じていきます。ヴィンチェンゾ・ナタリ監督の映画「キューブ」や、マリオ・レブレーロの小説『場所』を参照することで、広場恐怖症と閉所恐怖症の並列性という結論が導き出されます。スリリングな論考です。
漫画論「背中は見えない——藤本タツキ『ルックバック』」という漫画論は、このところサブカルチャーを論じることの多い鎌田陵人によるもの。前号で映画「悪魔のいけにえ」を論じた鎌田は、それに影響されて描かれた藤本の「チェンソーマン」から、「接続」と「切断」というテーマを剔出して、『ルックバック』についても論じていきます。
榎本宗俊の「食養生」が続きます。かつての日本人の食に関わる短歌を紹介しながら、現在は失われた食に関わる豊かさや健康への志向について論じていきます。
研究では、鈴木良一の「新潟県戦後五十年詩史――隣人としての詩人たち〈20〉」が完結を迎えました。資料集めの段階から数えれば20年がかりのこの労作は、ずっと注目を集めてきましたし、労多くして功の少ないこの種の研究の割には高い評価を得て来たと思います。日本広しといえども、どこの県にもこのような詩史は存在しません。新潟県だけに止まらず、中央の詩壇にかかわる部分もあり、この労作は全国の詩人にとって、今後スタンダードとして位置づけられるでしょう。扱ったのは1995年まで。今後誰かが2022年までを補塡することがあるとはとても思えません。
坂巻裕三の永井荷風研究「麻布市兵衛丁「偏奇館」界隈、時間と空間」が続きます。荷風は大正9年、実家の「断腸亭」を売却して、麻布市兵衛丁に「偏奇館」を建てて移り住みますが、それまでの外国遊学、就職、帰国後の放蕩生活のすべてが親がかりだったことからの離脱を志したものと見ています。当時の重要な作品「花火」や「震災」『濹東綺譚』を取り上げながら、情け容赦もなく変わりゆく東京の都市風景への荷風の違和感について語っていきます。そこには坂巻自身の変貌を重ねていく同時代への違和感と共通するものがあるようです。
小説は2本あります。まず板坂剛の「イビサの女」。いつものように差し引きゼロに終わる虚構らしい虚構の世界です。短くて読みやすく、破綻がありません。読後たとえようもない人生に対する虚しさを感じないではいられません。
柳沢さうびの「瑠璃と琥珀」は先号の「えいえんのひる」との連作になっています。登場人物の枠組みはそのままに、視点を変えて書かれています。当然、文体を変えていく必要がありますが、柳沢はその難題に見事に答えています。「えいえんのひる」で示された謎が解明されていきます。すでに名人の域に達した彼女の作品の評価が期待されます。
以下目次を掲げます。
館路子*幽かな秋の時間の、狭間/魚家明子*骨/魚家明子*さびしい石/大橋土百*海境のゆらぎ
【追悼・米山敏保】米山敏保*薄日射/米山敏保*池の記憶/米山敏保略年譜/追悼文・福原国郎*「何のことはない」/徳間佳信*古備前の徳利――米山さんの思い出に代えて――/柳沢さうび*「百済仏なんて博物館にしかない」
【高橋睦郎×田原 対談録】俳句と現代詩の世界
霜田文子*「描かれた《ビルケナウ》」の向こう――ゲルハルト・リヒター展を観て――/柴野毅実*『テラ・ノストラ』のゴシック的解読――カルロス・フエンテスの大長編を読む(上)――/岡嶋 航*backrooms――あるいは無限の空間について――/鎌田陵人*背中は見えない――藤本タツキ『ルックバック』――/榎本宗俊*食養生について/鈴木良一*新潟県戦後五十年詩史――隣人としての詩人たち〈20〉/坂巻裕三*麻布市兵衛丁「偏奇館」界隈、時間と空間/板坂剛*イビサの女/柳沢さうび*瑠璃と琥珀
お問い合わせは玄文社、genbun@tulip.ocn.ne.jpまで。

みんなこの街のどこかに住み、働きながら
音探しの旅を重ねている
自分が自分で在り続けるために
(石川眞理子「音市場の朝に」より)
A5判194頁 定価(本体1,000円+税)
柏崎市内書店で販売中
2022年5月享年65歳で亡くなった石川眞理子の遺稿集。柏崎で「JAZZ LIVEを聴く会」を設立し、日本海太鼓のメンバーとして活動、2007年の新潟県中越沖地震直後には、「かしわざき音市場」を立ち上げ定着させるなど、地方における音楽プロモーターとして八面六臂の活躍をして駆け抜けた石川の軌跡をたどる。石川眞理子遺稿集編集委員会の編集による一冊。
昨年5月、石川眞理子さんの訃報に接したのは游文舎で「LPを楽しむ会」を開こうとしているときでした。「まさか」の思いで自宅に駆け付けた時、彼女は既に死に装束で布団に横たわっていました。乳癌で放射線治療を受けていたため、着けていたカツラが妙に若々しくて、生きているようにしか見えませんでした。
同級生の猪俣哲夫さんとエトセトラの阿部由美子さん、金泉寺の小林知明さんが「石川眞理子遺稿集編集委員会」として、石川さんが残した遺稿の数々をまとめ、一冊の本に編集してくれました。玄文社主人は原稿の校閲・校正と年譜作成のお手伝いをしています。思い入れのある一冊です。
内容は「ジャズのこと」「太鼓・音楽のこと」「音市場のこと」「平和・原発のこと」「社会・友人・家族のこと」の5部に分かれていて、そんなにたくさんの文章があるわけではありませんが、彼女の多方面にわたる活躍を偲ばせます。そういえばいつでも忙しくしていた人でした。ひとの5倍くらい働いて、ひとの5倍くらいの成果を上げて、ひとの5倍くらい充実した人生を送って、消えていきました。
ジャズ論はプロのレベルに達していると思います。技術論だけでなく、音楽の奥にある感性や精神性にも迫っています。音楽好きの人はあまり本を読んだり、美術鑑賞をしたりしない人が多いようですが、彼女は違っていました。玄文社刊行の霜田文子著『地図への旅』についての書評やケーテ・コルヴィッツ論は、彼女の論理的な読解力だけでなく、優れた芸術的感性を示した素晴らしい文章です。
「平和・原発のこと」では、彼女の社会的活動の一端を窺うことが出来ます。反原発の集会で司会をつとめていたのを思い出します。その時は徹夜で準備したと言っていましたから、そういうことはよくあったようです。反戦の演劇や原爆の悲惨を訴える映画上映会でも司会をしていた彼女の姿が目に浮かんできます。そんなときも本業の仕事が終わってから、徹夜して準備をしていたのでしょう。
「社会・友人・家族のこと」で、父親のことを語っている文章がありますが、こうして親を尊敬することのできた人を羨む気持ちが私にはあります。また柏崎の「えんま市」のことを回顧して書いた文章は、通称えんま通りに生まれ育った人でなければ書けないもので、懐旧の念を掻き立てる文章になっています。
もっとたくさんの文章を書き残して欲しかったという思いがしてなりません。

このほど玄文社主人の文章が、アジア文化社の総合文芸誌「文芸思潮」85号に掲載されたので、紹介します。
この号の目玉は「文芸評論の危機」と題した特集で、中でも井口時男氏を司会役とし、若手批評家4人が発言する座談会「文芸評論の現状ー危機と打開」が面白いと思います。
ちなみにこの雑誌はアマゾンから購入できます。
では長いですが、お読みください。
批評と亡霊
小学生の時からよく本を読む少年だったが、本当に文学に目覚めたのは、中学生の時、母方の祖父の家にあった屋根裏部屋の本棚に、ドストエフスキーの『死の家の記録』を見付けて読み、さらに『罪と罰』を読んで大きな衝撃を覚えてからだった。それからは文学というものが自分の中で最も大きなテーマとなった。中学時代はものを書くということはなかったが、高校生になってからは友人と回覧雑誌を作ったりして、書くことを始めていた。高校時代には部員でもなかったのに、文芸部の雑誌に三年続けて批評文を寄稿した。気がついたら詩でもなく、小説でもなく、文芸批評のようなものを書くようになっていたわけで、それがどうしてだったのか自分でもはっきりとは分からない。
しかし、それが当時一世を風靡していたジャン=ポール・サルトルの実存主義といわれるものの影響であったことは確かだ。当時日本でも実存主義が蔓延していて、ありとあらゆるものが実存主義と関連付けられていたが、今になって思えば実存主義を謳えばどんな本でも売れたのであって、おかげでサルトル周辺の本をよく読まされたのだった。高校生でサルトルが理解できたとは思えないが、その文学作品に対するアプローチの仕方に興味があった。『存在と無』は分からなくても、『シチュアシオン』の方はそうでもなかったのだ。
小林秀雄に代表される日本の文芸批評もよく読んだ。小林秀雄だって高校生に分かるはずもないが、やはりその文学作品に対する接近の仕方が、私の体質によく合っていたのだと思う。中原中也のことを書く批評家としての大岡昇平などの著作に触れたのもこの頃のことである。しまいには、小説や詩作品そのものよりも、それを論じた批評作品の方を量的にも多く読むようになる、という転倒に陥ってしまうことにもなった。
世の中には小説も書けば批評も書くという器用な人もいるが、私にはそんなことはできない。今までに詩を一篇だけ書いたことがあるが、それ以外は批評しか書いたことがない。文学のあらゆるジャンルの中で、最も読まれることの少ないであろう文芸批評というものを、ほんの一握りの読者に向けて、五十年以上書き続けてきたのだった。他に何も出来ないのだから、そのことを後悔したこともない。今日、文芸批評の終焉ということが言われようが言われまいが、私には関係のないことだと思っている。
文芸批評については、他人の書くものをあげつらって気楽なものだと思われるかも知れないが、そんなことはまったくない。私は大学を卒業してから家業を継いで実業の世界に入ったが、批評の理念と実業の理念とが、自分の中でことごとく対立し合うという体験を日々強いられていた時期がある。文学書を読んで考えることと、実業の世界で考えなければならないこととが、いつでも背理の関係に置かれて、深刻な分裂に曝されることになるのだった。それは、批評が考えることが、直接人生に関わるものではないということに依っているのかも知れない。批評は他者の作品を通してしか人生に触れることができないのだから。
社会人になってから「北方文学」という同人雑誌に参加して書くことを続けてきたが、批評ということに関わった友人たちが、二十代から三十代そこそこで次から次に死んでいくという苛酷な体験もあった。自殺もあれば、事故死も、癌死もあったが、彼らの批評行為はぎりぎり観念的なもので、生活の課題と思想的な課題との間で葛藤を続け、生き抜くことができずに次々と斃れていったというのが真実に近い。自分もまたそうした苦闘を抱えていたので、彼らの死は私に甚大な危機をもたらした。私は死んだ友人たちの霊に取り憑かれてしまったのである。
そんな中、私はかろうじて生き延びたのだが、批評行為を続ける中で、彼らが抱えていた本質的な生きづらさに直面することを強いられた。批評というものは、「書くことは生きることだ」というような楽観主義とは無縁の表現行為である。表現行為が「作品」を通してしか文学について語り得ないということは、それが主観的であれ、客観的であれ、生きることの等価物ではあり得ないということを意味している。
私はそんな苦渋に満ちた行為を「表現論的倒錯」と呼んだこともある。あるいはそれは「倒錯」そのものであったかも知れない。私は「倒錯」の反対概念としての「健常」が、社会的または歴史的な概念にすぎないことを逆手にとって、「倒錯とは倒錯からの快癒の運動である」というテーゼを立てて開き直り、そんな苦境を乗り越えようとしたのだった。
批評は人に思想的なテーマや哲学的なテーマに向き合うことを必然化させるが、そんな中で批評主体はどんどん内省的になっていく。あらゆる表現行為の中で、批評ほど内省的、あるいは内向的な行為はないということも言える。批評は一人称でしか書かれ得ない唯一の表現行為である。客観的な論述のように見えても、その裏には「……と私は思う」とか「……と私は考える」という発言が隠されている。だから批評家が小説を書くと、どうしても私小説的な方向に傾きがちになる。〝私〟という意識が、世界で唯一無二のものであるというのが、批評の本質的な認識であるからだ。
私は特別に批評理論を学んだこともないし、特定の思想に立脚した批評を行ってきたのでもない。またさまざまな文芸批評家と呼ばれる人々の本を読んできたにしても、特定の批評家に支配的な影響を受けたこともない。ただ作品を通して自分の考えていることを発言してきただけである。しかし、私には最初からテキストクリティックという習性が染みついていたように思う。
私はロラン・バルトの『作者の死』を読んだこともないから、作品を作者の伝記的事実に還元してはいけない、というような理論を意識的に採用してきたわけでもない。ただ私には作者の残した伝記的な痕跡に興味が持てなかっただけのことだ。だから私にとっては、江藤淳のような批評家が最も苦手な存在であって、夏目漱石が嫂に懸想していたとか、肉体関係があったとかいう推測に、何の興味も湧かないし、そうした事柄が作品そのものに大きな影を落としているなどという主張に同意することがまったく出来ないのである。
私にとっては、作品にテキストとして書かれていることがすべてであって、分析の対象はそこに収斂される。その時作者というものは私の視界から消え失せるのであり、消え失せることこそが作者というものの特権でさえあると私は思う。先日「北方文学」も共催者として名を連ねた、柏崎市の游文舎での講演会で、詩人の高橋睦郎氏は「僕は詩人というものは、本来、いろんなことに対して精神的に盲目でなければならない。実際に眼を開いてものを言うのは作品であって作者ではない」と語っていた。世界に対して開かれているのは作品であって、作者ではない。それは詩であろうが、小説であろうが同じことである。
テキストはまた、過去や同時代のテキストと共鳴したり反発したりするが、そこにテキストとテキストの間の磁場が形成される。そうした磁場に分け入ることもまた批評の使命であるし、それもまた作者が要請するのではなく、作品が要請するのである。その要請に従うことは、テキストとテキストとの関係が繰り広げる、広大で豊饒な世界と向き合うことであり、それは作者の人間性などに対する探究よりも遙かに有意義なものだと私は確信している。
私はこれまで、作家論的なものを書いたことがない。特定の好きな作家は何人かいるが、その作家の生涯を辿るとか、彼の実生活と作品との関係について追求したりするということに、興味が持てないからだ。だから私の書いてきたものはほとんど作品論に偏っているのである。私の中で作者というものは、批評を書き始めた時にはすでに死んでしまっていたのかも知れない。そしてテキストに対する強いこだわりは、言語そのものに対するこだわりにつながっていく。
言語というものに直接こだわり始めたのは、ソシュールの言語学に触れてからだったと思うが、それはレヴィ=ストロースの『野生の思考』を読んだことがきっかけになっている。『野生の思考』にはソシュールの言語学が大きな影を落としているのである。物事を通事的にではなく共時的に捉えることは、ソシュールの考えに沿っていたし、それが未開民族への偏見の払拭を可能としたのである。それはまたマルクス主義的な進歩史観への根源的な批判でもあった。私はマルクス主義の影響を受けたことはないが、サルトルの実存主義はその裏に教条的なマルクス主義を隠し持っていた。レヴィ=ストロースの『野生の思考』巻末のサルトル批判は、高校生の時から囚われていたサルトルの思想から、私を決定的に解放してくれる議論であった。
社会人になってから『野生の思考』を読んだことは、私にとって最も大きな事件であった。サルトルの思想の呪縛から解放され、生活と文学の矛盾に囚われていた私は、この本によってはじめて精神的な解放感を味わうことになった。とたんに生きることがそれほど苦痛ではなくなったのも事実である。また書くことへの信頼を取り戻してくれたのも『野生の思考』だったのであり、この本によって私の周りに取り憑いていた死者たちの影も随分と薄らいできたのだった。
こうしてレヴィ=ストロースの導きによってソシュールの言語学に触れることになるのだが、ソシュール自身は著作を残しておらず、ソシュール自身のテキストというものはほとんど存在しない。だから弟子たちの残した講義録や日本における祖述者たちの本によって、基本的なソシュール言語学の概略を理解していくしかなかったが、重要なところは理解できたように思う。その後私はヴァルター・ベンヤミンの「言語一般および人間の言語について」という論考に取り組むことになり、彼がソシュールとほぼ同時に言語の本質を捉えていたことを知った。そして、この短い論文こそが私の言語観を決定的なものにしたのだった。
「われわれはどのような対象にも言語のまったき不在を表象しえない」とか、「どの言語も自己自身を伝達する」といった一節は、論理の飛躍の中に言語に対する奥深い真理を孕んでいた。私は精神現象が物質的なものの解明によって説明されるとする、自然科学者たちの一元論的な議論に対して反論すべく、ベンヤミンの言語論を中心に据えて、『言語と境界』という理論的な本を五年前に書いた。これが私の最新の著書となっている。これからもベンヤミンを通して得た言語観が、私の批評の中核をなすことだろう。

「北方文学」第85号が発刊されましたので、紹介させていただきます。発行直前に同人の坪井裕俊氏が急逝大動脈瘤解離で急逝され、昨年10月に亡くなった同じく同人の長谷川潤治氏と合わせて、追悼特集を組むことになりました。二人とも団塊の世代で、この世代はどうも長生きはできないようです。二人がまだ若かった頃の作品を再録し、略年表を作成し、追悼文を数編ずつ載せてあります。読んで二人のことを偲んでいただければ幸いです。
巻頭は詩集『魚卵』で知られる三井喬子さんの寄稿作品です。題して「海堀とはかいぼりのことである」。題名も不思議な感じですが、中身も不思議なイメージに満ちています。「うるさい!」と怒鳴る池の主たる龍の存在感が中心にあって、この龍が何を意味しているのか?、池の水を抜く「かいぼり」とは何の象徴なのか?、いろいろ考えさせる作品です。
三井さんの作品に触発されたのか、同人三人の詩が揃いました。ずいぶん久しぶりのことです。館路子「夏の未明・宙の篝火」、鈴木良一「亡き人へのオマージュ――庭仕事の人」、魚家明子「労働」と続きます。
批評の最初は霜田文子の「ポ・リン/ここにとどまれ ブルーノ・シュルツ ―揺らぐ国境の街で―」です。1892年に生まれ、1942年にナチスによって殺害されたポーランドのユダヤ人作家ブルーノ・シュルツについての論考です。ロシアによるウクライナ侵攻の暴力と、ナチス・ドイツの暴力が、時代認識として重なっています。ポーランドはウクライナとともに、ナチスとソ連によって最も歴史の悲惨を体験させられた国であり、迫害されたユダヤ人という点ではヴァルター・ベンヤミンともつながっています。マイナーな作家ですが、ちゃんと『ブルーノ・シュルツ全集』全二巻も日本で出ているのでした。
海津澄子の「遠藤周作と私――読書体験と宗教論――」が続きます。遠藤周作によってカトリック信仰へと導かれ、全作品を読んでキリスト教への思索を深めていった海津さんの、読書と思索の記録であります。カトリックの教義に縛られることなく、自分の頭で考え、神について、人について思考を深めていく姿に共感したいと思います。「本は人に知識を与え、読むことは共感のカタルシスを得させる。そしてそれだけでなく、その人が思想することを助け、その人自身の内側を作りあげていく」。全くその通りです。
榎本宗俊の「寂寥のさなかの美質」もまた宗教論です。越後堀之内生まれの歌人宮柊二を中心として、その〈生活道〉に即した歌の本質に触れています。
批評は以上3本で、柴野毅実の紀行文「ユイスマンスとシャルトル大聖堂――続・建築としてのゴシック――」へと続きますが、これも紀行というよりも批評に近いものかもしれません。コロナのパンデミックが始まる前の2019年に、シャルトル大聖堂を訪れた時の感想を、J・K・ユイスマンスの『大伽藍』に沿って展開したものです。ゴシック大聖堂の持つ美学的な矛盾を指摘し、それに無自覚であったユイスマンスへの批判となっています。しかし、ゴシック建築の持つ矛盾が、我々の内部の矛盾を惹起することも確かで、それは危うい美学的体験を強いる建築なのであります。柴野が撮影した写真23葉を掲載。
続く徳間佳信の「現代中国のアイデンティティを巡る二篇」は、現代中国の作家張梅の「?里的天空」と、李其綱の「浜北人」について論じたものです。「浜北人」については著者による翻訳も掲載されています(「?里的天空」はすでに「北方文学」80号に「この町の空」とのタイトルで紹介済みです)。二つの論文は、現代中国の変貌の中における作者の自己アイデンティティの問題を分析したものになっています。「?里的天空」においては農民工と呼ばれる層の、「浜北人」においては都市民の意識の変化が捉えられています。
鈴木良一の「新潟県戦後五十年詩史―隣人としての詩人たち」も19回目を数え、長期にわたる連載もあと1回ということになりました。鈴木のライフワークといえるこの労作もついに完結というわけです。扱う年代は1991年から1995年で、最初に「北方文学」40号から44号までの動向が紹介されています。創刊者吉岡又司の定年により編集発行人が、長谷川潤治に交替しています。同人の若返りも進み、初期同人から第2世代への交代期と位置づけることが出来るでしょう。他には「BLUE BEAT JAKET」、「桜花文芸」、「地平詩集」、「掌詩集」、「くちなし」、「新潟詩人会議」、「泉」などの詩誌の活動が紹介されています。
福原国郎の「疑惑――戊辰戦争余波――」は、福原家に伝わる古文書などの一次資料を根拠にした、福原らしい歴史研究と言えます。戊辰戦争が彼の故郷真人村に何をもたらしたかが手に取るように分かります。軍隊の食糧の現地調達という悪癖が旧日本軍に始まったことでないことも、それによって田舎の小村がいかに多大な迷惑をこうむったかということも分かるのです。〝疑惑〟というのは、その頃地元の庄屋が帳面の不正を行っているようだから調べてくれとの訴えがあったにもかかわらず、うやむやのうちに終わっていることを指しています。
坂巻裕三の永井荷風研究も長丁場になりそうです。今号は荷風の二番目の妻であった舞踊家藤蔭静枝のことを調べた「荷風夫人・藤蔭静枝のこと」です。静枝の本名は内田八重で、新潟市の芸妓の家に生まれた女性です。東京に出て新橋芸者として売り出していた頃、荷風と知り合っています。最初の妻と結婚する前から荷風と八重は関係があったようですし、父の死後すぐに最初の妻を離縁して八重を二番目の妻として迎えています。八重は女出入りの激しすぎる荷風を見限って家を出てしまいますが、離婚後も二人はときどき関係を持っていたようです。荷風という人はなんという人だったんでしょう。この論考の後半は、静枝の調査のために新潟市を訪れた坂巻の、紀行文のような感じになっています。
小説が3本。最初は魚家明子の「電車の夜」。8頁の極めて短い作品で、雪のため立ち往生した電車の中で出会った高校生の、死への恐怖を描いた掌編小説といったところでしょうか。
板坂剛の「アンダルシアの罠」は、彼としてはいつもより短い作品で、これくらいの方が焦点がはっきりしていいのではないかと思われます。酷暑のアンダルシアで気を失い、記憶をも失った男の謎。アンダルシアにいるとばかり思っていた男は再び気を失ったと思うと、なぜか六本木のギャラリーにいるという夢幻的な作品になっています。それをつなぐのは、フラメンコの男女のダンサーを描いた絵画という仕掛けです。
最後の柳沢さうびの「えいえんのひる」を紹介する前に、彼女の前作「反転銀河に擬似星座」が、文芸誌「季刊文科」88号に転載になったことを報告しておきます。まだ同人になって5年にも満たないのに、最初の作品は「文芸思潮」に転載になりましたし、恐ろしい才能です。今号の作品はいつもと打って変わってファンタジー風の味わいの小説です。前作は異常に漢字が多かったのに、今作はひらがなが多くて、タイトルまでひらがなになっています。当然前作とは文体も全く違っていて、いくつもの文体を駆使できる能力を証明しています。最後の文章だけ読んでください。「いっせいにつぼみをつけたおほりのはすが、とがらせた唇からぷうっとあまく涼しい息をはいて、次々に開いていった。もうすぐ、夏になる。」 決まってますね。
目次
【追悼・長谷川潤治】長谷川潤治*闇草紙/長谷川潤治*少年詩人・井上円了――新資料・稿本『詩冊』を読む――/長谷川潤治略年譜/追悼文・鈴木良一*同時代人としての長谷川潤治/福原国郎*あとは朧/鎌田陵人*長谷川先生と論語/柴野毅実*酒は骨で飲む!
【追悼・坪井裕俊】坪井裕俊*《異域》の精神--『大川の水』論 芥川龍之介の世界Ⅰ--/坪井裕俊略年譜/鷲尾謙治*弔辞/米山敏保*坪井さんの思い出/坂巻裕三*会いたかった同人
三井喬子*海堀とはかいぼりのことである/鈴木良一*亡き人へのオマージュ――庭仕事の人/館路子*夏の未明・宙の篝火/魚家明子*労働/霜田文子*ポ・リン/ここにとどまれ ブルーノ・シュルツ ―揺らぐ国境の街で―/海津澄子*遠藤周作と私 ――読書体験と宗教論――/榎本宗俊*寂寥のさなかの美質/柴野毅実*ユイスマンスとシャルトル大聖堂――続・建築としてのゴシック――/徳間佳信*現代中国のアイデンティティを巡る二篇/鈴木良一*新潟県戦後五十年詩史―隣人としての詩人たち〈19〉/福原国郎*疑惑―戊辰戦争余波―/坂巻裕三*荷風夫人・藤蔭静枝のこと/鈴木良一*新潟県戦後五十年詩史―隣人としての詩人たち第十章―一九九一年から一九九五年まで(前半)/魚家明子*電車の夜/板坂 剛*アンダルシアの罠/柳沢さうび*えいえんのひる

「北方文学」第84号が発刊になりましたので、紹介させていただきます。今号発行を前に新村苑子が高齢のため同人を去り、長谷川潤治が亡くなり、着実に高齢化による同人減少が続いているのに、今号はなんと400頁の超大冊となりました。これはやはり、一人一人の同人の創作意欲の高まりによるものと考えるしかないでしょう。特に今号は長めの小説を4本揃え、評論・研究の充実と相俟って、ページ数が激増したというわけです。
巻頭は館路子の詩「虹への軽いオブセッション」で、詩を書く同人が減ってきていることもあって、ここが館の指定席になりつつあります。最近、文学作品をモチーフに書くことが多くなっていた館ですが、今回は〝虹〟がモチーフです。禁忌としての虹を追い求める〝あなた〟とは何か? なにかこれまで捨て去ってきたものへの慚愧の思いさえ感じさせます。オブセッションは〝軽い〟ものでなどないようです。
次は大橋土百の俳句です。2020年から2021年までの「森の思索ノート」によるもので、さまざまな感慨が俳句にまとめられています。時事的なものもあれば、日常雑感的なもの、自然を通して人間の生き方を問うものなど、79句が収められています。
続いて批評が6編。映画批評から日本文学、短歌俳句論からゴシック論まで多彩です。最初は岡島航の「かぎりなく死に近づく」。直接的にはフランスホラー映画、パスカル・ロジェ監督の「マーターズ」についての論ですが、中国の残酷刑「凌遅刑」やバタイユ、メキシコの作家サルバドール・エリソンドの『ファラベウフ あるいは瞬間の記録』などへの言及があり、映画論というよりは、人はなぜ残酷なものに惹かれるかという問いであり、殉教というものに対する思想的な探究でもあります。
次は同じく映画論を並べてみました。鎌田陵人の「チェンソーを持つ悪魔」がそれです。まだ比較的若い人の批評を頭に持ってくることで、新しいジャンルへの批評的眼差しの可能性に賭けてみました。鎌田のはトビー・フーパー監督の「悪魔のいけにえ」について仔細に論じたものです。チャエンソーから〝鎖〟と〝鋸〟、つまりは接続と切断という両義的なテーマに展開していきます。
次は坪井裕俊の芥川論「人間の中心にある利己主義の行方です。芥川龍之介の代表作「鼻」を昨今のコロナ禍と関連させて論じたものです。「鼻」の主人公内供の最後の言葉に《逆転するアイロニー》を読み取ろうとする試みです。
次いで榎本宗俊の「民芸について」。エピグラフに吉本隆明の『最後の親鸞』から、「頂を極め、そのまま寂かに〈非知〉に向かって着地することができれば」という一節が引かれていますが、榎本の議論のすべてはこの言葉に尽きています。
次の柴野毅実の「欲望の他者への差し戻し」は、スコットランドの作家ジェイムズ・ホッグの、ゴシックロマンスの末尾を飾る作品『義とされた罪人の手記と告白』についての論考です。分身小説は古今東西いろいろありますが、この作品は分身という他者による欲望の代行を描いたものとして先駆的なものです。宗教による度を過ぎた禁止が、分身をもたらすという論旨ですが、そのことはわが国において分身小説というものがほとんど存在しないことの、原因を解明するものともなります。
霜田文子の「危機の時代の子供たちへ」は、これまであまり論じられたことのなかったベンヤミンの『子どものための文化史』について論じています。これはベンヤミンが1929年から1932年にかけて子供向けラジオ番組で語った原稿を集めたものでありながら、大災害や大事故などの大きな災厄ばかりを取り上げていることで知られています。そのことが子供とは何か?、教育と何か?という問いを誘発していきます。
研究の最初は新しい同人の坂巻裕三です。坂巻はこれから自らライフワークとする永井荷風研究を展開していく予定です。最初は「荷風」という雅号が一体何から来たのかについての論考「雅号「荷風」考」です。本人が語っている、かつて入院先で惚れ込んだ看護婦の名前「お蓮」からという通説を否定し、青年時代に父と一緒の上海旅行で訪れた、西湖十景の「曲院風荷」からきているという新説を唱えるものです。そこでは父久一郎と荷風との親密な関係が問題になってきて、坂巻は二人の関係を仔細に検討していきます。
研究の2番目は鈴木良一の「新潟県戦後50年詩史」の第18回になります。1986年から1990年までの後半を扱います。本田訓、高田一葉、五十川康平、齋藤健一、田代芙美子、常山満、館路子、樋口大介、鈴木良一らが出していた詩誌について、詳しく紹介するとともに、それらが新潟県の詩界の転換点を刻印するものであったことを示唆しています。この間に刊行された37点の詩集も紹介しています。
ここから小説4本がスタートします。ここまでで194頁ですから、半分以上を小説作品が占めていることになります。それぞれが長いので、こんなボリュームになってしまいました。黄怒波著・徳間佳信訳の「チョモランマのトゥンカル」は連載2回目で、これで本誌掲載は終了、いずれ大長編として出版される予定です。今回の内容は中国の国家資本主義の先端的部分で、多くの詐欺的行為や裏切りが横行していることを、かなり具体的に感じさせるものです。それがどう続いていくのかはまだまださっぱり分かりませんが。
続いて板坂剛の久しぶりの登場です。「河川敷の少女、あるいは愛の罪」は板坂独特の観念小説ですが、題材はフラメンコ舞踊の世界にあり、彼の生きている業界に近いところにあります。フラメンコ自体が「愛の罪」を体現したような舞踊と言えますが、ある日本人女性フラメンコダンサーがスペインで犯した愛の罪が、彼女の残した娘と彼女の兄ではないかと目されるスペイン人ダンサーとに憑依していく物語とでも言いますか。
次は魚家明子の「Colors」。人の顔を覚えられない〝相貌失認〟という病気に悩まされていた〝私〟は、ある日の集団登校時に立哨をする〝ピンクさん〟と呼ばれる人に出会うことで、漸く人の顔を認識できるようになっていきます。そんな〝私〟と〝ピンクさん〟との冒険の物語であり、少女が彼を通じて成長していく過程を描いた、ある種のユートピア小説でもあります。「世界は思ったより優しい」という、彼が去った後の少女の言葉にすべてが語られているようです。
最後は「北方文学」同人となって5作目となる、柳沢さうびの「反転銀河に擬似星座」です。1作ごとに文体を変え、モチーフを変え、刺激的な作品を発表してきた柳沢ですが、本作はこれまでで最も長く、プロットも安定し、文体も決まっていて、これが彼女の一応の完成形なのかもしれません。発達障害に苦しむ若い男女の青春小説のような見かけでありながら、奥底にはもっと深いものを感じさせます。圧倒的なスピード感を持った今までにない文体に関しては、それだけでも読者を引き付ける力を持っていると言っていいでしょう。間違いなく芥川賞にも値する傑作です。絶対必読の作品です。
目次を以下に掲げます。
詩
館 路子*虹への軽いオブセッション
俳句
大橋土百*水泡の戯れ
批評
岡島 航*かぎりなく死に近づく――瞬間の解剖
鎌田陵人*チェンソーを持つ悪魔
坪井裕俊*芥川龍之介の世界XⅡ 人間の中心にある利己主義の行方 『鼻』論 ―《逆転するアイロニー》で獲得する内供の自尊心
榎本宗俊*民芸について
柴野毅実*欲望の他者への差し戻し――ジェイムズ・ホッグの分身小説について――
霜田文子*危機の時代の子供たちへ――ヴァルター・ベンヤミン『子どものための文化史』――
書評
柴野毅実*俳句への越境的アプローチ—―田原編『百代の俳句』――
研究
坂巻裕三*雅号「荷風」考
鈴木良一*新潟県戦後五十年詩史――隣人としての詩人たち〈18〉第九章―一九八六年から一九九〇年まで(後半)
小説
黄 怒波*チョモランマのトゥンカル(二)
板坂 剛*河川敷の少女、あるいは愛の罪
魚家明子*Colors
柳沢さうび*反転銀河に擬似星座
お問い合わせはgenbun@tulip.ocn.ne.jpまで。

「北方文学」第83号が発刊になりましたので、紹介させていただきます。今号は執筆者が少なかったのですが、長編作品が多く244頁の大冊となり、同人の創作意欲が健在なことを感じさせます。
巻頭に田原さんの詩「母を悼む」を2篇掲載。田原さんは近頃母親の郭秋娥さんを亡くされたそうで、「母の葬儀」は文字通り中国式葬儀の様子を克明に描いています。日本の仏式葬儀との大きな違いを感じさせます。「赤いマホガニーの棺」とあり、重さが1トン、クレーン車で吊って墓穴に入れるというから驚きです。高級家具に使うマホガニーを棺桶に使って、使者を鄭重に弔うということですね。
館路子の長編詩「白く燃える火のオード」が続きます。先号から動物シリーズに代わって、文学作品をテーマにした連作ということになりましょう。川端康成の「雪国」と鈴木牧之の「北越雪譜」がモチーフです。雪にまつわる隠喩としての〝白く燃える火〟は、もはや文学作品の中にしか残されていない、ということへの感慨。駒子のモデルとされた女性が出てくるのが驚き。
次は魚家明子の2編「2020 Ⅶ」と「うたかた」。近頃魚家の作品は冴えわたっているが、今号のはやや重い。ただただ過ぎていく日常的な時間への疑問があって、それが詩人としての魚家を苦しめる。時間とは詩的な跳躍と背反するものでなのであろうか。
批評が4本続きます。「北方文学」の最大の特徴は批評のウエイトが高いことです。いつもよりは少ないけれど、重厚な作品が続きます。
最初は柴野毅実の「夏目漱石『明暗』とヘンリー・ジェイムズ」。3年にわたって連載してきたヘンリー・ジェイムズ論の延長上で書かれた、漱石の『明暗』についての論考です。国文学者が誰も言わない、ジェイムズの与えた漱石への影響を軸として、『金色の盃』と『明暗』との類縁性について詳細に論じるとともに、それが『明暗』に何をもたらしたかということへの考察となっています。自分ではかなり画期的な部分があると思っているのですが……。
次の霜田文子「不眠の夜、光の正午」は、多和田葉子の長編小説『飛魂』についての批評です。『飛魂』を貫いているのは、なんとニーチェの『ツァラトゥストラ』の哲学だというのです。驚くべき指摘で、読んで納得させられる部分が多くあります。『飛魂』は多和田の作品としては取り上げられることの少ないものですが、これもまた画期的な論考と言えるでしょう。
榎本宗俊に「提携へのメモ」はいつものように古今の俳句や短歌についての、浄土真宗的な読み込みによる覚書的な文章で、彼の文章でなければ出会うことのないいくつかの作品との出会いが貴重な体験をたらしてくれます。
次いで坂巻裕三さんの「故路奈文Ⅷ 初読・フォークナー」。初登場の坂巻さんは、永井荷風の研究家でもあるのですが、英語に堪能(翻訳で読むより英語で読んだ方がよく分かる、というくらい)で、アメリカ通の人です。コロナ禍での蟄居生活の中で読み直したり、初めて読んだりした本についての〝読書エッセイ〟ですが、なかなか軽いものではなく、文明論的な視点がきちんと入ったフォークナー論になっています。
研究としては今号は鈴木良一の「新潟県戦後50年詩史」のみ。「隣人としての詩人たち」の17回目にあたり、1986年から1990年までの前半を扱います。最初に「北方文学」の動静が取り上げられますが、ここで登場するのが柴野。同誌の詩人たちへの批評と、それが果たした役割について書かれています。38号の来迎寺出身詩人・山口哲夫に対する追悼特集や第40号の現代詩特集のことなどが紹介されています。三条の経田佑介の「ブルージャケット」の動き、「新潟詩人会議」と「創玄」の創刊など、重要な事項が記録されています。
書評が一本。「北方文学」同人・鈴木良一の新詩集『ひとりひとりの街』についての、魚家明子の書評です。題して「詩を生きて、種を撒く人」。
最後に小説が3本続きます。最初は柳沢さうびの「とらのゆめのを」。プロレスラーの男の彼女との行き違いや、先輩花形レスラーの彼女との関係に対する疑いや嫉妬が描かれているのですが、こんな卑俗なテーマが柳沢の文体に乗ると、どこまでも文学的な香気を感じさせるから不思議です。夢とも妄想ともつかぬ描写は、とても素人とは思えぬハイレベルな文体に支えられています。短い作品ですが、こんな文体で長篇を書いたら、彼女はすごい作家になれると思うのですが。
大ベテランの新村苑子の「昭夫の決断」が続きます。癌に冒された妻を気遣う夫の気持ちが、優しく書かれていきます。突然、妻入院先の病院のベッドで不可解な死をとげてしまいます。なんという不条理な。
最後は中国の作家・黄怒波の大長編「チョモランマのトゥンカル」の第1回目です。トゥンカルというのは「チベット仏教の祭祀用に吹き鳴らす法螺貝」のことだそうです。1節から7節まで続くチョモランマ頂上付近での登山隊の悪天候との戦いは、臨場感溢れる描写が続きど迫力です。8節からある開発区の完成祝賀式典の場面に変わりますが、チョモランマ登山とどう関係するのかは今のところ分かりません。なんせ全体のまだ10分の1くらいなので。翻訳は徳間佳信。
目次を以下に掲げます。
田 原*母を悼む(二編)悲しみ・母の葬儀
館 路子*白く燃える火のオード
魚家明子*2020 Ⅶ・うたかた
柴野毅実*夏目漱石『明暗』とヘンリー・ジエイムズ
霜田文子*不眠の夜、光の正午――多和田葉子『飛魂』を読む――
榎本宗俊*定型へのメモ
坂巻裕三*故路奈文Ⅷ 初読・フォークナー
鈴木良一*新潟県戦後五十年詩史――隣人としての詩人たち〈17〉第九章―一九八六年から一九九〇年まで(前半)
魚家明子*詩を生きて、種を撒く人――鈴木良一詩集『ひとりひとりの街』――
柳沢さうび*とらのゆめのを
新村苑子*明夫の決断
黄 怒波*チョモランマのトゥンカル
お問い合わせはgenbun@tulip.ocn.ne.jpまで。
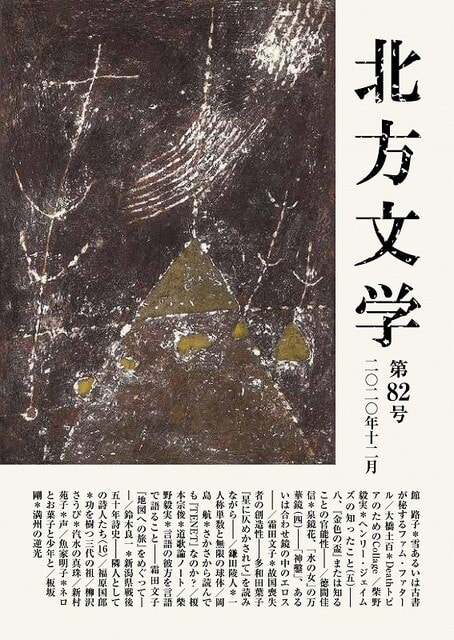
「北方文学」第82号が発刊になりましたので、紹介させていただきます。80号、81号と同人の死が相次ぎ、追悼特集を余儀なくされましたが、今号は幸い追悼の必要はありませんでした。それにも拘わらず264頁の大冊となり同人の旺盛な創作意欲を感じさせます。
巻頭に館路子のいつもの長詩。このところ動物をモチーフとした作品を書き続けてきましたが、今号の「雪あるいは古書が秘するファム・ファタール」では動物は登場せず、谷崎潤一郎の「細雪」と「春琴抄」がモチーフとなっています。しかも大正生まれの母親が残した昭和24年の粗悪な紙質のそれらの本は、母の記憶をも呼び起こします。なにか書評を思わせるような一編です。
詩がもう一編。大橋土百の「DeathトピアのためのCollage」。いつもの俳句ではなく現代詩で、大橋独特の土着的精神は感じられず、意外な面を見せています。本人によれば、若い時に西脇順三郎の作品を読んで大きな影響を受けたのだそうで、それを知れば意外でもないのかもしれません。ちょっと古い感じの現代詩的な言葉使いが全編を覆っています。
批評が6本続きます。それぞれテーマはバラバラですが、批評の比重が高いのが「北方文学」の最大の特徴ですから、本来の姿と言えるでしょう。文学論がほとんどですが、映画論も一本あり、対象は何であれ批評精神の発動こそ大事にしなければならないものと思っています。
最初は柴野毅実の連載「ヘンリー・ジェイムズの知ったこと」の5回目で完結編。『金色の盃』を取り上げます。これまで論じてきたセクシュアリティということの論理的な展開のために、ミシェル・フーコーの『性の歴史Ⅰ 知への意志』とスティーヴン・マーカスの『もう一つのヴィクトリア時代』を参照して、議論を進めていきます。作品に即しながらヘンリー・ジェイムズにおけるセクシュアリティと知との関係に迫ります。これまでの総集編ということで長い論考となっています。
次は徳間佳信の「泉鏡花、「水の女」の万華鏡」の4回目。今回は「神鑿」を取り上げます。いつも鏡花のマイナーな作品ばかりが出てきますが、メジャーな作品にも共通するエロティシズムの論理の追究が行われています。今回は人形というものに対するフェティシズムがその対象となっています。
次に掲載された霜田文子の「故国喪失者の創造性」は、多和田葉子の『星に仄めかされて』についての批評です。越境の文学ということが言われますが、霜田はベンヤミンの翻訳論を借りて、言語と言語を媒介するものとしての純粋言語について語ります。それこそが故国喪失者の創造性を生み出すのだという議論です。
鎌田陵人の「一人称単数と無限の球体」は村上春樹の最新短編集『一人称単数』についてのいささか意地の悪い批評になっています。鎌田は一人称単数ということについて、シュレーディンガーの「意識の単数性」という疑念を持ち出して嗾けていますが、勝負は言うまでもないでしょう。村上の思わせぶりな円についてのなぞなぞについても、パスカルの『パンセ』に出てくる無限球体の概念を対峙させていますが、こちらも同様。
岡島航は前号に引き続いて映画論。2020年のアメリカ映画で最も話題となったクリストファアアー・ノーランの「TENET」における、時間の逆行についての議論を展開しています。逆行にあっても主観時間は常に巡航しているというパラドックスを解く鍵はしかし、ノーランの映画それ自体の中にはないのかも知れません。
批評の最後は榎本宗俊の「道歌論ノート」。いつものように仏教論であり、結論は「南無阿弥陀仏」ということになるのですが、これもまた自らの精神史に即しての批評なのであります。
書評が一本。11月に玄文社から刊行された、霜田文子の『地図への旅』についての書評です。題して「言語の彼方を言語で語ること」。言語ならざる世界を言語で語る美術批評の宿命的なあり方のみならず、この本の中核をなすアール・ブリュット的な絵画に対する著者の対峙の仕方についての本質的な議論を展開しています。
以上批評、以下は研究ということになります。鈴木良一の大連載「新潟県戦後五十年詩史」の今回は1981年から1985年の後半を取り上げています。1980年から1986年まで新潟市に居住した福田万里子が、新潟県の詩の世界に果たした役割について書かれた部分が今回の中心でしょうか。
福原国郎の「功を樹つ三代の祖」は小千谷市旧真人村の庄屋であった先祖の功績を、福原家に伝わる古文書等を読み解いて実証的に検証する試みです。先号のテーマであった長岡高校の歴史から、彼本来のテーマに戻っての、いつもながら見事な研究です。
最後に小説が4本続きます。小説が4本並ぶというのも久しぶりのことではないでしょうか。最初は柳沢さうびの「汽水の真珠」。ある女性に寄生する何ものかの語りとして小説は進行していきます。それがいったい何なのかという謎は最後まで明かされません。ただし「汽水に生息するくじゃく貝」の作り出す虹色の真珠が、何ものかの象徴として機能しているとすれば、真珠の元となる異物こそがその正体かも知れません。つまり女性の肉体と精神に関わる異物、つまりは自己同一性を阻害する何か。濃厚な小説です。いつもながら見事なタイトル。
大ベテランの新村苑子の「声」が続きます。強姦され祝福されざる子供を産み、その子を失った女性と、ベトナム戦争から日本に逃れてきた、祝福されざる存在としてのあるベトナム人神父との出会いを描く。設定がいいですね。宗教小説として読むこともできます。
一番の若手である魚家あき子の「ネロとお菓子と少年と」は、彼女独特のファンタジーの世界になっています。口からお菓子が出てくる女性と、不思議な少年と犬との出会いをファンタジックに描いています。会社の同僚との関係の中で口からお菓子が出なくなり、少年も犬も消えていなくなってしまいます。
最後は板坂剛久々の作品「満州の逆光」です。「満州国再興計画」なるものをめぐっての謎に満ちた探索行。歴史幻想小説と言っていいかも。通俗的なプロットかも知れませんが、最後まで飽きさせずに読者を引っ張っていきます。2号前の「幕末の月光」に似た手法ですね。
目次を以下に掲げます。
館 路子*雪あるいは古書が秘するファム・ファタール
大橋土百*DeathトピアのためのCollage
柴野毅実*ヘンリー・ジェイムズの知ったこと(五)――八、『金色の盃』または知ることの官能性――
徳間佳信*泉鏡花、「水の女」の万華鏡(四)――「神鑿」、あるいは合わせ鏡の中のエロス――
霜田文子*故国喪失者の創造性――多和田葉子『星に仄めかされて』を読みながら――
鎌田陵人*一人称単数と無限の球体
岡島 航*さかさから読んでも『TENET』なのか?
榎本宗俊*道歌論ノート
柴野毅実*言語の彼方を言語で語ること――霜田文子『地図への旅』をめぐって――
鈴木良一*新潟県戦後五十年詩史――隣人としての詩人たち〈16〉
福原国郎*功を樹つ三代の祖
柳沢さうび*汽水の真珠
新村苑子*声
魚家明子*ネロとお菓子と少年と
板坂 剛*満州の逆光
お問い合わせはgenbun@tulip.ocn.ne.jpまで。

霜田文子氏の『地図への旅―ギャラリーと図書室の一隅でー』を刊行しました。
『未完の平成文学史』の著者である、元日本経済新聞文化部編集委員、浦田憲治氏のまえがき掲載。
帯文を紹介します。
文学と美術が奏でる美しい旋律
読んで感じるのは、美術評論家や文芸評論家の本とずいぶん肌合いが異なっていることだろう。あたかも岸田劉生や小出楢重らの画家が書いた評論やエッセーを読むかのような、心地よい官能性がある。霜田さんのもつ明晰な頭脳、豊富な読書体験、旺盛な知的好奇心に加えて、美術作家としての柔らかで鋭敏な感受性を感じとれる。文学と美術が見事に共鳴し、美しい旋律を奏でている。本書は、文学や美術などの芸術が「知性や感性の冒険と遊び」であることを教えてくれる。
元日本経済新聞文化部編集委員 浦田憲治 (まえがきより)
取り上げられた作家たち
川田喜久治、フランソワ・ビュルラン、古賀春江、ドナルド・キーン、川端康成、ホルヘ・ルイス・ボルヘス、チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ、残雪、フリオ・コルタサル、フアン・ルルフォ、チアヌ・アチェベ、ガッサーン・カナファーニー、目取真俊、ギュンター・グラス、 ロベルト・ボラーニョ、ブルーノ・シュルツ、アゴタ・クリストフ、多和田葉子、舛次崇、岡上淑子、関根哲男、エマ・マリグ、ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ、鴻池朋子、小沢剛、季村江里香、舟見倹二、アンティエ・グメルス、上原木呂、コイズミアヤ、北條佐江子、猪爪彦一、信田俊郎、谷英志、伊藤剰、加谷径華、たかはし藤水、玉川勝之、赤穂恵美子、佐藤美紀、本間惠子、茅原登喜子、カルベアキシロ、アントニ・ガウディ、ゲルハルト・リヒター、カスパー・ダーヴィット・フリードリヒ、ヨゼフ・スデク、ムヒカ・ライネス、Tommaso Protti、Ursula Schultz-Dornburg、ギュスターヴ・モロー、アルベルト・ジャコメッティ、レオナルド・ダ・ヴィンチ
四六判390頁、上製本、定価(本体価格3,000円+税)
お問合せ・ご注文は玄文社まで email/genbun@tulip.ocn.ne.jp
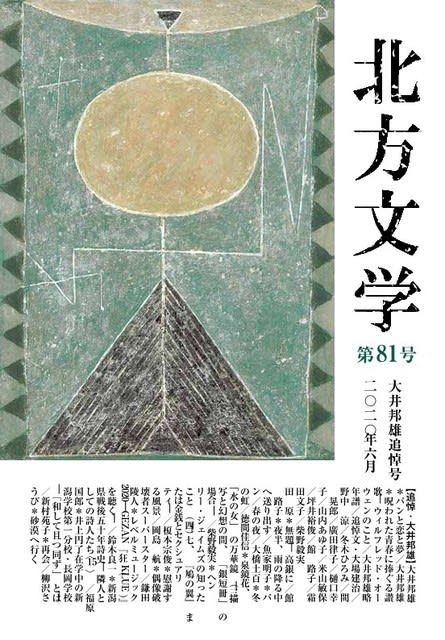
「北方文学」第81号が発刊になりましたので、紹介させていただきます。80号に引き続いて今号も追悼特集を組むことになってしまいました。最後の創刊同人であった大井邦雄氏が今年1月に亡くなってしまったからです。大井氏は早稲田大学名誉教授であり、定年後もシェイクスピア研究をライフワークとして続け、2014年にはハーリー・グランヴィル=バーカーの訳述で日本翻訳文化賞特別賞を受賞しています。シェイクスピア研究の泰斗、大場建治氏はじめ、多くの同僚の方や弟子の方々から追悼文をいただきました。同人の追悼文も5本掲載しました。かなり詳細な略年譜も作成しました。
大井氏本人の作品も2編掲載しています。「北方文学」第2号掲載の詩「パンと恋と夢」と、第59号掲載のウィルフレッド・オーウェン論です。シェイクスピア研究に一生を捧げた大井氏の原点にあったのは詩であったのでした。
巻頭に中国人で日本語で書く詩人、田原氏より久しぶりに寄稿をいただきました。韓国の高名な詩人、高銀に捧げられた無題の作品は、詩の言葉が漢江の流れとともにどこまでも到達していく、普遍性への信頼を語っています。
続いて館路子の長詩。災厄詩人として知られる彼女ですが、このところ動物をモチーフとした作品を書き続けてきました。今号の「夜半、雨の降る中へ送り出す」ではその動物がこれと特定されていません。何か得体の知れぬ気味悪いものであるところを見ると、新型コロナウイルスのことなのかもしれません。
魚家明子の詩が2編続きます。「パン」と「春の夜」です。軽めに書かれていますが、夢が肉体を通して喚起するイメージが鮮烈に綴られていきます。天性の詩人ですね。
批評が5本続きます。これこそ「北方文学」の「北方文学」らしいところで、それぞれテーマはバラバラですが、批評精神は共通しています。今号は若手の映画論とロック論もあり、
サブカルチャーを本格的に論じることのできる人材を大事にしたいと思っています。
最初は徳間佳信の「泉鏡花、「水の女」の万華鏡」の三回目、「銀短冊」についての論考です。「銀短冊」の前に、先々号の「沼夫人」への中国伝統劇の台本『雷峰塔伝奇』の影響について論じています。中国文学を専門にする徳間らしい指摘です。あまりこれまで論じられていない「銀短冊」についての分析で、徳間は鏡花の語りが幻想へと向かっていく構造を一般化している。語りの中で事実と暗喩との境界が定かでなくなっていき、そこに生々しいイメージを持った幻想が生まれてくるという指摘です。
次は柴野毅実の連載「ヘンリー・ジェイムズの知ったこと」の4回目。『鳩の翼』を取り上げます。今回はあくまでも作品に寄り添い、作品分析を通してジェイムズの作品に迫ります。ジェイムズがしばしばテーマとした金銭と恋愛が、この作品において最も突出した到達点を示しているというのが柴野の考えです。バルザックの『ウジェニー・グランデ』との比較も行っています。
榎本宗俊の「慰謝する風景」へと進みます。基本的な枠組みは短歌論ですが、いつものように仏教論でもあり、反近代論でもあります。いつも断片的な議論を展開する榎本ですが、今回はかなりまとまりがあります。
次の岡嶋航「偶像破壊者スーパースター」はホラー映画の新鋭、アリ・アスター監督の「ヘレデタリー/継承」と「ミッドサマー」について論いています。ホラー映画における顔の破壊がテーマになっています。よく観ていますね。
鎌田陵人の批評もサブカルチャーに関わるもので、日本のオルタナティヴロック、GEZANを論じています。ロックの原点がrebel(反抗)にあるという指摘は正しいと思いますが、鎌田の好きなのはパンク系なので、あまり一般受けするようなものではありません。
以上批評、以下は研究ということになります。鈴木良一の大連載「新潟県戦後50年詩史」も始まってから10年近くたつでしょうか。今回は1981年から1985年を取り上げていて、「北方文学」のウエイトが大きくなっています。懐かしい名前がたくさん出てきます。ちなみに私はそのころまだ30代の若手でありました。
福原国郎の井上円了についての論考は、現在彼が進めている県立長岡高校150年史編集のための資料読みから出てきたテーマに拠っています。東洋大学創立者の井上円了は現長岡市出身で、長岡高校の新潟学校第一分校・長岡学校時代の在籍者で、生徒会「和同会」の創設者でもありました。
最後に小説が2本続きます。大ベテランの新村苑子の「再会」は、冤罪で20年の懲役後、冤罪のもととなった事件に責任のある元夫と苦い再会をする女の心情を描きます。こういう重いテーマで書かせたら、いい味を出します。
まだ同人歴の浅い柳沢さうびの「砂漠へ行く」は、前2作に引き続いて新人とは思えない安定感を持った作品です。前2作のような幻想的な要素はありませんが、不可解で割り切れない読後の印象は共通しているかもしれません。それにしてもいいタイトルだなあ。
目次を以下に掲げます。
【追悼・大井邦雄】
大井邦雄*パンと恋と夢
大井邦雄*呪われた青春に捧ぐる讃歌――ウィルフレッド・オーウェンのこと
大井邦雄略年譜
追悼文・大場建治/野中 涼/冬木ひろみ/間 晃郎/廣田律子/樋口幸子/山内あゆ子/米山敏保/坪井裕俊/館 路子/霜田文子/柴野毅実
田 原*無題――高銀に
館 路子*夜半、雨の降る中へ送り出す
魚家明子*パン/春の夜
大橋土百*冬の虹
徳間佳信*泉鏡花、「水の女」の万華鏡(三)――描写と幻想の間、「銀短冊」の場合
柴野毅実*ヘンリー・ジェイムズの知ったこと(四)――七、『鳩の翼』または金銭とセクシュアリティ――
榎本宗俊*慰謝する風景
岡島 航*偶像破壊者スーパースター
鎌田陵人*レベルミュージック2020 ――GEZAN『狂(KLUE)』を聴く――
鈴木良一*新潟県戦後五十年詩史――隣人としての詩人たち〈15〉
福原国郎*井上円了在学中の新潟学校第一分校・長岡学校――「和して且つ同ず」とは
新村苑子*再会
柳沢さうび*砂漠へ行く
お問い合わせはgenbun@tulip.ocn.ne.jpまで。