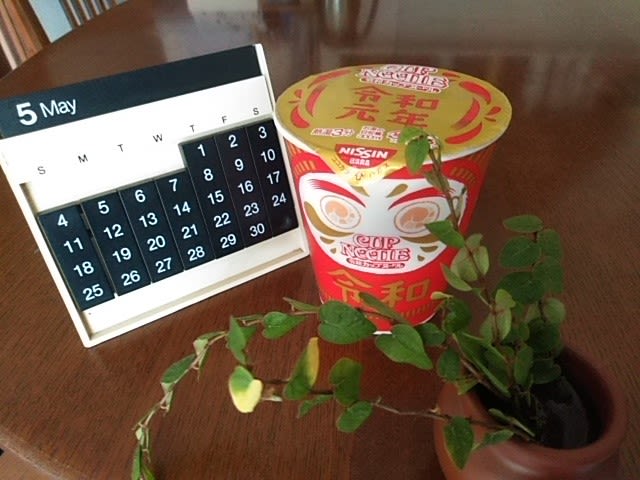朝から雨の木曜日、中庭の木々のみどりが濃くなって鮮やかに濡れている。二本の欅の大木が枝を広げて雨空にのびて、ベランダの先にある一本のゆずり葉にも雨粒が落ちている。
今年になって入れ替わった葉々の重なり、みどりの色変化が鮮やかだ。葉の表面の雨粒は弾かれて集まり、しずくとなって下の方の枝の葉へと伝わっていき、軽くなった上方の葉は反動で小さく揺らぎ、落ちたしずくのほうはやがて地中へと染み込んでいく。いつもその繰り返しの中で、五月の雨は降り続けている。
小満がすぎて大方の田んぼには、もう稲の苗が植え終えられたことだろう。JR横浜線から見える恩田川あたりに広がる田園風景を見たのはつい最近のこと、水が張られた田んぼの苗はまだ植えられたばかりで風が吹くと産毛のようにそよいでいた。
こどもの国線で「こどもの国」を訪れるのは、昨年八月以来だ。長津田をスタートしてわずか二駅、終点のこどもの国駅から徒歩ですぐ、歩道橋を渡ってゲートをくぐると百ヘクタールの里山風景を遺して切り開かれた広大な丘陵が広がる。平日の午前中とあって訪れる人は少なく、新型コロナウイルス感染下だからなおさらのこと静寂な雰囲気がする。戦時中に陸軍弾薬庫があった当時、貨物引き込み線が正面入り口から園内まで敷かれていたという。
その跡地が、現上皇上皇后両陛下のご成婚に際し、おふたりのご意向に沿う形で、国民からよせられたお祝い金をもとに、こどものための福利厚生施設として計画がされた。開場したのは東京オリンピック後の1965年五月こどもの日、広大な敷地は東京都と神奈川県境にまたがって広がっている。
中央広場両側はすでに葉桜の季節、左手前方には皇太子記念館の赤い大屋根がのぞいている。その下の室内ホールはきれいに解体されてしまったが、屋外の集会施設として利用できそうだ。せめてステージになりそうな舞台くらいは残していてくれればよかったのに残念。そしてすぐ先の屋外プールは、今夏も閉じられたままのようだ。
周遊道路からひと山越えて(意識しなければ気がつかないのだけれど)横浜市郊外と東京町田市の境を跨ぎ、白鳥湖のほうまで行ってみることにした。いい陽気にすこし汗ばむくらい、そこは森に囲まれた湖といった風景になる。足漕ぎのボート乗り場がある風景は以前とあまり変わっていないように思えた。湖畔のベンチには仲良しの父親と娘らしき一組の親子がいるだけだ。その少し離れた脇でメタセコイヤの大木が木陰を作っている。
このあたりで一足早い昼食をとることにして、自動販売機でお茶のペットボトルを購入した。持参のお弁当を広げたらまるでピクニック気分か。座った視線の湖のずっと先には、その名の通りつがいの白鳥がのんびりと泳いでいる。ほんのすこし奥まっただけなのにまるで別世界が広がる。
食べ終わってから湖にかかる太鼓橋を渡り、白鳥のいる先までいってみることにした。湖の奥のほうへ進むにつれて、周辺にはイロハモミジがたくさん植わっていて、いまは青紅葉のトンネル、秋になると見事な紅葉だろう。利用したことはないがバーベキューとキャンプ場はこの奥になるらしい。
白鳥湖から離れて人口せせらぎのある方向に戻り、県境のトンネルを超えてゆく。道の両側にはかつての軍需施設遺跡として弾薬庫だった洞窟倉庫の入り口がいくつか残されている。
そうこうして進んでいくと大きく視界が開けてきて、丘陵一帯に白い木さくで囲われた牧場地が現れた。ここがポニーと乳牛と羊と小動物のいる雪印こどもの国牧場だ。乳業メーカーである雪印直営の牧場はここだけかもしれない。前にきたのは娘が小さかったころだから、以来二十年ぶりくらいだろうか。
さきのバーベキューにキャンプ場といい、ここが都心から30キロしか離れていない周辺を住宅地と学校に囲まれた空間だとはにわかに信じがたい気がしてくる。尾根の向こうは、日本体育大学と横浜美術大学、そして横浜市立奈良中学校があるのだから。
まあ、せっかくだから名物の地産牛乳を使用したソフトクリームをいただくとしよう。牧地の一部を開放した芝生地の一角にミルクプラントがあって、そこで生乳を加工している。乳脂肪たっぷりのまさに作りたてソフトミルクでバニラビーンズの香りさえしない。丘のむこうにはこどもたちの姿が見えて、歓声が上がっているのどかな風景。昨今のコロナ禍を忘れそうな文字通り“牧歌的”なひと時に浸る。
もうひとつあるトンネルを過ぎると右手に多目的広場、かつての陸軍田奈部隊本部があった場所だ。当時からの歴史を知るであろう、大きなヒマラヤ杉がそびえている。もうすこし進めば正面広場にもどって、東京都と横浜市の境を行ったり来たりしながら、これでほぼ園内の主要個所をひとめぐりしたことになる。
ひたすら広大な郊外の里山空間、これといったモニュメント性のなさがいいのかもしれない。いざとなれば、非常時の大規模避難場所としても活かされるだろう貴重な中立的空間。まったく仰々しさがなく、消費生活からも遠く、ひたすら家族的で健康的である。貧富の差なく平等志向のもと軍事遺産を平和的に転換してみせた空間は、戦後の日本が国民統合の象徴としての天皇制度を抱き、希求してきた理想を表しているのかもしれない、と終戦76年後の夏を迎える前にぼんやり思う。
そしてもうひとつ、すこし汗ばみ青空を見上げながら考える。二回目の東京オリンピックに関して優先すべきことは、はたしてそこにあるのだろうかという疑問だ。誰のための何のためのオリンピックなのだろう。

園内中央広場から正面入り口、長津田方面を眺める。
かつての軍需貨物引き込み線ホーム、弾薬工場跡(撮影:2021.5.25)

うすピンク色に焼けたヤマボウシ山法師(野性種)
















 箱根芦ノ湖畔から望む雨上がりの富士(撮影:龍宮殿別館 2020/09/22)
箱根芦ノ湖畔から望む雨上がりの富士(撮影:龍宮殿別館 2020/09/22)


 児童遊園地跡「オクテトラ」 造形デザイン:イサム・ノグチ(1965年)
児童遊園地跡「オクテトラ」 造形デザイン:イサム・ノグチ(1965年)