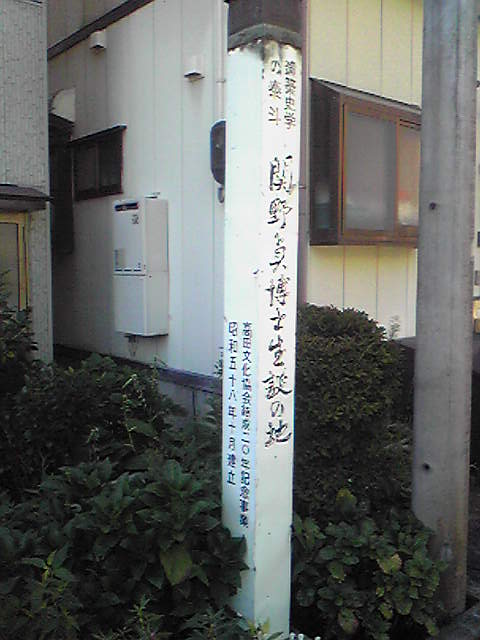あさ六時に目が覚める。
休日の週末土曜日、先週に引き続いて台風が接近している。それも27、28号とダブル台風の影響で昨夜からずうと雨降りだ。窓の外では、雨の粒がマンション敷地のコンクリート面にできた水たまりに落ちて波紋の飛沫をあげているのが見える。窓ガラスについた水滴がいく粒か集まってひとすじの流れ模様となって落ちていく。まるで偶然から定められた出会いのように。まだ、雨は降りしきっていて、お昼頃まで止む様子はなさそう。
そうだね、何を聴こうか。
まだ身体が目覚めきっていないから、北欧を思わせるような静ひつな音楽がいい。
まず、ヨーロピアン・ジャズ・トリオの1989年デビュー作から「ノルウェイの森」と「マイ・ロマンス」を連続して。若手ピアノトリオのシンプルなメロディーと端正なリズムがやさしく響く。「ノルウェイ・・・」は、ビートルズよりもこの演奏で体験したときの印象が強い。
「マイ・ロマンス」ときたら、やはりビル・エヴァンストリオの「ワルツ・フォー・デビイ」のなかの同曲を聴き比べてみたくなる。テイク1、2と続くニューヨークの老舗ビレッジ・ヴァンガードにおける1961年6月25日ライブ録音。アルバムのカヴァーデザインとブックレットフォトがこのアルバムの前奏曲となっていて、雰囲気をよく伝えている。演奏はリリカルというより禁欲的でいくぶんくぐもったピアノフォルテの音、寄り添うようなスコット・ラファロのベース、52年前の店内のざわめき、グラスの触れ合う音と拍手が入っているのが、当時のライブハウスの雰囲気を伝えている。こちらの演奏はエヴァンストリオならではの親密なインタープレイがいいな。静かな「マイ・フィーリッシュ・ハート」からはじまって、タイトル曲と聴きこむほど味がでてくる演奏。締めくくりは「マイルストーンズ」、マイルスはいまだに正面から向き合っていないのだけれど、この曲は親しみやすくて元気にさせてくれる。
ようやく、身体のほうも空腹を覚えてきたので、このあたりで朝食としようか。
休日の週末土曜日、先週に引き続いて台風が接近している。それも27、28号とダブル台風の影響で昨夜からずうと雨降りだ。窓の外では、雨の粒がマンション敷地のコンクリート面にできた水たまりに落ちて波紋の飛沫をあげているのが見える。窓ガラスについた水滴がいく粒か集まってひとすじの流れ模様となって落ちていく。まるで偶然から定められた出会いのように。まだ、雨は降りしきっていて、お昼頃まで止む様子はなさそう。
そうだね、何を聴こうか。
まだ身体が目覚めきっていないから、北欧を思わせるような静ひつな音楽がいい。
まず、ヨーロピアン・ジャズ・トリオの1989年デビュー作から「ノルウェイの森」と「マイ・ロマンス」を連続して。若手ピアノトリオのシンプルなメロディーと端正なリズムがやさしく響く。「ノルウェイ・・・」は、ビートルズよりもこの演奏で体験したときの印象が強い。
「マイ・ロマンス」ときたら、やはりビル・エヴァンストリオの「ワルツ・フォー・デビイ」のなかの同曲を聴き比べてみたくなる。テイク1、2と続くニューヨークの老舗ビレッジ・ヴァンガードにおける1961年6月25日ライブ録音。アルバムのカヴァーデザインとブックレットフォトがこのアルバムの前奏曲となっていて、雰囲気をよく伝えている。演奏はリリカルというより禁欲的でいくぶんくぐもったピアノフォルテの音、寄り添うようなスコット・ラファロのベース、52年前の店内のざわめき、グラスの触れ合う音と拍手が入っているのが、当時のライブハウスの雰囲気を伝えている。こちらの演奏はエヴァンストリオならではの親密なインタープレイがいいな。静かな「マイ・フィーリッシュ・ハート」からはじまって、タイトル曲と聴きこむほど味がでてくる演奏。締めくくりは「マイルストーンズ」、マイルスはいまだに正面から向き合っていないのだけれど、この曲は親しみやすくて元気にさせてくれる。
ようやく、身体のほうも空腹を覚えてきたので、このあたりで朝食としようか。