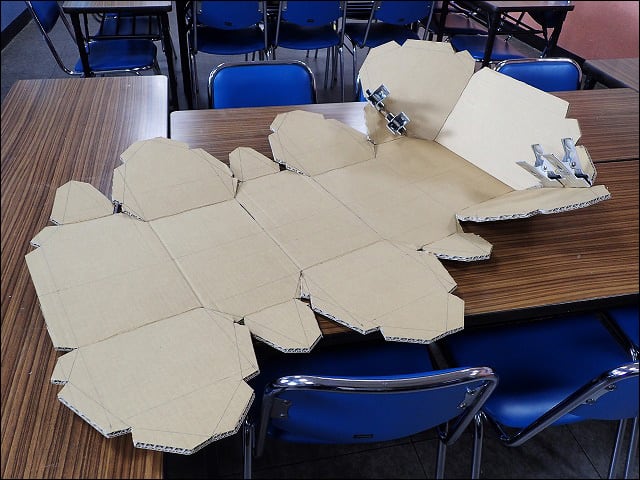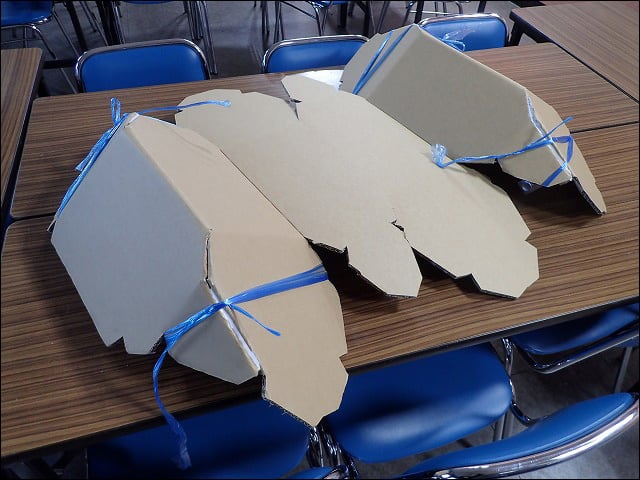この日は晴れ。澄み切った青空のもと,ガガイモの綿毛がほわーっと開いて,今にも旅立ちそう。風もそこそこあって,旅立ちの日としてはなかなかのもの。

風は,下写真では右から左方向へ吹いています。風の吹くままにゆらゆら揺れます。

こちらは,袋菓が割れて,閉じた綿毛が行儀よく並んでいます。間もなく落下傘たちが勢いよく開くでしょう。

日が傾いてから,もう一度行ってみました。風がほとんどなく,綿毛は下に垂れていました。

種子が錘になって,落下傘がぶら下がっているといった感じ。

おやおや,種子の一つが近くのアメリカセンダングサの種子に捕まっています。あてのない旅ですが,まさかこんなところで簡単に捕まろうとは。種子はもっともっと遠くに旅立とうとしたにちがいありません。

種子の数だけ,物語が生まれて展開していきます。観察をとおして種子の散布作戦のおもしろさが見えてきます。自然の妙が伝わってきます。