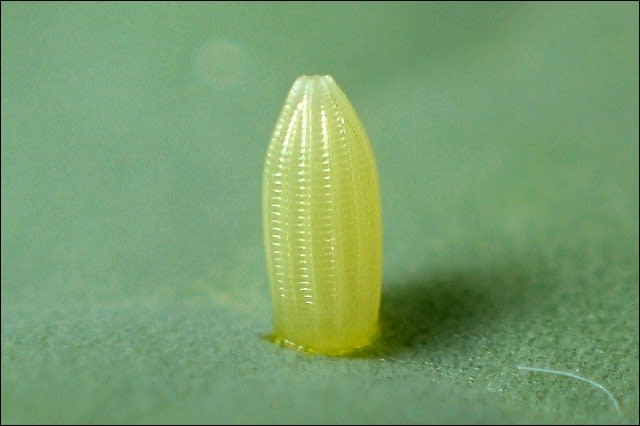自宅庭の一画に砂利を敷き詰めたところがあります。そこを歩いていると,コメツキムシが歩きながら旋回しているのが目に留まりました。ほぼ同じコースを,それも大急ぎでなにやら困ったことでも起こっていそうな様子で動いているのでした。
確めようと思って近づいてみると,周りにはアリがいっぱい。コメツキムシはアカアシオオコメツキでしょうか。アリたちはコメツキムシの動きに応じて,それを追いかけるように集団移動していくのです。

「おやっ? これは集団で襲っているのかなあ?」。そう思いながら,しばらく観察。

砂利の間に入って身動きの取れなくなった瞬間,アリはコメツキムシのからだに取り付きました。顎を突き立てているものもありました。確かに襲っているのです。

かろうじてそこから脱すると,コメツキムシは前と同じように旋回。どうしてもっと遠くに移動しないのかふしぎでしかたありません。ときには,例によってペチーンと跳ぶこともありますが,それもせいぜい10cm程度。するとまた,アリたちが追いつきます。
そうこうしているうちに,コメツキムシは植木鉢の下の隙間に入ってしまいました。偶然のこととはいえ,たぶんそうなると身動きがとれなくなるはずです。
30分ほどしてから,鉢を動かして見てみました。コメツキムシはすっかり参ってじっとしたまま。アリはそれを楽々と襲っていました。コメツキムシはもうダメなのでしょうか。わたしには,相当なダメージを受けているとしか思えませんでした。

ところが,またペチーンと10cm跳んだのです。死力を絞って,といったふうです。しかし,石の窪みに入ったまま動きませんでした。当然のことながらアリは次々に襲いました。とうとういのちが絶えたにちがいありません。

これも自然の掟です。なるがままです。感傷を差しはさむ余地はありません。生きとし生けるものの宿命です。アリの攻撃性をまざまざと見せつけられた思いがします。硬い殻で身を包んだコメツキムシが,跳んで逃げようともがいても徒労に終わりました。わたしには驚異の出来事でした。