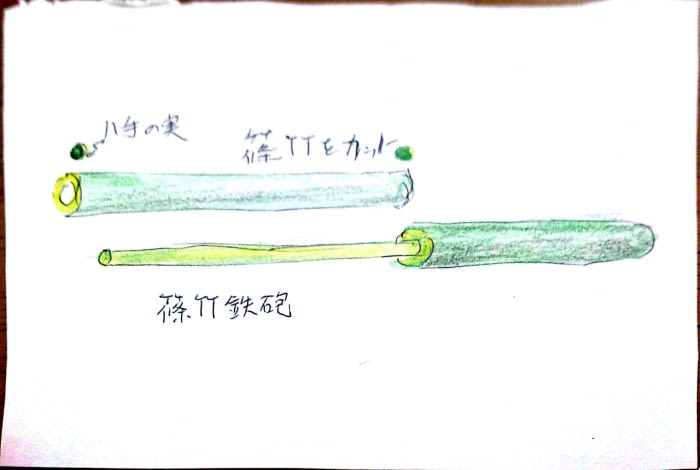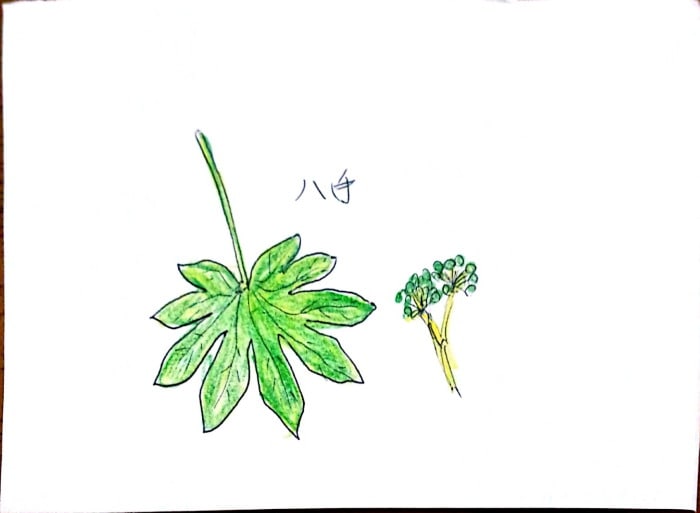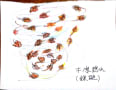2012年12月16日 快晴
昨日の雨が上がって穏やかに晴れ上がりました。若しかしたら、気温も20℃位まで上がったかもしれません。今日は近所のイベントがあり、可也着込んでいったら暑くて、途中で抜け出して、軽装に着替える始末でした。イベントが終わってほっとしたのが午後2時頃で、夕方5時からは寄り合いがあるので、近くの公園にカメラを持って散歩に出かけました。上天気で家族連れで賑わっていました。幾つかの風景をアップします。
最初の一枚は奇跡の少女と題しました。確かキリストさんかお釈迦様もそうだったと思いますが、小鳥や動物に慕われて、何時も周りは小動物の楽園に様になっていました。この写真もそれを連想させます。


そして、冬眠を忘れた、或いは、暖かすぎて目覚めた亀です。何れにしても、亀は冬眠しているはずです。池の水温が思ったより暖かいのでしょうか?よー、カメよ、大丈夫か?(^_-)-☆

極めつけは、寒桜(河津桜とは違います)が咲き始めています。少し早い気もしますが、冬の訪れが早かったので、咲いちゃったのでしょうか?因みに、河津桜はまだまだ蕾でした。異常気象かも

そして、座敷犬です。何とも、名前が浮かびません、いろんな種類がいるんですね。

昨日の雨が上がって穏やかに晴れ上がりました。若しかしたら、気温も20℃位まで上がったかもしれません。今日は近所のイベントがあり、可也着込んでいったら暑くて、途中で抜け出して、軽装に着替える始末でした。イベントが終わってほっとしたのが午後2時頃で、夕方5時からは寄り合いがあるので、近くの公園にカメラを持って散歩に出かけました。上天気で家族連れで賑わっていました。幾つかの風景をアップします。
最初の一枚は奇跡の少女と題しました。確かキリストさんかお釈迦様もそうだったと思いますが、小鳥や動物に慕われて、何時も周りは小動物の楽園に様になっていました。この写真もそれを連想させます。


そして、冬眠を忘れた、或いは、暖かすぎて目覚めた亀です。何れにしても、亀は冬眠しているはずです。池の水温が思ったより暖かいのでしょうか?よー、カメよ、大丈夫か?(^_-)-☆

極めつけは、寒桜(河津桜とは違います)が咲き始めています。少し早い気もしますが、冬の訪れが早かったので、咲いちゃったのでしょうか?因みに、河津桜はまだまだ蕾でした。異常気象かも

そして、座敷犬です。何とも、名前が浮かびません、いろんな種類がいるんですね。