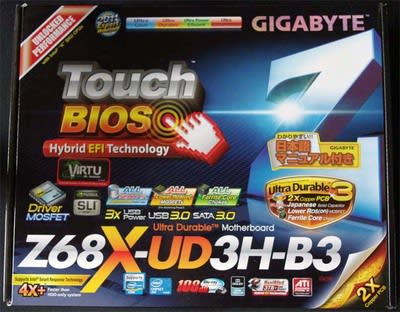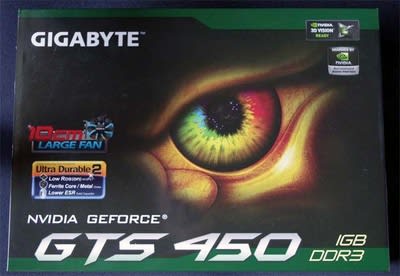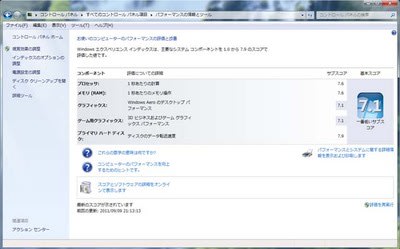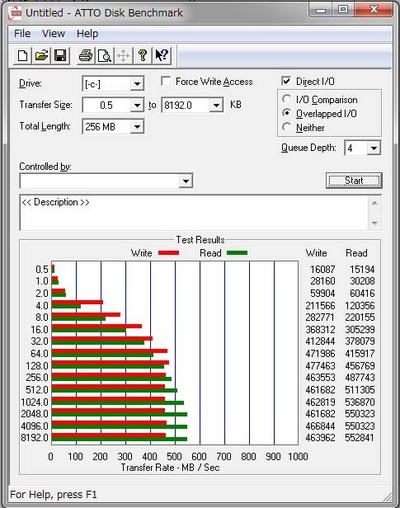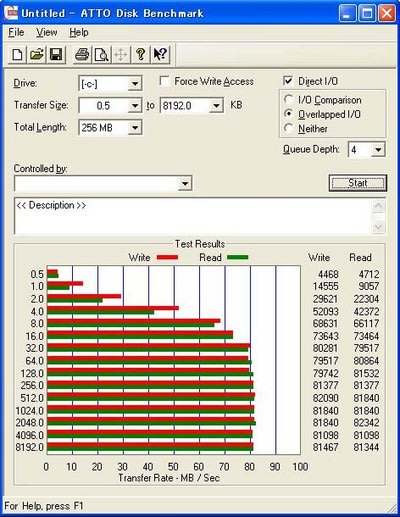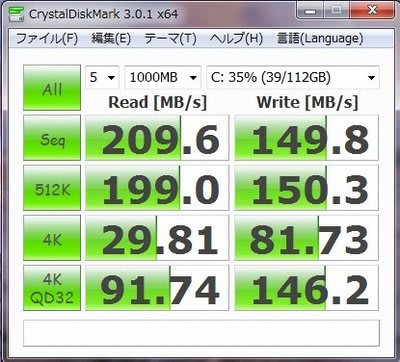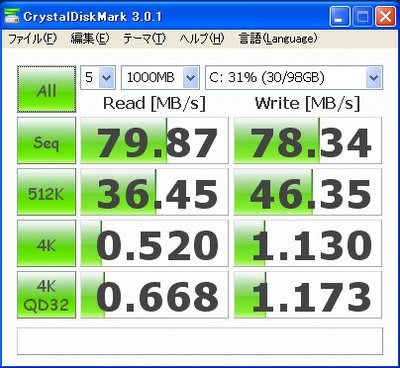65cmフォーク式カセグレン望遠鏡の極軸調整作業を行いました。
極軸調整と言っても、総重量3.5tの望遠鏡を動かすのは大変
です。前回2011年4月13日にK-5で撮影したM51は3分露光で
星ふたつ分程流れていました。
↓
http://sky.ap.teacup.com/eti_forest/45.html
これは東日本大震災の影響を確認するために撮影したもので、
明らかな極軸ズレが確認できました。
今回はそれを修正し、精度検証を行いました。
現場メモ

精度検証にはGA-4を使いました。
GA-4の目盛パターンは、焦点距離1000mmの時に8.6”角/目盛
です。本65cmカセグレンはF12、よってFL=7800mm で、
1.10”角/目盛となります。
TPINTパラメータOFF , 大気差補正追尾ON , 機差補正追尾OFF
<測定1:極軸修正前>
極軸修正前にH=0h , δ=0°付近の星で10分間ノータッチ追尾
を行い、そのズレを記録する。
測定日時:2011年9月7日 19:53:30~20:03:30
測定対象:FK5-709星
測定結果:Fig1の赤矢印のように、8.27”角ズレた。
上記計算結果より、10分間で312.7μmのズレを撮像素子上
に認める結果となった。撮像素子上で星を点像に留めるため
には、30μm~50μmに抑えなければならない。
最近の高画素CCDやデジイチでは、40μm以下が適正である。
前回2011年4月13日のM51は3分間で星ふたつ分のズレであった
から、おおよそ83.4μm程ズレていたことになる。
<測定2:極軸修正後>
測定日時:2011年9月7日 20:46:30~20:56:30
測定対象:FK5-709星・・実際には15度ほど西へ動いている
測定結果:Fig1の第1円以内に収まっていた。
第1円=41.7μmであり、撮像素子上で星を点像に留める
許容値である。焦点距離7800mmで10分間第1円に留まっている
ということは、星像が点像になるということである。
<ピリオディックモーションについて>
65cm望遠鏡のPモーション周期は約4分間であるが、
10分間第1円から出ることはなかった。
第1円=1.1”角であるから、驚異的に高精度である。
-----------------------
以上の結果から、本機に再度カメラを取り付けて実写して
みる必要がある。一番動きが早いH=0h , δ=0°付近で
この性能なので、オートガイダーを使う必要は無いと思う。
F12と暗いので、ISO6400 , 6分×8枚のコンポジットあたりが
良いであろう。また、サブ望遠鏡として15cmED , FL=1800mm
があるので、こちらではもっと楽であろう。
オートガイダー全盛の時代ですが、本当に高精度な赤道儀に
大気差補正、水蒸気圧補正、機差補正追尾をかけることによ
り、かなりの確率で10分間はノータッチガイドで行けそう
な気がします。6X7時代は20分間のノータッチを基準
にしていました。
*第1円=1.1”角の中では、シンチレーションによって
星が常に動いていました。これ以上の焦点距離では
AO補正光学系を使わないと高分解能写真は撮れません。
惑星や月は別ですが。
極軸調整と言っても、総重量3.5tの望遠鏡を動かすのは大変
です。前回2011年4月13日にK-5で撮影したM51は3分露光で
星ふたつ分程流れていました。
↓
http://sky.ap.teacup.com/eti_forest/45.html
これは東日本大震災の影響を確認するために撮影したもので、
明らかな極軸ズレが確認できました。
今回はそれを修正し、精度検証を行いました。
現場メモ

精度検証にはGA-4を使いました。
GA-4の目盛パターンは、焦点距離1000mmの時に8.6”角/目盛
です。本65cmカセグレンはF12、よってFL=7800mm で、
1.10”角/目盛となります。
TPINTパラメータOFF , 大気差補正追尾ON , 機差補正追尾OFF
<測定1:極軸修正前>
極軸修正前にH=0h , δ=0°付近の星で10分間ノータッチ追尾
を行い、そのズレを記録する。
測定日時:2011年9月7日 19:53:30~20:03:30
測定対象:FK5-709星
測定結果:Fig1の赤矢印のように、8.27”角ズレた。
上記計算結果より、10分間で312.7μmのズレを撮像素子上
に認める結果となった。撮像素子上で星を点像に留めるため
には、30μm~50μmに抑えなければならない。
最近の高画素CCDやデジイチでは、40μm以下が適正である。
前回2011年4月13日のM51は3分間で星ふたつ分のズレであった
から、おおよそ83.4μm程ズレていたことになる。
<測定2:極軸修正後>
測定日時:2011年9月7日 20:46:30~20:56:30
測定対象:FK5-709星・・実際には15度ほど西へ動いている
測定結果:Fig1の第1円以内に収まっていた。
第1円=41.7μmであり、撮像素子上で星を点像に留める
許容値である。焦点距離7800mmで10分間第1円に留まっている
ということは、星像が点像になるということである。
<ピリオディックモーションについて>
65cm望遠鏡のPモーション周期は約4分間であるが、
10分間第1円から出ることはなかった。
第1円=1.1”角であるから、驚異的に高精度である。
-----------------------
以上の結果から、本機に再度カメラを取り付けて実写して
みる必要がある。一番動きが早いH=0h , δ=0°付近で
この性能なので、オートガイダーを使う必要は無いと思う。
F12と暗いので、ISO6400 , 6分×8枚のコンポジットあたりが
良いであろう。また、サブ望遠鏡として15cmED , FL=1800mm
があるので、こちらではもっと楽であろう。
オートガイダー全盛の時代ですが、本当に高精度な赤道儀に
大気差補正、水蒸気圧補正、機差補正追尾をかけることによ
り、かなりの確率で10分間はノータッチガイドで行けそう
な気がします。6X7時代は20分間のノータッチを基準
にしていました。
*第1円=1.1”角の中では、シンチレーションによって
星が常に動いていました。これ以上の焦点距離では
AO補正光学系を使わないと高分解能写真は撮れません。
惑星や月は別ですが。