本記事は2018年03月07日の調査によって加筆・修正されています。
修正箇所を青文字で記入。
極軸調整不可の図

技師長の笠原です。
今回は堂平天文台91cmイギリス式反射式望遠鏡のダメ出し第一弾です。
まず結論から言いましょう。
上記のごとく極軸調整が出来ない構造であります!
・北端・南端軸受け共、二つ割りのメタル受け機構。
|
+->自動調芯ボールベアリング受けでした。
・南端はいくらかの球座受けになっている可能性もあるが、
見たところソリッドに固定されていた。
|
+->球座ではなく、自動調芯ボールベアリングでした。
・北端には方位・高度調整機構が備わっているが、これは据え付け時に
36°00’22”に調整するためのものであり、設置後に極軸を微修正
してはいけない。
|
+->理由は・・・ギアトレインが全て極軸ベースプレートに固定
されているからです。
つまり、北端の調整機構を動かそうものなら、
追尾用ウォームホイールとウォームギアのクリアランスも傾きも
狂う構造である。同様に粗動モータ用平ギアもガリガリ・グチャ!
である。

まさかの二分割メタル受け!
自動調芯ボールベアリングが入っています。

南端部も二分割メタル受けだが、やや球座か
自動調芯ボールベアリングが入っています。


何故こうなったのか?
この構造では、据え付け時以外の極軸調整が出来ない。
しかも、据え付け時でさえ、極軸を調整後に各ギアトレインの
アライメントを決めなければならない。
なんという構造だ!有り得ないぞ。
私が6時間調査をして、どう考えても、どうひねっても調整不可能だった。
もちろん、南端ピラーごと方位・高度調整など出来る構造物ではない。
<結論>
60年前の設計時、望遠鏡の極軸が何であるのか?
調整機構をどのように作るべきなのか・・・
誰も知らずに作ったと思われる。
地球の歳差運動とか、地震によるズレ、地盤沈下などなど。
全く考慮されていない。
それでも観望会程度はクリアできている。
3.11の時、北端ピラーが一部欠け、ドームがレールから外れたが、
極軸は岩盤に載っているピラーで守られた模様。
当時の機械屋さんを責めても仕方がない。
機械としては良く出来ています。
<ベアリングを使っていないぞ>
使っています。
60年前の設計時、直径1m越えのテーパーローラーベアリングは
無かった模様。NTNが1.15mの”超大径”ベアリングを作ったという
ヒストリーがあった。これ、ボールベアリングだろうねえ。
よって、
この望遠鏡、大きなベアリングが一切使われていないのです!
”まさかの二分割メタル受け”は、そのような時代背景があってのこと。
円筒コロぐらいは入っているかもしれないけどね。
軸構造に関しては2018年03月08日の記事、
”堂平の宇宙(そら)から12”で詳しく書いています。
良く見ると、ギア軸受けも全部メタル受けです。




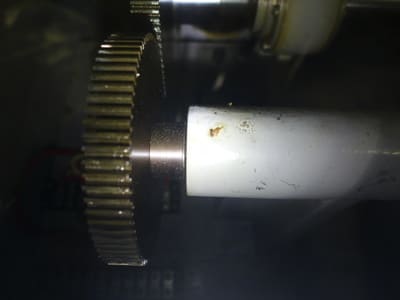
<機内配線整理を開始>
現状使われていないケーブルがゴチャゴチャと這いずり回っており、
実にうっとおしい。

配電盤の中をチョキチョキぶった切った。

今回はスター・トラッカーケーブルとBNCコネクタバーを捨てた。

赤経軸エンコーダと、
絶対に動かしてはならない方位・高度、調整機構もどき。

ドームは三井造船が昭和37年8月11日に納めた模様。


今回はここまで。
修正箇所を青文字で記入。
極軸調整不可の図

技師長の笠原です。
今回は堂平天文台91cmイギリス式反射式望遠鏡のダメ出し第一弾です。
まず結論から言いましょう。
上記のごとく極軸調整が出来ない構造であります!
・北端・南端軸受け共、二つ割りのメタル受け機構。
|
+->自動調芯ボールベアリング受けでした。
・南端はいくらかの球座受けになっている可能性もあるが、
見たところソリッドに固定されていた。
|
+->球座ではなく、自動調芯ボールベアリングでした。
・北端には方位・高度調整機構が備わっているが、これは据え付け時に
36°00’22”に調整するためのものであり、設置後に極軸を微修正
してはいけない。
|
+->理由は・・・ギアトレインが全て極軸ベースプレートに固定
されているからです。
つまり、北端の調整機構を動かそうものなら、
追尾用ウォームホイールとウォームギアのクリアランスも傾きも
狂う構造である。同様に粗動モータ用平ギアもガリガリ・グチャ!
である。

まさかの二分割メタル受け!
自動調芯ボールベアリングが入っています。

南端部も二分割メタル受けだが、やや球座か
自動調芯ボールベアリングが入っています。


何故こうなったのか?
この構造では、据え付け時以外の極軸調整が出来ない。
しかも、据え付け時でさえ、極軸を調整後に各ギアトレインの
アライメントを決めなければならない。
なんという構造だ!有り得ないぞ。
私が6時間調査をして、どう考えても、どうひねっても調整不可能だった。
もちろん、南端ピラーごと方位・高度調整など出来る構造物ではない。
<結論>
60年前の設計時、望遠鏡の極軸が何であるのか?
調整機構をどのように作るべきなのか・・・
誰も知らずに作ったと思われる。
地球の歳差運動とか、地震によるズレ、地盤沈下などなど。
全く考慮されていない。
それでも観望会程度はクリアできている。
3.11の時、北端ピラーが一部欠け、ドームがレールから外れたが、
極軸は岩盤に載っているピラーで守られた模様。
当時の機械屋さんを責めても仕方がない。
機械としては良く出来ています。
<ベアリングを使っていないぞ>
使っています。
60年前の設計時、直径1m越えのテーパーローラーベアリングは
無かった模様。NTNが1.15mの”超大径”ベアリングを作ったという
ヒストリーがあった。これ、ボールベアリングだろうねえ。
よって、
この望遠鏡、大きなベアリングが一切使われていないのです!
”まさかの二分割メタル受け”は、そのような時代背景があってのこと。
円筒コロぐらいは入っているかもしれないけどね。
軸構造に関しては2018年03月08日の記事、
”堂平の宇宙(そら)から12”で詳しく書いています。
良く見ると、ギア軸受けも全部メタル受けです。




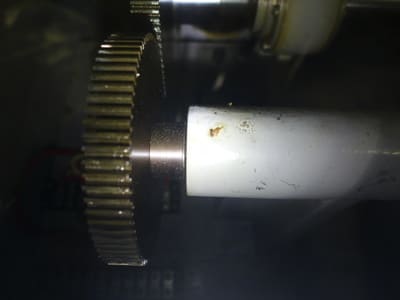
<機内配線整理を開始>
現状使われていないケーブルがゴチャゴチャと這いずり回っており、
実にうっとおしい。

配電盤の中をチョキチョキぶった切った。

今回はスター・トラッカーケーブルとBNCコネクタバーを捨てた。

赤経軸エンコーダと、
絶対に動かしてはならない方位・高度、調整機構もどき。

ドームは三井造船が昭和37年8月11日に納めた模様。


今回はここまで。
















