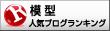いざ切った貼ったしてみると、色々とやりたくなったり、何か形が気に入らなかったりして、結構予定以上の作業になっています
 最初の予定では、踵部分は下方向に延長するだけでしたが、上部の形が気になって成形し直しました
最初の予定では、踵部分は下方向に延長するだけでしたが、上部の形が気になって成形し直しました
画像は塗装後なので、分かり難いのですが、上部を5mm詰めてから、左右の内側を斜めに削り落としています。
高さが決まったので、爪先を削り始めますが、曲線で構成されたパーツなので、角を出しつつ延長します。
 外装の内側を削り込む前ですが、現状でこの程度の角度で可動します
外装の内側を削り込む前ですが、現状でこの程度の角度で可動します
このキット、これで4回目ぐらいですが、爪先と踵のパーツと、脹脛の外装がやたらと干渉するので、角度的な部分で上手く調整してみようと思います。
爪先は、この後先端のプラ棒が固定されたら、上と側面にプラ板を貼って、削り込んで調整します。
 画像で見ると分かると思いますが、踵のパーツは可動に合わせて、なるべく干渉しないように削ってあります
画像で見ると分かると思いますが、踵のパーツは可動に合わせて、なるべく干渉しないように削ってあります
まだ調整段階ですが、脹脛の出っ張ったパーツの形状を、短くしながら少し引っ込めようかと思います。
後は左右の内側を削って、もう少し傾きの角度が出るように調整してみます。
 前方には、この程度の角度まで可動出来ますが、踵を離してよければ、あと少しは曲がります
前方には、この程度の角度まで可動出来ますが、踵を離してよければ、あと少しは曲がります
内部フレームが無ければ、足首周りの外装を可動させたいのですが、内部が露出してしまうので、ちょっと無理っぽい感じです。
チェックしながら感じましたが、あの時代のキットにしては、内部のシリンダーの可動が理に適っていて、その上スムーズなのは凄いですね。
 後方への可動は、踵を立てたままですと殆ど動かないので、画像のような形で行う事になります
後方への可動は、踵を立てたままですと殆ど動かないので、画像のような形で行う事になります
以前、何処かで記載しましたが、HMは基本的に地上での移動は、ホバーによる滑空(ドムのような感じ)なので、走る動作はあまり考慮されていません。
パワーランチャーや、バスターランチャーを構えて、踏ん張って発射するための脚部と考えるべきですね。