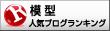コンバーターの可動部ですが、ポリパーツをボークス製のものに交換して、可動箇所に押し込んでチェックしてみたところ、意外と設計図のままの仕様で行けそうな状態になりました
ダンバインの時よりもコンバーターが小型なのと、取り付け位置の関係で、良い感じの強度が保てそうです
この後のダンバインでも、これを参考に一工夫すれば、手の込んだ改造をしなくても何とかなるかも知れませんので、今回のポリパーツ変更は良い発見になりました
 頭部の触角と顎のパーツは、塗装の関係で取り付けていませんが、それ以外のパーツは全て取り付けてあります
頭部の触角と顎のパーツは、塗装の関係で取り付けていませんが、それ以外のパーツは全て取り付けてあります
肩と胴体を繋ぐケーブルは、設計図には13mmと記載されていますが、その長さだと腕を上げた時に外れますので、22mmにして多少弛んだ状態にしています。
このキット、余剰パーツがオーラソードの柄だけで、予備の平手や握り手はありません。
 付属の羽根を使う事にしたのですが、1/72サイズのHGABのものなので、少し大きい様な気がしています
付属の羽根を使う事にしたのですが、1/72サイズのHGABのものなので、少し大きい様な気がしています
オーラソードの件ですが、手に持たせる為に接着すると、柄を収納状態で使う事が無くなるので、これを避ける為に右手の指の間隔を調整して、着脱出来る様にしてみようと思います。
流石にシリーズ後期の製品なので、バランスが良くなっているような気がします。
 少し可動させてみましたが、肘関節や膝関節がそのままレジンパーツで構成されているので、かなり干渉しますね
少し可動させてみましたが、肘関節や膝関節がそのままレジンパーツで構成されているので、かなり干渉しますね
昨日変更した膝関節の構成ですが、設計図の通りの仕様で造っても、足首の可動範囲で妨げられるので、接地面を考えるとどちらでやっても同じ事になります。
現状、右手は親指の調整だけでも、画像程度まではオーラソードを握れます。
 文頭で記載したように、オーラコンバーターは、画像のような状態で安定出来ています
文頭で記載したように、オーラコンバーターは、画像のような状態で安定出来ています
可動範囲や他の部位との干渉も無いので、このままパーツの接着面の成型が綺麗に見えれば、この仕様で仕上げようと思います。
シリーズNo.1のダンバインと比べると、格段に造り易くなっているのと、パーツの全体バランスが整って来ているように感じます。