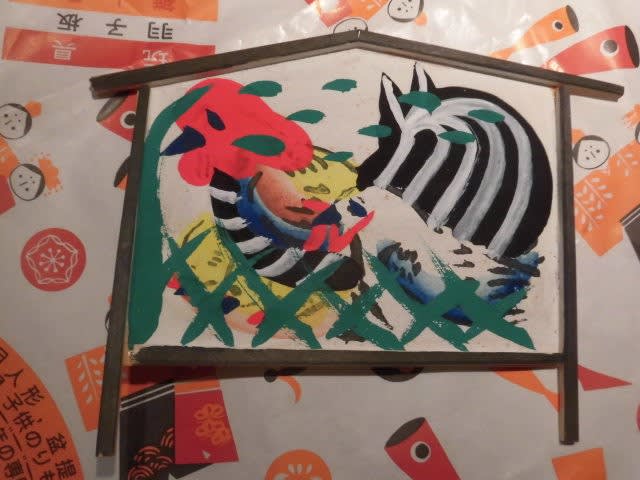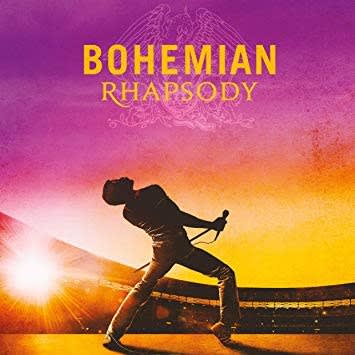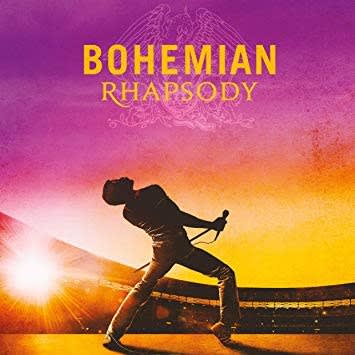
昨年暮れ。いろいろな納めに向けて夜なべをしていた折、たいていNHKの深夜の再放送をつけながら作業をしていたのですが、そこで今この映画が話題となって、「クイーン」のボーカルだったフレディー マーキュリーが今の若い人の間で熱くなっている、というニュースを耳にしました。映画のタイトルになっている「ボヘミアン ラプソディー」が収録されているアルバム「オペラ座の夜」のLPは不思議と買って聞いていたのでした。ただリリースされたリアルタイムではなくて大学に入学した頃だったかと思います。
レコードやCDを自分で買うということは、いいなと思って身銭を切るのでそれなりのレベルに思い入れがあったのですが、自分の音楽の履歴といえば、大学にあがるまで鎖国的状態だったように思います。その時代時代にテレビやラジオから耳に入ってきた楽曲のいくつかは記憶に残っていますが、ロックなどよくわからなかったですね。小学生から中学生にかけて自分の小遣いで買ったレコードというと、テイチクレコードの「日本の民謡シリーズ」の青森、秋田、山形民謡のレコードだったり、高橋竹山の「津軽三味線」、藤本ふみ吉の「江戸端唄」、芳村伊十郎の長唄だったりしました。それでもラジオから流れてくる「カーペンターズ」や「スリーディグリーズ」とか「オリビア ニュートンジョン」なんかの楽曲は耳にには入っていました。
大学に入って同じアトリエの友人が洋楽好きで、その人から聞かされたのが「ボヘミアン ラプソディー」はじめて聞いたときは、曲調が4段階に変化して何とも不思議、それと長い曲だなあという印象でしたが。気になって「オペラ座の夜」を買ってしまったのです。収録されている楽曲がそれぞれあって、一番最後に「ボヘミアン、、、、」が入っているという構成でした。何も予備知識もなく買ったレコードで「クイーン」のメンバーの顔さえ知らなかったのでLPにあるメンバーの顔写真をはじめて見て「ベルばら」みたいだと思いました。フレディ―以外のメンバーもバッハやヘンデルみたいだと思った憶えがあります。同じアルバムに収録されている「You're my best Friend] という曲はメロディーラインがポップな感じでこれも好きでした。不思議なことに、この曲を聴くと世田谷のぼろ市を思い出すんです。(どうして?という具体的な理由はわからないのですが、、。)
音楽的開国となってから小林克也さんの「ベスト ヒット USA]の番組を見るようになってから、リアルで「クイーン」のミュージックビデオだとか化粧品のCMだとかKIRIN メッツ?のCMとかカップヌードルのCMとか目や耳に入ってくるようになった気がするんですが「オペラ座の夜」の顔写真の「ベルばら」ではなくてサーカスのクラウンみたいな全身タイツのようないでたちにはびっくりしましたね。
20代30代はドイツに出かけることが多かったし、ミュンヒェンのいろいろな友達の家に居候させてもらっていたので、フレディ―がどこかに別荘を持っているという話を聞いてどこなんだろうとは思っていました。因みにミーハーですが、第三帝国時代のベルリンオリンピックの記録映画「民族の祭典」の監督だった、また80年代はじめ「NUBA]という写真集を出版して話題となったレニ リーフェンシュタールさんの家は市内 シュワービング地区にあって友人のお父さんの住まいの真向かいでした。
そういうなかで、フレディーが亡くなったというニュースでびっくりした記憶もあります。どっぷりと「クイーン命」的ではなかったけれど、どの曲もフレディーのしなやかで熱い歌唱力に惹きつけられるものがありましたね。
不思議と映画館に足を運ぶということがないんですが、今回出かけてきました。前回映画館に入ったのは十数年前だったか渋谷のスペイン坂の映画館だったように思います。シネコンなるものも初めてです。
何の予習もなしに観たのですが、大筋実際のクイーンとフレディーの人生に沿ったストーリーだったのでしょうか。演じている俳優さんとかまったくわかりませんし、劇中の歌唱は別人が歌っているものですけど。本物をよく意識して演じられているようですね。フレディーの自宅にたくさんの猫さんたちが同居していて話相手になっていること。居間に大きなマルレーネ ディートリヒ の大きな肖像が飾られていること、これなんか実際のことだったのでしょうか。
「ボヘミアン、、、、」の曲そのものはクイーンが一番ピークに登る時期の曲と聞いているので、今回の映画のあたかもフレディー自身の短い生涯を自身が象徴する意思があったのかどうかわかりませんが、こうやって映画を見るとそういう風に見えてきますね。「ツィゴイネル」=「流浪の民」=アウトサイダー=マイノリティー という象徴なんでしょうか。二重三重4重にも彼が生涯被っていたほかの人々からの壁のようなものを示す場面がありました。
最後ライブエイドのステージで終わったのが救いのような。それ以降の彼の生涯は実際しりませんが、映像で作ったら観ていてつらくなるものだったでしょう。
45年の生涯といえば、夭折ですよね。若いころ、憧れの画家の人生と自分の現在の年齢との比較を勝手にしていて、エゴン シーレは28?才、カイム スーチンは 42歳 、オスカー ココシュカ は70幾つ、デイビット ホックニーは存命中、などと自分自身の余命で自分の人生を充実できるかどうかみたいなことを友達と冗談半分話していました。
元旦で56になってしまいましたが、自己満足できる人生の充実を目指したいものです。
そういえば、オープニングの20世紀フォックスのロゴのファンファーレがいつもの「ぱんぱかぱーん」ではなくて同じメロディーなんだけれど。いかにもクィーンっぽい「♪キュイーン♪」というエレキの音なのも面白かったです。