昨日、「漆が付着した1200年前の紙は土中に埋もれても腐らず」と記しましたが、本当です。

この土器は、とある所から出土した約1200年前に使われたもの。
内側に黒っぽく見えるのが漆です。
たぶん、1200年前とさほど状態は変わっていないと思われます。
この土器の側面の漆の状態から、赤矢印の高さまで漆が注がれていたことは確実です。
そして、漆は薄くまんべんなく塗られるので、いっぺんになくなることはありません。
少しずつ使われ、少しずつ減っていくのです。
ただ、漆は乾燥を嫌います。
ですので、それを防ぐために土器にためた漆の表面に紙をかぶせなければなりません。
野菜の煮物を作るときに、灰汁取りシートを使われる方がいらっしゃるかもしれませんが、同じようにして使います。
今と違って昔は、紙は貴重品ですから、反故紙すなわち文字が書かれた紙がふた紙として使われます。
文字が書かれたふた紙に漆が付着すれば、土中でも腐りません。
で、運良く発掘されれば、昔の文字が読めるというわけです。
これを漆紙文書(うるしがみもんじょ)といいます。
なかには「病気になったので、今日お休みします」なんて書かれた欠勤届も出土しています。
もっと知りたいあなた。
平川南著『よみがえる古代文書』(岩波新書)がオススメです。

この土器は、とある所から出土した約1200年前に使われたもの。
内側に黒っぽく見えるのが漆です。
たぶん、1200年前とさほど状態は変わっていないと思われます。
この土器の側面の漆の状態から、赤矢印の高さまで漆が注がれていたことは確実です。
そして、漆は薄くまんべんなく塗られるので、いっぺんになくなることはありません。
少しずつ使われ、少しずつ減っていくのです。
ただ、漆は乾燥を嫌います。
ですので、それを防ぐために土器にためた漆の表面に紙をかぶせなければなりません。
野菜の煮物を作るときに、灰汁取りシートを使われる方がいらっしゃるかもしれませんが、同じようにして使います。
今と違って昔は、紙は貴重品ですから、反故紙すなわち文字が書かれた紙がふた紙として使われます。
文字が書かれたふた紙に漆が付着すれば、土中でも腐りません。
で、運良く発掘されれば、昔の文字が読めるというわけです。
これを漆紙文書(うるしがみもんじょ)といいます。
なかには「病気になったので、今日お休みします」なんて書かれた欠勤届も出土しています。
もっと知りたいあなた。
平川南著『よみがえる古代文書』(岩波新書)がオススメです。












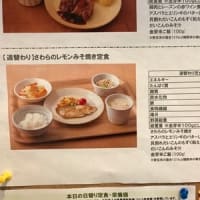













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます