昨日はワッハ7階の「ラクゴリラ」へ。
開場30分前に整理券を受け取ったが、既に30番台後半。
開演してみると、空きもあった。
80人前後の入りかな。
平日だから仕方ないだろう。
「つる」(小鯛):△
芸名が変わったことを軽く振ってネタに入る。
語尾まではっきり喋り、無駄な間投詞がないので聞きやすい。
間や声の調子が、何となく八天みたい。
科白を言い終わってから振るまで、少し引っ張る。
変わったリズム。違和感までは感じなかったが。
張り交ぜの小屏風を褒める所でトチった。
上手く飛ばしていたとは思う。
そのあたりでウケる客、あまり良いとは思えんなあ。
「分かっている」と言ってアホが甚兵衛さんの家を出るのは
好みではない。
小手先でウケを取る感じ。
戻ってきた時の甚兵衛さんの説明では「つー」だけ言わせて、
「後からるー」を説明させないまま飛び出す形。
確かにその方が、アホが次に間違える理屈としては正しいのかも知れないが、
うーん、気にしなくてもいいかな、とも感じる。
2回目に飛び込んだ時に
いきなり「昔一人の老人が」(だったか)から言い出すのは
自然だし、面白かった。
「池田の猪買い」(文三):△
やはり声が出ていないと思う。
声が出ていないおかげで、アホの甲高い声が以前ほど引っ掛からないが。
マクラ・ネタとも本人のにこやかさで押していく感じ。
このニンは希少なものではあるのだが…。
時間がなかったのか、ところどころ抜いていた。
ただ、道を尋ねるところは抜いて欲しくないなあ。
全体に科白廻しが雑。
「のぼせ」を治すために猪の肉を買いに行く流れになってしまっていたが、
あまりにも無茶だろう。
体を(「冷え」を性病と客が認識する/しない、いずれにせよ)
冷え込ませたらいけないから、厚着をする訳だし。
それならば最初の「盆の窪」に据える灸が「冷え」を治すためだ、
と言う方が(同じ嘘ならば)まだマシ。
それ以前に、普通に「のぼせ」が治って「冷え」が出ていることにしたら良いのに。
他にも細かい言い間違いが散見された。
それを拾って笑う客がいるのも如何なものかと思うが。
アホの「行き方が分かっていないのに分かっているように見せる」表情付けや、
甚兵衛さんとアホの「どーんと突き当たる」あたりの説明、
六大夫さんがアホに無言で鉄砲を突きつけるところなど、
細かい部分では丁寧に作られているのに、勿体ない。
あと、最後の六大夫さんが台尻で猪の頭を殴った理由が、
この日の地の説明(「拍子の悪いことに」気絶していただけ)ではよく分からない。
意図的に殴るのであれば、ここは結局、
「猪は気の弱い獣で、簡単に気を失う」(嘘)で誤魔化すしかないと思うのだが。
本当に弾が当たって死んでいる、と六大夫さんが思っていたら、
わざと台尻で殴る訳はないだろうし。
「替り目」(こごろう):△+
「見ず知らずが酒では仲良くなれる、甘いものでは無理」から、
酔っ払いの小咄をいくつか振ってネタに入る。
小咄のつなぎの地の文なし。良いと思う。
俥屋(もちろんタクシーも)なしで家に帰ってくる。
これはこれで良いと思う。
「自分が到来物」とか、まあ悪くない。
夫婦の会話があまり好みではない。
枝雀っぽいのかなあ。
情がべたべたする感じ。
転換までは、「夫婦の関係」に関わる部分はあまり言及しない方が良いと思う。
「髭が生えている」とか、どうも野暮ったく感じる。
転換の科白がちと長いが、
「ほかほかの布団」「ぱりっとした浴衣」など小物を出して感覚で伝えていくのは、
まあ、一つの方法かな。
好みではないけど。
うどん屋を呼ぶ。
ただそれならば、
「燗を付けたい」設定を前半に入れる必要があると思う。
隣に火を借りに行こうとするくらいは。
うどん屋に「後で買ってやるから」は言わない方が良いと思うが。
買ってもらえるんだったら、うどん屋も酔っ払いのウダウダを辛抱するだろうし、
サゲで「向こうで呼んでいる」のも「銚子の替り目」ではなく、
「うどんを食べるために呼んでいる」と思いそう。
友達の娘の結婚式の話は良かった。
見る対象が「娘が大きくなった」ではなく、
「それを育てた父親である友達」にあった。
そのため、個人的に感情移入しやすかったのかも知れない。
嫁はおでん屋から帰ってこない。
酔っ払い自身がうどん屋を呼んでサゲ。
酔っ払いはうどんを食べたい⇔うどん屋は燗を付けさせられると思う
というギャップが、嫁が呼ぶよりも明確になるかな。
ただ、前半とのつながりは悪くなると感じる。
2つのネタを付けた「酔っ払い点描」に見える。
「くさめ茶屋」(花丸):△-
マクラは東京での会など。面白い。
ネタは、ネタそのものの出来が良いとは思えない。
小咄を無理に一席物にしている(薄めている)感じ。
「風邪の神」を呼ぶ前の向かいのお茶屋の繁昌や
「それに引き替え」みたいな話があるのだが、
さして面白い振りとも思えないな。
金を持っている人を呼び込んだら風邪の神様だった、くらいの話で
良いと思う。
向かいの客を送る場面が、何となく落語ではなく芝居っぽい感じ。
科白の言い方、ハメなどの問題かも知れない。
「早く変な客を追い出そうとしている」設定が
なかなか分からなかった。
風邪の神様がずっと居続けしようとしている感じも弱いし。
持って廻らず、
ストレートに「帰って下さい」と言えばいいのに、と途中で思ってしまった。
頬かむりを取る前の「変な客、出たくない」のと
取った後の「風邪の神様、追い出したい」ところが、
ダブっているが微妙にずれていたことも、
分かりづらかった原因かも知れない。
火鉢を持ってきたり、陽気に騒いだりして追い出すのであれば、
逆にどんな遊びをしていたのか、などをもっと明確に描いておく必要があると思う。
「布団部屋で喜ぶ」だけでは不足だろう。
「三人兄弟」(生喬):△+
このネタ、生で見るのはたぶん初めて。
マクラは「兄弟弟子」の話。
このネタでは、けっこう付き物なのかな。
もう少し具体的な話をしても良いかも。
地の文での兄弟の遊び方、服装など丁寧に話す。
意味は100%分かるものではないが、これは必須だろう。
ネタは、もっと「大家」の雰囲気が欲しい。
親旦那、子どもたちとも全体的にガラが悪過ぎる。
長男作次郎、次男彦三郎あたりは、
「ツッコロバシ」の雰囲気があっても良いと思う。
2階で「花札できない」など吉松と話すところは
相対的に「はんなりした感じ」「粋な感じ」が出ていたが、
最初の親旦那との会話、外の市助との会話でも出す必要があると思う。
2階で3人の寝ている順序がよく分からなかった。
年の順に並んでいるのかな。
作次郎が寝床を出るときは、吉松が真ん中であるような振り方を
していたように思うのだが。
吉松の独り喋り。
これも表情付けや語気など、少し恐い。
確かに吉松の遊びや日頃の行動は乱暴なのだろうが、
格子越しに冷やかすあたり、
もう少し「遊び」「シャレ」でからかう気持ちがあった方が良いと思う。
客としても廓の雰囲気を思い浮かべやすいし。
おばさんが宥めるところ、それを受けて男女が落ち着くところは良かった。
サゲ、親旦那がけっこう本気のトーンで
「吉松を跡継ぎにする」と言っているのだが、
ちと無理があると感じる。やはり無茶者ではあるし。
あまり本気で言わさず、
「終わるためのサゲ」程度の重み付けで良いのではないか、と思う。
次回(12月)は大喜利を付け、
年明け(2月)から太融寺に移るそうな。
開場30分前に整理券を受け取ったが、既に30番台後半。
開演してみると、空きもあった。
80人前後の入りかな。
平日だから仕方ないだろう。
「つる」(小鯛):△
芸名が変わったことを軽く振ってネタに入る。
語尾まではっきり喋り、無駄な間投詞がないので聞きやすい。
間や声の調子が、何となく八天みたい。
科白を言い終わってから振るまで、少し引っ張る。
変わったリズム。違和感までは感じなかったが。
張り交ぜの小屏風を褒める所でトチった。
上手く飛ばしていたとは思う。
そのあたりでウケる客、あまり良いとは思えんなあ。
「分かっている」と言ってアホが甚兵衛さんの家を出るのは
好みではない。
小手先でウケを取る感じ。
戻ってきた時の甚兵衛さんの説明では「つー」だけ言わせて、
「後からるー」を説明させないまま飛び出す形。
確かにその方が、アホが次に間違える理屈としては正しいのかも知れないが、
うーん、気にしなくてもいいかな、とも感じる。
2回目に飛び込んだ時に
いきなり「昔一人の老人が」(だったか)から言い出すのは
自然だし、面白かった。
「池田の猪買い」(文三):△
やはり声が出ていないと思う。
声が出ていないおかげで、アホの甲高い声が以前ほど引っ掛からないが。
マクラ・ネタとも本人のにこやかさで押していく感じ。
このニンは希少なものではあるのだが…。
時間がなかったのか、ところどころ抜いていた。
ただ、道を尋ねるところは抜いて欲しくないなあ。
全体に科白廻しが雑。
「のぼせ」を治すために猪の肉を買いに行く流れになってしまっていたが、
あまりにも無茶だろう。
体を(「冷え」を性病と客が認識する/しない、いずれにせよ)
冷え込ませたらいけないから、厚着をする訳だし。
それならば最初の「盆の窪」に据える灸が「冷え」を治すためだ、
と言う方が(同じ嘘ならば)まだマシ。
それ以前に、普通に「のぼせ」が治って「冷え」が出ていることにしたら良いのに。
他にも細かい言い間違いが散見された。
それを拾って笑う客がいるのも如何なものかと思うが。
アホの「行き方が分かっていないのに分かっているように見せる」表情付けや、
甚兵衛さんとアホの「どーんと突き当たる」あたりの説明、
六大夫さんがアホに無言で鉄砲を突きつけるところなど、
細かい部分では丁寧に作られているのに、勿体ない。
あと、最後の六大夫さんが台尻で猪の頭を殴った理由が、
この日の地の説明(「拍子の悪いことに」気絶していただけ)ではよく分からない。
意図的に殴るのであれば、ここは結局、
「猪は気の弱い獣で、簡単に気を失う」(嘘)で誤魔化すしかないと思うのだが。
本当に弾が当たって死んでいる、と六大夫さんが思っていたら、
わざと台尻で殴る訳はないだろうし。
「替り目」(こごろう):△+
「見ず知らずが酒では仲良くなれる、甘いものでは無理」から、
酔っ払いの小咄をいくつか振ってネタに入る。
小咄のつなぎの地の文なし。良いと思う。
俥屋(もちろんタクシーも)なしで家に帰ってくる。
これはこれで良いと思う。
「自分が到来物」とか、まあ悪くない。
夫婦の会話があまり好みではない。
枝雀っぽいのかなあ。
情がべたべたする感じ。
転換までは、「夫婦の関係」に関わる部分はあまり言及しない方が良いと思う。
「髭が生えている」とか、どうも野暮ったく感じる。
転換の科白がちと長いが、
「ほかほかの布団」「ぱりっとした浴衣」など小物を出して感覚で伝えていくのは、
まあ、一つの方法かな。
好みではないけど。
うどん屋を呼ぶ。
ただそれならば、
「燗を付けたい」設定を前半に入れる必要があると思う。
隣に火を借りに行こうとするくらいは。
うどん屋に「後で買ってやるから」は言わない方が良いと思うが。
買ってもらえるんだったら、うどん屋も酔っ払いのウダウダを辛抱するだろうし、
サゲで「向こうで呼んでいる」のも「銚子の替り目」ではなく、
「うどんを食べるために呼んでいる」と思いそう。
友達の娘の結婚式の話は良かった。
見る対象が「娘が大きくなった」ではなく、
「それを育てた父親である友達」にあった。
そのため、個人的に感情移入しやすかったのかも知れない。
嫁はおでん屋から帰ってこない。
酔っ払い自身がうどん屋を呼んでサゲ。
酔っ払いはうどんを食べたい⇔うどん屋は燗を付けさせられると思う
というギャップが、嫁が呼ぶよりも明確になるかな。
ただ、前半とのつながりは悪くなると感じる。
2つのネタを付けた「酔っ払い点描」に見える。
「くさめ茶屋」(花丸):△-
マクラは東京での会など。面白い。
ネタは、ネタそのものの出来が良いとは思えない。
小咄を無理に一席物にしている(薄めている)感じ。
「風邪の神」を呼ぶ前の向かいのお茶屋の繁昌や
「それに引き替え」みたいな話があるのだが、
さして面白い振りとも思えないな。
金を持っている人を呼び込んだら風邪の神様だった、くらいの話で
良いと思う。
向かいの客を送る場面が、何となく落語ではなく芝居っぽい感じ。
科白の言い方、ハメなどの問題かも知れない。
「早く変な客を追い出そうとしている」設定が
なかなか分からなかった。
風邪の神様がずっと居続けしようとしている感じも弱いし。
持って廻らず、
ストレートに「帰って下さい」と言えばいいのに、と途中で思ってしまった。
頬かむりを取る前の「変な客、出たくない」のと
取った後の「風邪の神様、追い出したい」ところが、
ダブっているが微妙にずれていたことも、
分かりづらかった原因かも知れない。
火鉢を持ってきたり、陽気に騒いだりして追い出すのであれば、
逆にどんな遊びをしていたのか、などをもっと明確に描いておく必要があると思う。
「布団部屋で喜ぶ」だけでは不足だろう。
「三人兄弟」(生喬):△+
このネタ、生で見るのはたぶん初めて。
マクラは「兄弟弟子」の話。
このネタでは、けっこう付き物なのかな。
もう少し具体的な話をしても良いかも。
地の文での兄弟の遊び方、服装など丁寧に話す。
意味は100%分かるものではないが、これは必須だろう。
ネタは、もっと「大家」の雰囲気が欲しい。
親旦那、子どもたちとも全体的にガラが悪過ぎる。
長男作次郎、次男彦三郎あたりは、
「ツッコロバシ」の雰囲気があっても良いと思う。
2階で「花札できない」など吉松と話すところは
相対的に「はんなりした感じ」「粋な感じ」が出ていたが、
最初の親旦那との会話、外の市助との会話でも出す必要があると思う。
2階で3人の寝ている順序がよく分からなかった。
年の順に並んでいるのかな。
作次郎が寝床を出るときは、吉松が真ん中であるような振り方を
していたように思うのだが。
吉松の独り喋り。
これも表情付けや語気など、少し恐い。
確かに吉松の遊びや日頃の行動は乱暴なのだろうが、
格子越しに冷やかすあたり、
もう少し「遊び」「シャレ」でからかう気持ちがあった方が良いと思う。
客としても廓の雰囲気を思い浮かべやすいし。
おばさんが宥めるところ、それを受けて男女が落ち着くところは良かった。
サゲ、親旦那がけっこう本気のトーンで
「吉松を跡継ぎにする」と言っているのだが、
ちと無理があると感じる。やはり無茶者ではあるし。
あまり本気で言わさず、
「終わるためのサゲ」程度の重み付けで良いのではないか、と思う。
次回(12月)は大喜利を付け、
年明け(2月)から太融寺に移るそうな。
















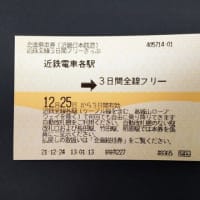
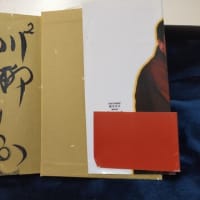

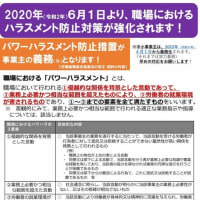







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます