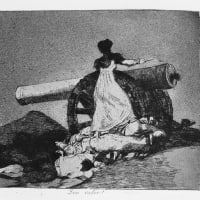人を殺した青年は、聖職者になりうるのか。モーセの十戒を犯した罪人は、神の赦しを絶対に受けられないのか。
ドストエフスキーが考えたとしてもおかしくないテーマである。この小説のような事件というか出来事が、カトリック90%のキリスト教国ポーランドにおいて実際にあったという。『聖なる犯罪者』は、ヤン・コマサ監督のポーランド・フランスのドラマ映画で、海外の2019年映画祭では数々の賞を受賞した作品。
以前、観たい映画としてブログに紹介したが、例のお達しがあり、映画鑑賞はあきらめ家にこもっていた。終了したかと思いきや、まだやっていたので、先週、有楽町のヒューマントラストシネマに観に行った。(去年の11月に東京写真美術館で「ポーランド映画祭」が開催され、本作は注目すべき映画だとして先行公開されたらしい)。

▲公開されて2か月ほどが経った。1日1回の興行でも観客はまばら。アントワーヌ・ランボー監督の『私は確信する』という仏映画に観客は吸い寄せられた。
冒頭に書いたように、本作は大きく野太いテーマがある。20歳そこそこの青年がひょんなことから憧れの神父になりすませてしまう。小さな村の教会ではあるが、村人たちの悩みを解決し信頼を少しずつ獲得する。やがて、贖罪の途をしめし、困難を克服して生きる歓びさえも人びとに授けてゆく。(魂のグローイングアップ映画といえるか)。
映画は、彼の素性がどうやって暴かれてゆくのか、そんな緊張感がずーっと張りつめる。青年が殺人を犯したという過去についてはほとんど語られない。光と闇のなかで彷徨うのは、彼だけではない。アルコール依存症の前神父、或る事件に執着し続ける村人たち、環境破壊をたくらむ製材所の社長も、精神の羅針盤を失った子羊ではないか・・。
この青年・偽神父は、決まりきった宗教の掟に縛られ、金や力のあるものが世の中を支配している現実を疎ましく思っている。神父は自分の天職だと思ったのかもしれない。しかし、彼は自分の素性がばれたとしても、神の救いを人々に示したいと願う。そしてやがて、真実に生きることの本質にめざめ、自己をさらけ出すことの大切さに気づきはじめる。
宗教にそれほど救いを求めなくなった現代の世なのに、神の道を選び、聖職者にならんことを欲した彼の名前はダニエル。今の若者にふさわしく、聖書の言葉をラップのように語り、ロックシンガーのように全身でシャウトする。悲しみや痛みは、心の底から叫ばなければ消えてはなくならない、と身を挺して人々に訴える。
映画の舞台は、少年院、小さな村、教会と住まいだけの、はっきり言えばスケール感は小さい。ただ青みがかったダークの色調が重く、カメラワークはつねに静かだ。時に衝撃的なシークエンスもあるが、全体的に落ちついていて、ポーランド映画ならではの格調さを感じたのは小生だけだろうか・・。
ハリウッドに行ったポランスキーを除いて、ポーランド映画はアンジェイ‣ワイダをはじめ重厚でシリアスな作品が多い。実はワイダをのぞけば、イェジー・カヴァレロヴィチの『夜行列車』と『尼僧ヨアンナ』を観たぐらいの生半可なのだ。実に、ポーランド映画を語る資格がないのだが、久しぶりにこれぞ東欧の映画だという印象をもった次第。
さて、『聖なる犯罪者』は、この日本において何を問いかけるのか。
映画評論家でもある四方田犬彦は、最後にこう結んでいた。
神学者ニコライ・クザーヌスが説いたように、聖なるものと汚れたものが、強烈に相反しながら深いところで象徴的に一致を遂げるというのが宗教の原理である。(中略)この映画は中世に唱えられたこの原理に基づく興味深い寓話として、戒律なき日本社会の観客にも、何か大切なことを告げているように、わたしには思われる。

▲偽神父ダニエルを演じた若者は、バルトシュ・ビィエレニアという俳優(当時28歳)。
この映画は事実をもとに、脚本が先行して作られた。オリジナルはマテウシュ・パツェヴィチュによる脚色で、彼はまだ29歳の俊英であり、16人の候補のなかから40歳の監督ヤン・コマサを指名したとあった。もっとも二人は前作の『ヘイター』でもタッグを組み、国際的にも高い評価をうけている。
ポーランドはかつて第264代ローマ教皇となったヨハネ・パウロ2世をバチカンにおくり出した国。いうまでもなく東欧の社会主義国でありながら、カトリックの命脈を絶え間なく守り続けてきたキリスト教国だ。なおかつ文学をはじめ芸術・文化はそうとうに成熟している国である。最近『異端の鳥』が映画化されるなど、ポーランド系文化に目を瞠るものが増えている(監督はチェコ出身であり、原作はポーランドのイェジー・コシンスキだが、作品としてはチェコ映画)。
▲『メッセージ』という映画の記事を書いたとき、上のトレーラーを貼りつけたが、正式にこちらに引っ越した。