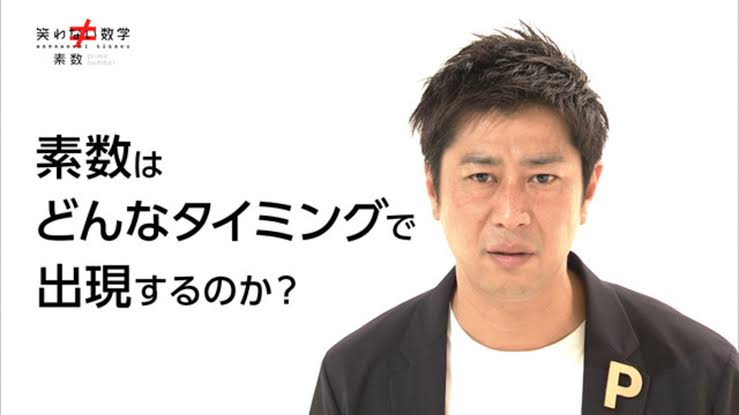
NHKBSでは「素数の魔力に囚われた人々」という番組が流れてた。これは「リーマン予想・天才たちの150年の闘い」というタイトルで2009年に放送されてたものだ。
オイラーから”素数の謎”のバトンを譲り受けたガウス少年は、素数のパターンを自然対数logに見出した。つまり、素数の出現確率が自然対数の逆数に一致すると予想した。事実、ガウスの素数定理は”π(x)~x/logx(x→∞)”で知られる。
ずっと前に書き溜めてた記事なので、曖昧で抽象的な所があるかもですが、ご勘弁をです。
ガウスの素数定理
ガウスの弟子であったリーマンは更にこの素数定理(=素数密度の近似式)を推し進め、素数の謎を自然対数ではなく、複素解析関数であるゼータ関数に追い求めた。
こうしてリーマンは、ガウスの素数定理を”誤差項付きの複素解析的素数公式”(明示公式)として、リーマン予想と共に発表する。
しかし、リーマンはあろう事にガウスの素数定理を証明してなかったし、素数公式の中核をなす周期項を満たすリーマン予想をも証明していなかった。
この未だ未解決の”リーマン予想”で知られるリーマンの素数論文は理解するのに30年、リーマンの素数公式を証明するのに更に10年が掛かった。
因みに、若干15歳(1792年)のガウス少年が予想した素数定理は、その約100年後の1896年に、プサンとアダマール(共に仏)により独立して証明された。証明にはゼータ関数と複素解析が使われたが故に、”リーマンの弱い素数定理”とも呼ばれる。更に、初等的なやり方でセルバーグとエルデシュが独立して証明を与え(1949年)、素数定理の物語は幕を閉じる。
しかし、リーマン予想は謎のままであり続けた。この謎に一番近づいたのが、20世紀の最高の知性の1人で、あまりにも壮絶な人生で映画「ビューティフルマインド」のモデルにもなったジョン・ナッシュJrである。
彼はリーマン予想を解読する為に、ある時は論理的にある時は非論理的に考える必要に駆られた。そこで彼が得た結論は”リーマン予想は正しい事も正しくない事も証明できない”という事だ。しかしその時は、ナッシュは既に深刻な妄想型精神分裂症に陥っていた。
勿論、精神を病んだのは彼だけではない。ハーディングを始め、数多くの著名な数学者も精神を病んでしまう。お陰で、リーマン予想に挑戦する事は”自殺行為を意味する”と言われるようになった。
アラン・チューリング(1912-1954)もその1人であった。エニグマ暗号を解読し、第二次大戦の英雄とされた彼もリーマンの謎を解読する為に、自ら開発したチューリングマシンをフル稼働させたが、リーマン予想が正しい事を加速させるだけに終わった。
結果、精神的に追い詰められた彼もまた、青酸カリ入りの林檎を食べ、謎の自殺を遂げたとの噂もあるが、私的には同性愛説よりもこっちの方が信憑性は高く感じる。
オイラーからガウスへ
前回「その3」でも書いたように、2^(2ⁿ)+1で示されるフェルマー数は、オイラーによって6番目のフェルマー数が素数でない事が証明され、フェルマー数の役割を終えたように見えた。因みに、フェルマーはフェルマー数が素数であると信じていた。
がしかし、オイラーの後を引き継いだガウスは、”素数pがフェルマー素数の時、正p角形が定規とコンパスで作図できる”事を発見しました。
「正17角形の作図」でも紹介したので詳しくは書きませんが、このガウスの作図定理によれば、フェルマー素数は、F₀=2^(2⁰)+1=3、F₁=2^(2¹)+1=5、F₂=2^(2²)+1=17、F₃=2^(2³)+1=257、F₄=2^(2⁴)+1=65537と、この5つだけである事をオイラーが証明したので、作図可能な正p角形は、p=3,5,17,257,65537の時だけとなる。
但し、ガウスは正17角形の作図可能性を発見し、証明したが、正p角形の作図可能性を厳密に証明したのは、後のワンツエルという数学者とされます。
こうした正p角形の作図可能性を”代数的可解性”と呼ぶとするなら、それはガウスによって、古代ギリシャ時代の幾何学が素数という神秘な数を通じて、代数論や(解析学を含む)関数論という、新しい現代数学の領域に足を踏み込んだ瞬間でもありました。
ガウスはこの発見がとても嬉しかったらしく、自分のお墓に正17角計を刻む事を申し出たそうです。
因みに、ギリシャ時代には”(目盛のない)定規とコンパスで作図できる”図形が研究の対称になり、正3角計、正4角計、正5角計、正6角計までは判ってたのですが、正7角計は判ってなく、ガウスによる解決まで千年以上の歳月を要しました。
ラテン文学か?数学か?で迷ってたガウス青年は、この発見により、数学者の道を選択します。が結局は、数学者として正職に就く事はなかったのですが、数学史において重要な一歩となりました。
数学だけでなく、天文学や電磁気学や統計学に測量学など、様々な分野で数多くの業績を残したガウスですが、素数の研究にても画期的な発見をします。
それは「ガウスの素数定理」と呼ばれ、”x
以下の素数の個数π(x)がx/logxで近似される”という定理で、”π(x)~x/logx(x→∞)”と書く。これは、xを無限に大きくした時、π(x)/(x/logx)が限りなく1に近づくという意味です。
確かに、素数の出現は非常に不規則で、言わばデタラメに近く、このデタラメに潜む法則を炙り出すのが確率であり、事実、素数には確率法則に近い性質が備わっている。そして素数出現の確率法則には、底をe=2.71828…(=ネイビア数)とした自然対数logが出現する。
因みに、対数には自然対数と(底を10とした)常用対数があるが、今では自然対数が主に使われ、logₑxなどとeを表記せず、logxやlnxなどと書きます。
ガウスの素数定理については、過去に何度も記事にした(リーマン2-2、2-5、2-7、2-8)ので詳しい事は省くが、ガウスは統計的確率の視点で素数の出現分布を捉えた。
事実ガウスは、1792年頃に”xが素数である確率は1/logxで近似できる”事を(オイラーの素数密度の発見からの継承ではなく)単に経験的観察から発見します。
素数表から眺めた素数定理
15.6の頃のガウスは、ランベルトの素数表を使い、千ずつに区切った区画毎に素数を数え、何十万に至るまで数え上げた。つまり、π(1000)、π(2000)−π(1000)、・・・を求めたが、カッコ内が百万に及ばない所で諦めた。この方法では手間と時間が掛り過ぎるのだ。
そこで考えついたのが、1日15分と時間を決め、千個単位の中からランダムサンプリングを行い、統計的な振舞いを調べる手法であり、これに必要なのは829までの素数である筈だった。
少年はまず、700001から701000までの素数を抜き出した。ルート判定法から√701000≒838.2574...より小さい最後の素数は829。しかしガウスは、47で割る所までで諦めた。時間にして僅か30分、割るべき素数がまだ130個も残ってたのに・・・
とうとうガウスは、未完成の素数表を眺めてる内に、素数の出現頻度が対数の反比例(1/logx)に近づく事を突き止める。
つまり、x/π(x)に注目し、xが1000毎の値を眺め、x/π(x)の値の差が一定である事に気付いたのだ。
そこでeを底とした指数関数eˣを考える。x=1⇒e¹=2.718281828...、
x=2⇒e²=7.389056098...、
x=3⇒e³=20.085536923...、
x=4⇒e⁴=54.598150033...。
これは、引数xが1つ増える事に、値(eˣ)はe倍になる事を示す。が、この逆はどうなるのか?
答えは、引数xがe倍なる毎に値が1増える様な関数。つまり、指数関数(y=eˣ)の逆関数である対数関数(y=logx)となる。前者は”1つ増える”と”e倍”を、後者は(両辺の対数をとり)xとyを交換すれば理解出来ますね。
そこでガウスは、引数xをlogxで表し、xが1000毎のlogxの値を観察し、xが大きくなる毎にlogx−x/π(x)が小さくなる事を発見する。
これにより、x/π(x)~logxとなるから、ガウスの素数定理である”π(x)~x/logx”がめでたく導けた。
詳しくは「リーマン2-7」を参照するとして、天才ガウス少年が導いた近似がどれほど正確なのかは以下の通りである。
実際、x=10²の時、π(x)=25、x/logx=21.7で、その比は1.152。x=10³の時、π(x)=168、x/logx=144.8で、その比は1.160。以下同様に、x=10⁴の時の比は1.132、x=10⁵の時の比は1.104、x=10⁶の時の比は1.084となり、僅か8%のズレしかない。
つまり、数字が大きくなるにつれ、1に限りなく近くなる。
素数の出現確率
以上より、素数定理を確率で言えば、x以下の素数の個数~x/logx=x(1/logx)となる事から、"x以下の自然数が素数である確率はおおよそ1/logx”と見る事ができる。
これは、自然数xが偶数である確率~1/2より、nまでの偶数の個数はおおよそn/2だから、掛け算されてる1/2が偶数である確率となる事からも、簡単に理解出来る。
しかし、(一定な)偶数の確率と違う所は、(不規則な)素数である確率が元の数xに依存する事であり、”x付近の数が素数である確率(=素数密度)~1/logx”と解釈できる。
例えば、x=1000000の時、この付近にある数が素数である確率は1/log(1000000)≒0.072となる。
もっと具体的に言えば、”x付近の自然数L個の中に素数は、おおよそL/logx個ある”と出来る。事実、ボレル(仏)が調べた所、9000000と10000000の間の長さ1000000の区間には素数が62090個存在する。また、この区間の数が素数である確率は、その中間の数の自然対数の逆数=1/log(9500000)と考えられてる。
実際にエクセルで計算すると、この区間の素数の個数は、1000000/log(9500000)≒62240となり、ほぼ一致してるのが判る。
但し、これらの確率は解釈であり、厳密な意味での確率ではない。というのもxが決まれば素数かどうかは(計算は面倒だが)確定出来る訳で、確率で表される(丁半賭博の様な)不確定現象ではない。
つまり、素数かどうかは確定現象でありながら、”x付近の数が素数である確率は1/logxである”事が近似的に成り立つ。言い換えれば、素数が確実現象でありながら、ある意味では不確定現象(確率)として扱う事ができる。
素数の持つランダムな現象と規則的な現象。この2つの間に揺れ動くのがリーマン予想(仮説)であり、素数の神秘性にある種の認識を与えてくれる。
一方でガウスは、以上の素数定理よりも精度の高い以下の近似式をも見出してた。
π(x)~∫(2,x)dt/logt=Li(x)(対数積分)ですが、これも確率の近似という点で眺めれば、素数の確率的理解を正当化するものである。
事実、プサンとアダマールは、π(x)=∫(2,x)dt/logt−R(x)と書く時、誤差項R(x)は右辺の第一項に比べ、(相対的に見ればだが)非常に小さい事を示した。但し、R(x)はxの増大と共に0に近づく訳ではなく、非常に不規則な変化を示す事に注意です。
更に、(x/logx)’=1/logx−1/(logx)²に注意すれば、π(x)~∫(2,x)dt/logtから”π(x)~x/logx”が導ける事にも、ガウスは気付いていた。しかし、”π(x)~x/logx”の方が簡単で判りやすいので、これを”素数定理”と呼ぶ事の方が多い。
因みに、ガウスとほぼ同時期に素数分布を研究したジャンドルは純粋に経験的手法により、”π(x)≒x/(logx−1.08366)”を見つけ出した(1798年)。これは明らかにガウスの素数定理を推測できる。
最後に
以上の対数積分=Li(x)だが、リーマン予想の論文の最後には、”実際にLi(x)とx以下の素数個数の比較にて、ガウスとゴールドシュミットによりx=300万まで調べられ、素数の数は最初の10万までLi(x)よりも常に小さく、以降はxが増大するに連れ、少しずつ増大する。
しかし素数密度の増減は、私が大いに注目してる周期項(リーマン予想)に依存する。今後の課題として、素数密度に関する式(リーマンの明示公式)にて、個別の周期項の影響を調べる事は興味深い。また、私の明示公式(誤差項付き複素解析的素数定理)の方が最初の100の所でもより一致し、より規則的でもある”と自信たっぷりに語っている。
つまり、ガウスの素数定理よりも精度が高く、より規則的で、素数の神秘性に限りなく近づいたリーマン予想とも言える。
以上、1760年のオイラーに始まり、1791年のガウス(の素数定理)とルジャンドルの素数定理(1798)、そしてディリクレの算術級数の素数定理(1838)にチェビシェフの(誤差が±10%以下の)粗い素数定理(1848)、メルテンス(1896)からプサン&アダマール(1896)に、セルバーク&エルデシュ(1949)の初等的証明に至る。
またまた、長くなり過ぎたので今日はココマデにします。










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます