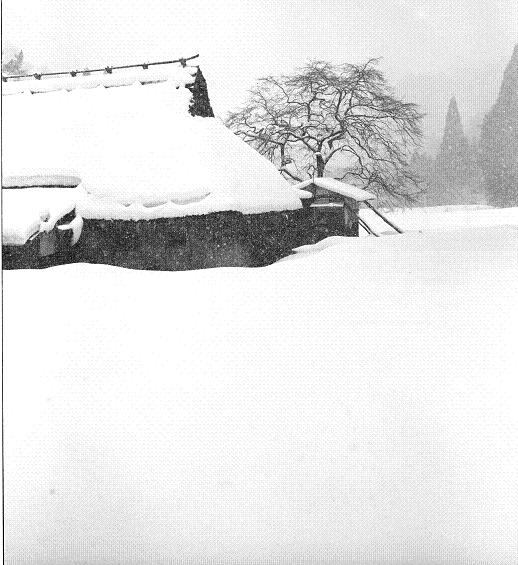撮影場所 宮崎県佐土原周辺 C57形蒸気機関車、門デフ
佐土原駅に帰る途中、雨が降ってきた。上りの貨物列車が通る時間であった。
雰囲気のよい川と橋があったので待つ。
暗くなってきたそれでもシャッタースピードは1/125秒はほしかった。
西の空が明るくシルエットになるがやむを得なかった。
自然が残る川で木々が生い茂り河童の居そうな川だった。
鉄橋も人気のある撮影場所のひとつである。
このブログのジャンルにも鉄道がある。鉄道ファンが大変多いの投稿数も多い。
投稿を見ていると電車や機関車が進んでくるのを正面から撮ったものが圧倒的に多い。
鉄道写真は電車の写真ばかりではないはず。
私も鉄道を撮影していた頃は若かったのでやみくもに機関車ばかり撮っていた。それも撮影ガイドブックを見て撮影していた。
鉄道写真を撮る前に鉄道は何のためにあるのか、鉄道設備には何があるのか、鉄道で働いている人の仕事はどんなものがあるか、車両の種類、沿線の風景にはどんなものがあるか、五百項目位を列記してみるのがよい。
その中から何にポイントを絞って自分独自のテーマを持った方がよいと思う。
それと数値目標にできるテーマがよいと思う。
たとえば
1.列車が鉄橋を走る風景を1000箇所撮影する。
2.踏切を列車が走る光景を1000箇所撮影する。
3.駅に列車が停車、通過している風景を1000箇所撮影する。
4.機関車を1000両撮影する。
5.駅の通勤、通学風景を1000箇所撮影する。
6.車内風景を1000箇所撮影する等。
1000という数字は千くらい撮れば継続する強い心が生まれる。また知識も増えるし発展的に周囲の事が見えてくる。信念や思想も生まれてくるはず。
私は車椅子生活のため鉄道写真は撮れないし今は別のテーマを持っているので、言いたい放題で申し訳ありませんが
誰か日本の鉄橋千箇所にチャレンジ下さい。