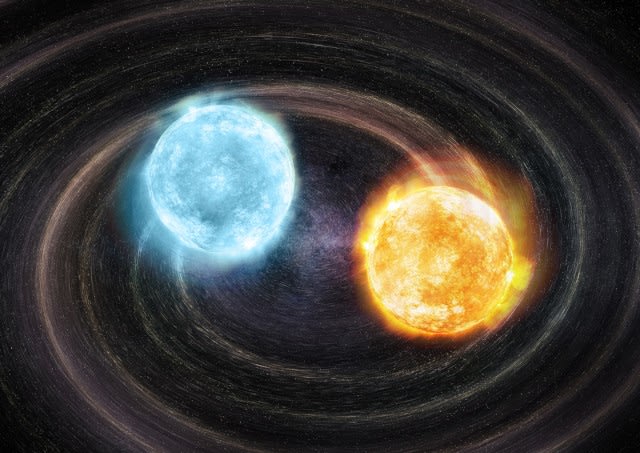今回は2年前に行ったツーリング。
インスタUPのみだったのでブログ記事にしてみました。
走ったのは5月の淡路島。
高速を使って一気に南端まで走ったところで朝ごはん。
サンセットラインをのんびりと流しながら北上して帰ってきました。
走りに行ったのはゴールデンウィーク真っただ中の5月1日(火曜日) 晴れ。
神戸淡路鳴門自動車道を下りたのは淡路島南IC。
少し走れば“絶景レストランうずの丘”に着きました。
ここで頂くのは、淡路島の生赤うに・淡路牛・島たまごを使った丼“島のうにくまぜごはん”です。
“うにく”の牛丼は初めてなんですね~ (^^♪ 食べる前からワクワクしてきます。
数量限定なんで開店20分前に着いちゃいました。
運ばれてきたのは一般的な茶一色の牛丼でなく、いかにも上品そうな色味の牛丼です。
卵黄のまぜご飯の上には、淡路牛上ロース、そして生ウニ。
ここに、うに醤油をかけて半分ほど食べた後は、薬味、海苔を添えて楽しんじゃいます。
やわらかロースの甘みと、うにの濃厚な旨味が絡んできます (>_<)
うにと卵黄の組み合わせが良い仕事をしている牛丼でした。
さて、レストランを後にすると北上するのみ。
うずしおラインから林道柿ノ木線を走って、県道31号の標識が見えてくると海までもうすぐ。
ここからは、左手に海を見ながら気持ち良く走れるサンセットラインが始まります。
サンセットラインは県道31号の愛称で、夕日がきれいな海沿いのルートです。
今回は青空の下を走って多賀の浜海水浴場で休憩。
お湯を沸かしてコーヒー飲んで昼寝をすれば、そろそろ出発です。
時刻は14時、時間もお腹もまだまだ余裕あり。
せっかく淡路島まで来たから美味しい魚も食べたいなぁ~
っということで、海鮮のお店を探しながら走っていると、ありました!
鮮魚店が営んでいるお店“魚竹鮮魚店やけんど〜海鮮どんや”、これは期待できそうです。
春の訪れを告げるサワラを使った丼を注文するも、まさかの“生サワラ丼”売り切れ…
気が付いた時には、やわらかプリプリ生しらす丼を頬張ってました。
意外にも付いてきたのはポン酢、出汁醤油じゃないんですねー
生たまごと合うのか不安だったので、ポン酢で半分食べた後に生たまご投入、合いますね。
このあと石田の棚田を探すも(迷う…)見つからず。
走っていて目に入った“鯉のぼり”の文字を手掛かりに行ってみると元気に泳いでました (^o^)
最後に立ち寄ったのは、明治初期の大阪条約によって建設された5基の灯台の最初の一つ“江埼灯台”です。
駐車場にバイクをとめて長い階段を上っていくと、まだまだ現役の古い灯台が出迎えてくれます。
瀬戸内海や明石海峡大橋を一望したところで今回のツーリングは終了。
天気も良く、時間の余裕たっぷりなツーリングでした。
こちらの記事もどうぞ

幻の但馬牛を食べに行ってきた! 浜坂~小代ツーリング
インスタUPのみだったのでブログ記事にしてみました。
走ったのは5月の淡路島。
高速を使って一気に南端まで走ったところで朝ごはん。
サンセットラインをのんびりと流しながら北上して帰ってきました。
 |
神戸淡路鳴門自動車道を下りたのは淡路島南IC。
少し走れば“絶景レストランうずの丘”に着きました。
ここで頂くのは、淡路島の生赤うに・淡路牛・島たまごを使った丼“島のうにくまぜごはん”です。
“うにく”の牛丼は初めてなんですね~ (^^♪ 食べる前からワクワクしてきます。
数量限定なんで開店20分前に着いちゃいました。
運ばれてきたのは一般的な茶一色の牛丼でなく、いかにも上品そうな色味の牛丼です。
 |
ここに、うに醤油をかけて半分ほど食べた後は、薬味、海苔を添えて楽しんじゃいます。
やわらかロースの甘みと、うにの濃厚な旨味が絡んできます (>_<)
うにと卵黄の組み合わせが良い仕事をしている牛丼でした。
さて、レストランを後にすると北上するのみ。
うずしおラインから林道柿ノ木線を走って、県道31号の標識が見えてくると海までもうすぐ。
ここからは、左手に海を見ながら気持ち良く走れるサンセットラインが始まります。
ちなみに、林道柿ノ木線は全線舗装路されていましたが、伸び放題の雑草がビシバシ当たってくるし視界が悪かったですね~
淡路島らしい手入れがされていない林道でした。
淡路島らしい手入れがされていない林道でした。
サンセットラインは県道31号の愛称で、夕日がきれいな海沿いのルートです。
今回は青空の下を走って多賀の浜海水浴場で休憩。
お湯を沸かしてコーヒー飲んで昼寝をすれば、そろそろ出発です。
時刻は14時、時間もお腹もまだまだ余裕あり。
せっかく淡路島まで来たから美味しい魚も食べたいなぁ~
っということで、海鮮のお店を探しながら走っていると、ありました!
鮮魚店が営んでいるお店“魚竹鮮魚店やけんど〜海鮮どんや”、これは期待できそうです。
春の訪れを告げるサワラを使った丼を注文するも、まさかの“生サワラ丼”売り切れ…
気が付いた時には、やわらかプリプリ生しらす丼を頬張ってました。
意外にも付いてきたのはポン酢、出汁醤油じゃないんですねー
生たまごと合うのか不安だったので、ポン酢で半分食べた後に生たまご投入、合いますね。
 |
走っていて目に入った“鯉のぼり”の文字を手掛かりに行ってみると元気に泳いでました (^o^)
最後に立ち寄ったのは、明治初期の大阪条約によって建設された5基の灯台の最初の一つ“江埼灯台”です。
駐車場にバイクをとめて長い階段を上っていくと、まだまだ現役の古い灯台が出迎えてくれます。
瀬戸内海や明石海峡大橋を一望したところで今回のツーリングは終了。
天気も良く、時間の余裕たっぷりなツーリングでした。
こちらの記事もどうぞ

幻の但馬牛を食べに行ってきた! 浜坂~小代ツーリング