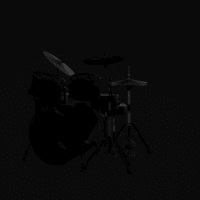今回は音楽記事です。
前回の音楽記事では、寺山修司に関連する人物であり、かつ、第三回中津川フォークジャンボリーで起きたステージ占拠事件にも関わっているとされるアーティストについて書くと予告しました。
それは誰かというと……小室等さんです。
この方の名前は、これまでフォークについて書いた記事のなかで、一度出てきました。
それは、フォーライフレコードについて書いたときのこと。フォーライフレコードを創設した4人は、吉田拓郎、井上陽水、泉谷しげる、そして小室等という顔ぶれでした。すなわち、小室等という人はこの3人と肩を並べるレジェンドなのです。
彼が寺山修司とつながるのは、「さよならだけが人生ならば」という歌において。
寺山修司の作詞で、カルメン・マキの歌として有名ですが……この歌を作曲したのが、小室等さんなのです。
小室等さんは、みずからの率いるグループ「六文銭」でも、この曲を発表しています。
この「六文銭」というグループは、先日ちょっと言及した木田高介さんが在籍していたこともあります。
グループ名は、モームの『月と六ペンス』からとったもの。
その『月と六ペンス』のタイトルは、芸術家の魂と金銭的な価値観を対比させたものといわれます。
つまりは、プライマル・スクリームが「お前は金を持っている/俺は魂を持っている」と歌った感覚でしょう。
「六文銭」だったら、お金のほうになってしまうんじゃ……とも思ってしまいますが、もちろん小室等は魂のほうの人です。
それは、彼の歌ってきた歌を思い起こせば、疑念の余地もないことです。
たとえば、ファーストソロアルバムのタイトル曲である、大岡信作詞の「私は月にはいかないだろう」。
その冒頭部分では、こう歌われます。
私は月にはいかないだろう
わたしは領土はもたないだろう
わたしは唄をもつだろう
ここでは、月へ行くということは、金銭とか名声を追い求めるといった意味合いであろうと考えられます。米ソの宇宙開発競争を念頭に置いているのかもしれません。そういったことと、「唄」が対置されているわけです。
その「唄」が、つまり魂ということなのです。
小室等さんは、よく谷川俊太郎さんの詩で歌ったりしていますが、要はそういうことです。
そして、その延長線上に寺山修司の詩もあったということでしょう。
一応解説めいたことをいっておくと、「さよならだけが人生ならば」というのは、井伏鱒二が「さよならだけが人生さ」といったのに対するアンサーソングという意味合いです。井伏鱒二といえば、太宰治の師匠であり、日本文学界におけるレジェンド。寺山修司を介して、そういうところにまでつながっていくのです。
ただし、小室等さんに関していうと、彼はむしろ、寺山修司よりも唐十郎の状況劇場との仕事でよく知られています。
状況劇場は、寺山の天井桟敷と並んで60年代末ごろに注目されたアングラ劇場です。
天井桟敷とはライバル的な関係ともみられていて、実際に乱闘騒ぎを起こしたこともありました。
アングラ劇というのは、そういうところがあるのです。
唐十郎は、新宿中央公園に無許可で紅テントを立てて劇を上演し逮捕されるという事件を起こしたこともありました。こういうところが、あの全日本フォークジャンボリーにおけるステージ占拠事件とつながっているようにも思えます。
…と、ここでそのステージ占拠事件について書いておきましょう。
これは、第三回全日本フォークジャンボリーの最中に聴衆がメインステージを占拠し、ジャンボリーが中止に追い込まれたというものです。この回が中断しただけでなく、おそらくはこれが原因で、翌年以降も行われなくなってしまいました。
この手の話がたいていそうであるように、事件の原因や推移に関しては諸説あり、おそらく“真相”は誰にもわからないのだと思われますが……サブステージにおける吉田拓郎さんの演奏後に小室等さんが「みんなメインステージに行こう」と呼びかけたことが、事件にいたる伏線の一つともいわれています。まあそれも、子細に検証してみれば、事件の原因といえるほどのものではないようですが……
商業主義批判が背景にあるともいわれ、また、学生運動の過激派が関与しているともいわれ……なかなか複雑な要素がからみあっているようであり、結局真相は闇の中なんですが、ともかくも、あの時代だからこそ起きた事件とはいえるでしょう。
60年代の学生運動や、それとベクトルを共有していた種々の芸術思潮は、たぶんに挑発的な性向を持っていました。その挑発性はときに暴走することがあり、その暴走がある一定のラインを超えてしまうと、それまで共感していた人たちがすっと引いていく……ということがしばしばあったように思われます。それが学生運動の領域で起きたのが連合赤軍事件であり、フォークの分野で起きたのがフォークジャンボリー乗っ取り事件だったんじゃないでしょうか。
この流れは、戦後勃興したカウンターカルチャーが「どこまで羽目をはずしても大丈夫か」を手探りする営みであり、世界的にそういう傾向があったと思われますが……日本の場合は、その閾値がかなり低いところに収まったように見えるのです。
逆にいえば、カウンターカルチャーに対する抑圧がこの国ではきわめて大きかった。そしてその圧が、70年代に日本のフォークを“ニューミュージック”に変化させていった力でもあるように思われます。
あるいは、ベルウッドレコードの誕生も、その流れの中に位置づけられるかもしれません。
ベルウッドは、URC、エレックと並んで、フォークの三大レーベルといわれているところです。
今回のテーマである小室等さんは、このベルウッドの名付け親でもあります。新レーベル創設に力を尽くしてくれた鈴木という人物がいて、「鈴木」をそのまま英語にしてベルウッドと名付けたといいます。
高田渡、加川良、中川五郎といった、URCにいた人たちがこのベルウッドに移籍してくるわけですが……彼らは、かつてやっていたようなプロテストソングを歌わなくなります。
この話題が出てくるときにはたびたびいっているように、ミュージシャンが何をどう歌おうが自由であり、別にそういう変化自体が悪いというわけではないんですが……ただ、70年代にみんなが揃ってそうなっていくのは、単に個々のアーティストにおける音楽性の変化というだけでは説明のつかない力が働いていると思われ、その力というのが、つまりは先述した目に見えない抑圧なのではないかと考えられるのです。そしてその向かう先が“ニューミュージック”なのだとしたら、それはどこか、フォークという若木の生長が“矯正された”とか“捻じ曲げられた”という側面があることは否定できないと私は思ってます。
一説に、“ニューミュージック”という表現はベルウッドレコード創設の声明文で使われたのが最初の用例ともいいますが、だとすると、まさにベルウッドはフォーク→ニューミュージックの象徴といえるんじゃないでしょうか。
さて……
ここで、小室等さんに話を戻します。
先述したように、小室さんはベルウッドの名付け親であり、ベルウッドが最初期から手がけてきたアーティストの一人でもあります。後にフォーライフ創設に参加したわけですが、近年、六文銭としてのアルバム『自由』をベルウッドからリリースしてもいます。先に引用したアマゾンミュージックの「私は月にはいかないだろう」は、その音源です。
小室等とベルウッドは、そういう切っても切れない関係にあります。
では、小室等もまた、プロテストソングを歌わなくなったのか……というと、そうではありません。
どころか、彼は1978年に『プロテストソング』と題したアルバムをリリースしてもいます。
70年代の後半にあえてそういうタイトルのアルバムを出したというところに、自分はあくまでもプロテストソングを歌い続けるという強い意志が感じられます。
しかもそれだけではなく、さらに2017年には『プロテストソング2』というアルバムをリリース。
ここまできたら、本来の意味での“確信犯”といえるでしょう。
「私は唄をもつだろう」というファーストアルバムでの宣言が半世紀たっても無効になっていないことを、小室等はここで示しているのです。
このなかの「木を植える」という歌がじつに印象的です。
これも谷川俊太郎さんの詩に曲をつけたものですが、なにか、遠い昔に失われた魂がここにあるというように感じられるのです。