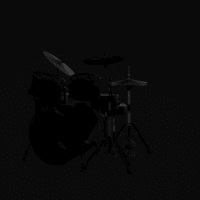今回は、音楽記事です。
このカテゴリーでは、前々回からストーン・ローゼズ、プライマル・スクリームときましたが……その流れに沿って、The Smith について書きましょう。
ストーンローゼズと並んで80年代UKロックの双璧をなすといわれるバンドが、スミスです。
この二つのバンドは同じマンチェスターの出身であり、人脈的にもつながるところがあります。
ローゼズ初期にドラムを叩いていたサイモン・ウォルステンクロフトという人がいるんですが、この人はスミスの前身となるバンドでもドラムを叩いていました。
また、ローゼズのベースで一時プライマル・スクリームに参加していたマニは、スミスのベーシストであるアンディ・ルークらとともに、Free Bass というベーシスト三人組のユニットをやっていたそうです(もう一人は、ニューオーダーのピーター・フック)。
前回の記事では、ストーン・ローゼズのライバル的存在としてプライマル・スクリームを紹介しましたが、ローゼズのライバルという点では、プライマルよりもスミスのほうがよく知られているでしょう。細かくいえば活動時期にずれがありますが、しばしばこの二者は80年代UKロック二大バンドのように扱われます。ものの本によると、往時のマンチェスターでは街じゅうの人々がローゼズ派とスミス派にわかれていたのだとか。
私個人の感想としては、スミスはローゼズに比べてインテレクチュアルな要素が強いように思われます。
英詞を読んでみると、難しい単語が多く使われ、歴史や文学を題材にした部分も。その知性的な感じのゆえに、いくらかとっつきにくいところがあるかもしれません。
たとえば、Cemetery Gates という曲では次のように歌っています。
キーツとイェーツは君の側
ワイルドは僕の側
ここに出てくる名前は、イギリスの文学者です。
ジョン・キーツと、W.B.イエーツ、そして、オスカー・ワイルド。
ロマン派のキーツではなく、耽美的なワイルド……この感覚は、ボーカルであるモリッシーのパーソナリティをよく表しているように思えます。
そのモリッシーさんですが、最近地味に話題になってます。
まず、モリッシーを描いた映画が日本で公開されました。
まあ、これは残念ながら福岡では上映がないので私は観ることができずにいるんですが……
また、モリッシーがイギリスの右翼政党への支持を表明していて、その件で本国イギリスでは物議をかもしているというニュースもありました。
そっちにいってしまったか……という話です。
もう一回り昔のパンク世代でいうとストラングラーズみたいな、唯美主義というか、そういう方向性でいくとこうなってしまうのか……とも思います。
このニュースや、先述の映画に関する情報を見聞きしていると、私はサイモン&ガーファンクルの I Am a Rock という歌を想起しました。
僕は壁をたてた そして強固な砦を
誰も打ち破れないように
友情なんて必要ない だって傷つくだけだから
愛や笑顔は 僕が忌み嫌っているものさ
愛を語ったりしないでくれ その話ならもう聞いたよ
それは僕の記憶の中で眠りについている
死に絶えた感情の眠りを妨げるつもりはない
愛さなければ 泣くことだってなかったんだ
僕には本がある 守ってくれる詩がある
部屋のなかに隠れ 子宮のなかのように守られて
僕は誰にも触れず 誰も僕に触れることはない
僕は岩 僕は島
岩は痛みを感じない
島は泣いたりしない
こういう、もうヒッキーヒッキーシェイクな感じの歌です。
聞くところによるとポール・サイモンはあるとき「あの歌は失敗作だった」といってもう I Am a Rock を歌わなくなったんだそうですが……モリッシーという人は、こういう感じのままでここまできてしまったんじゃないかと思えます。
自分という固い殻のなかに閉じこもり、そこから世界を斜めにみているというか……
まあ、アーティスティックな姿勢というのは、そういうものかもしれませんが。
その感覚は、代表曲の一つである The Boy with the Thorn in His Sideによく表れているでしょう。
The Smiths - The Boy With The Thorn In His Side (Official Music Video)
心の裡に棘をもつ少年
憎しみの奥には
愛への激しい欲求が横たわっている
この“内なる棘”をどこかで昇華しないと、極右政党を支持するみたいなことになってしまうんじゃないでしょうか。
「激しい欲求」と訳した部分は、原詞では murderous desire となっています。
直訳すると、殺人的な欲求……なるほど、オスカー・ワイルドっぽいです。おそらくモリッシーという人は、その殺人的な欲求が満たされることのない人生を送ってきたのではないか――そしてそれは、社会的に大きな成功をおさめながら、差別的、極右的な言動を繰り返したりする資産家の人たちも同じなのかもしれません。