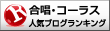当別高校に勤務しながら、引き続き個人的な合唱活動も続けていた。アポロ男声合唱団、札幌ズイングアカデミーの活動には可能な範囲で参加していた。しかし、アポロは上元先生が管理職として小樽を離れることになり、やがて消滅した。アカデミーも工藤先生が体調を崩されて解散に至ったが、教員になってから新たな活動(研修)の機会が出来た。それは、北海道高等学校音楽研究会(通称高音研)で、文字通り高等学校の音楽科教員で組織される研究団体であった。石狩支部の会員として札幌を含む石狩管内の先生方と交流、研修ができたことは大変貴重な体験であった。私が会員になったころには、小泉正松先生(札幌南高校)、加藤諠三先生(札幌西高校)が現職としていらっしゃり、われわれ若い教員に自らが研修を重ねることの大切さを説いてくださったものである。両先生の意思を受け継いで始まったのが「高音研演奏会」であった。
「高音研演奏会」は合唱、合奏を中心にして定期演奏会を続けていたが、私が転勤になってからも岩見沢から参加させていただいたので、相当な回数を重ねたはずである。その活動を通してももたくさんの方々との出会いがあった。恩師の武藤敏郎先生との再会があり、今も現役で大活躍中の大木秀一先生(当時藻岩高校)や井田重芳先生(東海大四高校)とは、お二人が新卒、新任の教師として出会い音楽活動を共にすることができた。
結局、当別高校には7年間勤務したが、合唱部は大きく育つことは無かった。当時、同じ町内の当別中学校には吹奏楽部があり、盛んに活動していた。そして、当然のごとく吹奏楽経験者が毎年、当別高校に入学するようになった。「当別高校にも吹奏楽部を」の気運が高くなって、1966(昭和41)年に吹奏楽部が創設された。私にとっては全く新たな世界であったが、当時国立音大の学生であった河地良智君(現洗足学園大学教授)が帰省の折に指導を仰いだり、、同大の仲間と共に全校生を対象にした音楽教室を行うなど、お世話になった。河地君は全日制第一期の卒業生(昭和39年卒)であり、当別高校の校歌を3年生の時に作曲している。
7年間はあっという間に過ぎ去ったが、その間、個人的には結婚、息子、娘の誕生などがあった。そして、1971(昭和46)年春に転勤の時がやって来た。当時、道教委では新卒6~7年で転勤の方針を立てており、それに該当する一人として校長より早くから指名を受けていた。また、転勤希望地を書くことが出来たので、第一志望として空知管内で合唱部がある学校とした。そして、ある時点で校長より「具体的なことはまだ言えないが、ほぼ貴方の希望通り進んでいます」の報告を受けた。当時、空知管内で合唱部があったのは、岩見沢東・西、滝川、深川西などであった。そして、岩見沢東高校への転勤が決まった。
「高音研演奏会」は合唱、合奏を中心にして定期演奏会を続けていたが、私が転勤になってからも岩見沢から参加させていただいたので、相当な回数を重ねたはずである。その活動を通してももたくさんの方々との出会いがあった。恩師の武藤敏郎先生との再会があり、今も現役で大活躍中の大木秀一先生(当時藻岩高校)や井田重芳先生(東海大四高校)とは、お二人が新卒、新任の教師として出会い音楽活動を共にすることができた。
結局、当別高校には7年間勤務したが、合唱部は大きく育つことは無かった。当時、同じ町内の当別中学校には吹奏楽部があり、盛んに活動していた。そして、当然のごとく吹奏楽経験者が毎年、当別高校に入学するようになった。「当別高校にも吹奏楽部を」の気運が高くなって、1966(昭和41)年に吹奏楽部が創設された。私にとっては全く新たな世界であったが、当時国立音大の学生であった河地良智君(現洗足学園大学教授)が帰省の折に指導を仰いだり、、同大の仲間と共に全校生を対象にした音楽教室を行うなど、お世話になった。河地君は全日制第一期の卒業生(昭和39年卒)であり、当別高校の校歌を3年生の時に作曲している。
7年間はあっという間に過ぎ去ったが、その間、個人的には結婚、息子、娘の誕生などがあった。そして、1971(昭和46)年春に転勤の時がやって来た。当時、道教委では新卒6~7年で転勤の方針を立てており、それに該当する一人として校長より早くから指名を受けていた。また、転勤希望地を書くことが出来たので、第一志望として空知管内で合唱部がある学校とした。そして、ある時点で校長より「具体的なことはまだ言えないが、ほぼ貴方の希望通り進んでいます」の報告を受けた。当時、空知管内で合唱部があったのは、岩見沢東・西、滝川、深川西などであった。そして、岩見沢東高校への転勤が決まった。