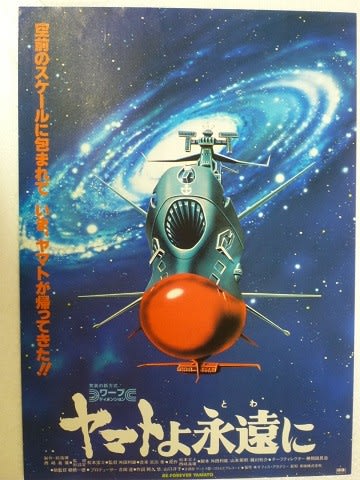2018年10月
六時礼讃堂(重要文化財)
1623年(元和9年)に建立された薬師如来坐像と四天王像を安置するお堂です。
1日を六分割して、その都度勤行(読経や念仏)を行う浄土教(浄土信仰)の教えに従って、 昼夜6回諸礼讃をする場所なのでこの名が付きました。

太鼓楼
元々、刻を知らせる太鼓を鳴らすお堂でしたが、再建の際に鐘を設け、大晦日には除夜の鐘も撞かれます。

伊勢神宮遥拝石
境内にある転法輪石、熊野権現礼拝石、引導石とこの伊勢神宮遥拝石は四天王寺四石と呼ばれます。
江戸時代はここで伊勢神宮の方を向いて遥拝する習慣があったそうです。

四天王寺の石槽(大阪府有形文化財)
いわゆる手水鉢ですね。

いつの頃からか四天王寺の境内にあったこの石はその形から蛙石とも呼ばれていて、触れると安産のご利益があったそうです。
明治時代になってからの調査でこの石は荒陵(現在の天王寺区茶臼山)から出土した古墳時代の石棺の蓋であることが分かりました。

野沢菜原種 旅の起点
2016年に建立された「野沢菜伝来記念碑」。
今では長野県を代表する名物の野沢菜ですが、江戸時代に現 野沢温泉村の僧侶が京都へ遊学した際に手に入れた天王寺蕪(かぶら)の種が野沢菜の先祖と云われてます。
こんなとこで野沢菜のルーツを知ることができるとは思いもよりませんでした



太子井戸屋形
その云われは知りませんが、応龍や菖蒲、流水などの見事な彫刻意匠に目を奪われました


南鐘堂(鯨鐘楼)

大黒堂
一体の像に大黒天・毘沙門天・弁才天の顔を持つ三面大黒天を本尊として祀ってます。
子孫繁栄・福徳智慧・商売繁盛などにご利益があるとされる欲張りにはもってこいの神様ですね(笑)
今年の2月に訪れた京都東山の圓徳院でも豊臣秀吉の出世守り本尊だった三面大黒天にお参りしました。

元三大師堂
比叡山延暦寺中興の祖で第18代天台座主だった元三慈恵大師良源を祀ったお堂。
四天王寺は中心伽藍だけでなく、境内に様々なお堂があるのも特徴で、全部回ろうとすると結構時間がかかっちゃいます


元三大師堂の敷地にあった魚籃観音
魚籃観音(ぎょらんかんのん)は三十三観音に数えられる観音菩薩のひとつ。
中国 唐の時代、魚を扱う美女がおり、観音経、金剛経、法華経を暗誦する者を探して結婚しましたが、まもなくして死んでしまいました。その後人々はこの女性は法華経を広めるためにこの世に現れた観音様だとして信仰されるようになりました。
魚の入った籠を持った姿や魚に乗った形で表される観音様です。
この像は水産業者がお祀りしたようですね。
お魚好きの管理人が四天王寺巡りの最後にこの観音様に出会えたことも何かの縁かなと思いました

おしまい
過去記事<大日本仏法最初 四天王寺1(2018年)>
よろしければ、応援クリックお願いします!