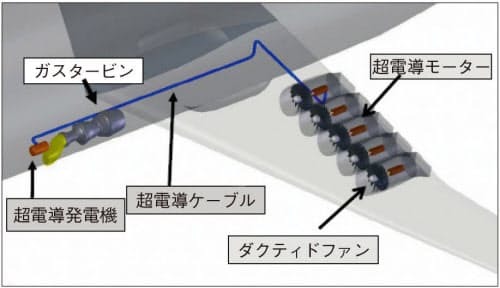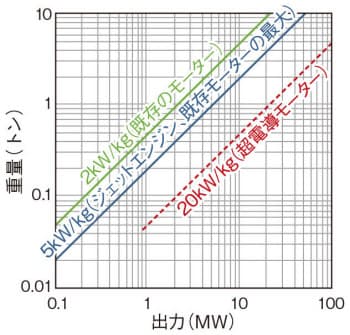中国では日本旅行の料金は比較的安く人気がある海外渡航先の一つ(春節のツアーを紹介する旅行代理店の看板、広東省広州市)
中国で日本観光の人気が高まり続けている。中国からの訪日客数は1~11月に前年同期比14%増の888万人となり、通年では1000万人の大台に迫る。ただ、倍増が続いた2014~15年に比べるとペースは落ち、最近ではアジアや欧州など他国との誘客競争も激しい。日本を旅行した経験のある中国人に聞くと「ホテルの予約をしづらい」「免税の手続きが煩雑」などの声もあがり、日本側で改善する余地がありそうだ。
「春節(旧正月)期間の日本行きツアーはもうほとんど売り切れました」。中国南部の広東省広州市にある大手旅行会社、広州広之旅国際旅行社の担当者はそう話す。中国では20年の春節休暇が1月下旬から始まるが、「(19年の)10月から予約する人が多かった」という。最も人気のある渡航先は大阪だという。
■南部からの訪日が増加
中国からの訪日客数(台湾と香港を除く)はここ数年右肩上がりで増えてきた。尖閣諸島を巡る問題で大規模な反日デモが続いた12年前後は低迷したが、14年から増加に転じた。日本政府観光局(JNTO)によると、18年は838万人で14年の240万人から3倍超に伸びた。
中国で日本はタイと並んで人気の海外渡航先だ。「近くて比較的安い」「日本独自の文化を体験したい」などの理由で、東京や大阪、京都、北海道だけでなく、九州や四国など幅広い地域を中国人観光客が訪ねるようになった。従来は北京や上海など中国の北部や中部の主要都市からの訪日が多かったが、ここ数年は広東省など南部からが目立つ。
ただ中国人訪日客数の伸びは鈍化しつつあり、中国人旅行者を争奪する競争も激化している。中国南部では最近、タイやベトナムなどのアジアや欧州の各国が誘客活動に力を入れている。「日本はこれまで黙っていても中国から観光客に来てもらえていたが、今は他国との競争に負けつつある」(業界関係者)という危機感も芽生えている。
こうしたなか、日本も官民を挙げて誘客活動の強化に乗り出した。JNTOは19日、広州市に事務所を開設した。中国本土では北京と上海に次ぐ3カ所目となる。中国南部で日本の観光情報の発信を強め、関連企業への支援も広げる考えだ。
JTBの広州市の現地法人、JTB広州も18年から訪日支援の取り組みを本格化し、日本のホテルや旅館など観光関連企業向けに誘客のノウハウを伝えるセミナーを増やしている。同社の辻本明司社長は「これからは性別や年齢などに応じた丁寧なマーケティングが必要になる」と話す。
実際に日本を訪れたり訪日に興味がある中国人に尋ねてみると、満足度や期待値は高いものの、課題を指摘する声も少なくない。
「日本の宿泊関係のウェブサイトは外国人にとって使いづらい」。広東省仏山市の金融業界で働く29歳女性の梁さんは、20年2月に友達と4人で九州旅行を計画している。阿蘇山に行くほか温泉を楽しむ予定という。ただホテルのサイトでの予約では日本の電話番号と住所の登録を求められ、外国人の利用は想定されていなかった。農村部で泊まるホテルも探し出せなかったという。
広州市のIT企業に勤める31歳女性の陳さんも、20年の春節に家族3人で東京や北海道を観光する計画だ。煩雑だと感じたのはビザの手続きだといい、「身分証などたくさんの資料を提出しなければならず大変だった。韓国のビザ取得のほうが簡単だった」と話す。
■フォークなく戸惑い
成都市で働く31歳男性の陳さんは、年に2~3回、日本を観光で訪れる。旅行自体の満足度は高いが、交通インフラについては不満を感じている。「タクシーがとても高額なため、外国人観光客にとって電車が実質的に唯一の移動手段だ。ただJRや地下鉄の違いのほか、普通や特急、準急など様々な種類があり分かりにくい」とぼやく。「中国人の観光客が多いわりに、中国語の案内表示は少ない」と感じているという。
バリアフリーに関する不満も良く聞かれる。中国人観光客はかつてのような爆買いをしなくなったとはいえ、日本で多くの商品を買って帰る場合が多く、荷物は重くなる。「エスカレーターが整備されていない場所が多く、大型のスーツケースを持つ人にとって極めて不便だ」(陳さん)
生活習慣を巡る違いに起因する不満もある。中国では食事の際に冷たい水ではなくお湯を飲む習慣がある。広州市のペット向け病院で働く28歳女性の陳さんは、12月中旬に東京と北海道を旅行したが、「飲食店で温かい飲み物が出ないので、自分で水筒にお湯を入れて携帯した」という。
「フォークが入っていないなんて!」と驚いたのは上海市で働く20代の女性だ。中国のカップ麺には通常、プラスチックのフォークがカップの中に入っている。困った末に、ホテルの室内にあった歯ブラシ2本で食べたという。
ほかにも「路上にゴミ箱が少なく、どこにゴミを捨てていいのか分からない」「免税手続きで長時間並ばなければならず非効率」といった不満も聞かれる。
中国からの訪日客は、海外からの訪日客全体の約3割を占める最大勢力だ。中国に過度に依存することはリスクにもなるが、せっかく伸びてきた需要を取り込む努力は欠かせない。20年は東京五輪が開かれる節目の年となる。中国に限らず海外からの訪日客が日本観光を楽しみ、一人でも多く「また来たい」と思ってもらえる取り組みを進める必要はまだまだありそうだ。