1月は、たまたま抽選で当たったものも含め、いくつか無料で行けるコンサートを聴いた。
まず1月16日(火)東京都人材支援事業団という団体の「華麗なるアーディストによる新春の調べ」に行った。この事業団は都の外郭団体であることは確かだが、都政のPRや福利厚生を行う団体とのことで、事業内容はよくわからない。コンサートは中学生の作文コンクール表彰式の出し物のようだ。
ただ出演メンバーが豪華だ。千住真理子(ヴァイオリン)、横山幸雄(ピアノ)、林美智子(メゾ・ソプラノ)、西村悟(さとし テノール)の4人、会場は初台のオペラシティだった。
東京オペラシティコンサートホールは新国立劇場に隣接しているので、1階や地下の飲食店に入ったことはあるが、3階に上がるのは初めてだ。3階にはコンサートホールのほか、アートギャラリーや近江能楽堂、書店があった。美術書主体のこの書店は、ちょっとみたところ選書が優れていた。
コンサートホールはパイプオルガン付きで座席数1632席とかなり大きい。
演奏曲目は、千住さんが「愛のあいさつ」「ツィゴイネルワイゼン」など、横山さんがショパンのポロネーズ6番「英雄」、自身の編曲による「オマージュ・ア・ラフマニノフ――ヴォカリーズ」というヴォカリーズ変奏曲のような曲など、林さんが「私を泣かせてください」(ヘンデル)など、西村さんが「君こそ我が心のすべて」(レハール)など、表彰式での「愛の喜び」(クライスラー)とアンコールの「小さな空」(武満徹)も含めると15曲ものポピュラーな作品中心の贅沢なコンサートだった。
わたしがもっとも感動したのは林さんと西村さんの声だった。林さんは芯の強いメゾソプラノ、西村さんは典型的な美声テノールだった。デュエットの椿姫から「乾杯の歌」、「落葉松」(野上彰・詞 小林秀雄・曲)、「小さな空」(武満徹・詞曲)はすばらしい出来映えだった。
主たる対象が中学生だったので、中学生時代についてインタビューがあった。林さんはお父さんがミニバスケの全日本監督だったこともあり小中はミニバスケ、それに加え陸上・水泳をやっていた、西村さんはバスケットで中学生のとき千葉県選抜メンバーで、全日本チームでニューヨークに遠征したそうだ。2人とも優秀なスポーツ選手だったとのことで驚いた。
千住さんは慶応女子の中学生だったが、1年のときはヴァイオリンで叱られ、2年のときは勉強で叱られあまり楽しくなかった、と意外な話だった。横山さんは普通の中学生で、放課後仲間と楽しく遊ぶが少年だったとのことだが、本当はどうだったのか、むしろ興味がわいた。
千住さんは、若いときからラジオ・テレビに出演する機会が多かったからか、お話が上手でMCの才能もある方だと思った。横山さんは、独奏曲以外はすべてピアノ伴奏も担当されたので、ほぼ出ずっぱりだった。どんな曲もソリストを立て、包み込みまとめる能力に感心した。
24日(日)午後、埼玉会館で高田馬場管弦楽団103回定期演奏会が開催された。プログラムは下記2曲だった。
マーラー 交響曲第10番からアダージョ
マーラー 交響曲第1番「巨人」
指揮:米津俊広
座席数1315席だが、1階は8割くらい入っていた。あいにく小雨が降る悪天候だったが、アマオケでたいしたものだ。
10番はマーラー最後の交響曲で5楽章形式で構想されたが、1910年作曲を開始したものの翌年50歳で死去したため1楽章のみほぼ完成に近い状態で残されたそうだ。
はじめて聴く曲ということもあり解釈が難しい。緩急も含めたリズムとハーモニーの「実験音楽」ともいえる曲だった。
チェロのピチカート、金管のハーモニー、そして最後のほうのトランペットのAの強烈なロングトーンが強く印象に残った。
1番巨人は20代の青年時代、1884-88年まで4年がかりで作曲された。たいへん有名な曲だ。巨人というと、ゴヤの「巨人」の絵を思い浮かべる。現にこの日のプログラム表紙にも使われていた。しかしゴヤの絵とこの作品はまったく関係がなく、ましてあの絵はゴヤの弟子の作品ということまでプログラム解説に書かれている。馬場管のプログラムは毎回優れているが、今回も勉強させていただいた。
この日の演奏は胴幅が広い巨大バスドラムの迫力の低音、ハープが印象に残った。3楽章中間部の(プログラム解説に書かれていた)子守唄の部分が美しかった。管弦打、ハープすべてよかったが、なぜか盛り上がりに欠けた。4楽章フィナーレで7人のホルン奏者がいっせいに立ち上がったとき、「キタ!」と思ったが、いつもに比べるといまひとつだった。指揮者とのすり合わせが少し不足していたのかもしれない。
指揮の米津俊広さんは、スロヴェニアやクロアニアで活躍している人で、馬場管とは2002年のべートーヴェン・交響曲3番を皮切りに今回で8回目、とくにマーラーは1,5,6,7,9,10番と6回にわたり指揮している。
指揮の様子はかなりエネルギッシュで、上半身を大げさなほどに動かすスタイルだった。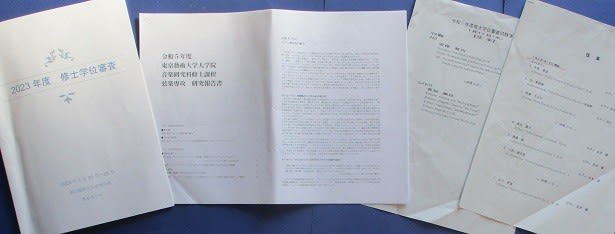
コンサートではないが、東京芸大卒業試験、修士学位審査請求試験が4年ぶりに公開され、3回聴きに行った(ただし声楽など非公開の部門もあった)。
まず年明け4日に学部のヴァイオリン4人、17日に修士のチェロとコントラバス、23日にピアノ3人の演奏を聞いた。
ホールは奏楽堂(上野公園内に移築された重要文化財の旧東京音楽学校奏楽堂ではなく、1998年に校内に完成した新奏楽堂)とその裏の校舎1階の第6ホールの2つの中ホールが使用される。後ろのほうに教員専用席がある。弦楽器は2-3人しか座っていないのに、ピアノは9人ずらりと並んでおられた。学生数に比例し教員の数が違うからかもしれない。
コントラバスの演奏曲はジョヴァンニ・ボッテジーニ(1821-1889)の編曲4曲と自身の協奏曲2番だった。ボッテジーニはイタリア・ロンバルディア州クレーマ生まれ、卓越した技巧から「コントラバスのパガニーニ」と呼ばれたそうだ。奏者が「なぜ低音楽器であるのにも関わらず、フラジオレットを駆使してこれほどまでの高音域を頑張って弾かなければいけないのか」「技巧的な部分のせいで音楽的表現が犠牲になる事が多々あるため、大道芸人になったような気分になる」と感想を書いている。奏者は長身の女性だったが、体を折り曲げるようにして高音部を弾いていた。ときおりコントラバスらしい低音部が出てきたが、なぜこういうコントラバスの魅力いっぱいの曲を選ばないのかと思った。研究報告書のタイトルは「ボッテジーニからみる独唱楽器としてのコントラバスの在り方」、よほどボッテジーニが好きなのかもしれない。
ピアノの1人の演奏曲はフォーレ、ラヴェル、シュミットの曲で、研究報告書のタイトルは「フロラン・シュミットのピアノ作品研究――モーリス・ラヴェルとの比較を中心に」だった。
フロラン・シュミット(1870-1958)はフランス・ロレーヌ州生まれ、パリ音楽院出身の作曲家兼ピアニスト。
シュミットという作曲家の名は知っているが、ドイツ人だと思った。するとその人はフロランでなくフランツ・シュミット(1874-1939)というオーストリアの作曲家だった。
演奏された〈影〉より第1曲「遠方から聞こえる」は、たしかにラヴェルとよく似た曲調だった。もう少し情熱的で烈しい感じがしたが、1曲聞いただけではわからない。
ヴァイオリンの4人は、生き生きした演奏、卒試と思えないしっとりした演奏、粘っこい演奏、自己主張のある演奏など、奏者による個性の違いがよくわかった。もちろんブラームス、シマノフスキ―、グリーク、エルガーの曲の違いのせいもあるのだが・・・。
演奏後、奏者がロビーに出て知人たちと談笑していることがある。ピアノの男性2人はずいぶん長身の方で驚いた(別に驚くことではないかもしれないが)。
毎日、FMラジオの「クラシックカフェ」「ベストオブクラシック」などでいくつもクラシック作品を聴く機会がある。しかし、生演奏は生身の人が目の見える範囲で演奏するので、やはり違う。
わたしの場合、音だけでなく演奏家の説明や語り、出入りも含めた動作や仕種、そういう個性の発見も楽しみのひとつだ。若い院生なら、この人はどんな演奏家になるのだろうとか、ベテランならどんな円熟の仕方をするのだろうとか、妄想が膨らむこともある。
コンサートを聞き終え、体のなかで音楽が飛び跳ねつつホールを後にすることは、日々の生活の刺激になることは確かである。
●アンダーラインの語句にはリンクを貼ってあります。
























