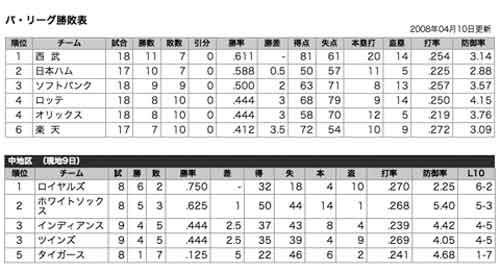金曜から土曜に掛けて、
わたしも参加している地域工務店グループ「アース21」のなかの有志の集まり
「森を考える会」の総会に行って参りました。
これは、地産地消とか言われているのに、
実際の北海道の森がどのようになっているのか、
なにも知らないのでは、提言もできないし、方向性も見えない。
そういう現状を打開するのに、自らも森林所有者になって
どのようなことを考えていったらいいか、
そういう体験を共有しよう、という狙いから作った会。
実際に昨年、わずかな面積ですが森林を購入したのです。
森林を購入したら、こんどは管理をしなければならないし、
定期的な下草伐採、間伐などから経営的視点から植樹計画も考えなければいけない。
そういう話し合いをする中から、北海道の森林のよい未来を考えたいということ。
今年第1回ということで、自分たちの森を見に行った次第です。
所有はグループの代表個人で登録していて、
わたしたち会員は、利用権として一口参加しているという形態です。
ゆくゆくはユーザーのみなさんにも呼びかけて、
北海道の森の現状を考えていただくきっかけにもしていければと考えています。
なんですが、まぁ、楽しみながらでなければ続かない。
ということで、場所は札幌の北方30kmほどの厚田の近郊で日本海も見える高台。
朝、近くの海で取れたホタテなどを仕入れてきてのバーベキュー大会から、
森林探索、沢地の探検などを行ってきました。
お酒が入っているので、わたしは沢まではおりませんでした(笑)。
笹に足を滑らせて、滑落したりするので、危険もあり、
万が一に備えて、助け出す係になった次第です(笑)。
まぁ、本音は痛い思いはしたくない、というところですが(笑)。
でも、早春とはいえ、森の空気感は清涼で素晴らしい。
購入した森林のお隣には、引退された元北海道職員のかたのロッジがあり、
そこを利用させていただいたのですが、
お話を伺うと、いろいろな側面が見えてきました。
とくに印象的だったのは、動物植生の変化ぶり。
ペットとして飼っていた犬や猫などを投げ捨てていく人が後を絶たず、
そうした犬が野犬となって、集団を造り徘徊していると言うこと。
人間の勝手気ままが自然の輪廻を破壊している実態がまざまざと感じられます。
一方で、いわば自然絶対主義的な、原理主義的な
一切自然に手を付けてはいけない、みたいな考えも同時に自然維持には問題がある。
森林は人間が適切に面倒を見ていく必要があるのだ、と思います。
そのような長期的な自然保持、環境保全の方法を考えていかなければなりませんね。
時期を見て、読者のみなさんやユーザーグループのみなさんなどに
森と親しんでいただく機会を作りたいと考えています。
沢地には野花が咲いていましたが、
その驚くほどの緑のみずみずしさ、花の色の新鮮さに心打たれます。