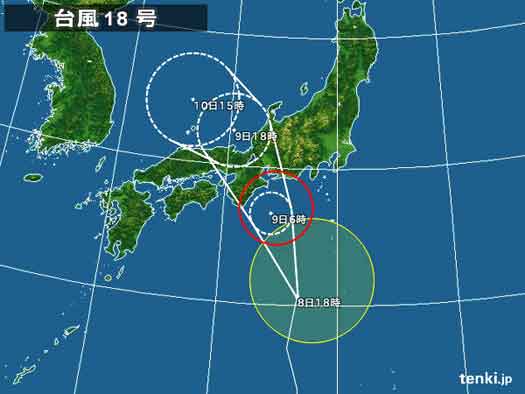きのう新住協総会から、無事札幌に帰還致しました。
最終日になって、ようやく名古屋らしい暑さは多少戻っていましたが、
それまではどちらかというと、肌寒いような天候で終始していました。
さて、総会の最終日は全国の会員からの事例発表。
それぞれに興味深い内容の発表だったわけですが、
最後の、木の香の家・白鳥さんの発表が注目されました。
白鳥さんは新住協の理事でもあり、若い年代の会員を代表するような存在。
東北大学出身で経営的にも先導的な取り組みをされています。
今回、自宅建築に取り組まれるにあたり
ドイツパッシブハウスの基準に合致した住宅を計画されたのです。
写真は、その熱的なシミュレーションを検討したプロセス。
よく、東北のプロのみなさんがこの基準に挑戦されるのですが
みなさん一様に、そのハードルの高さを語られます。
この白鳥さんの検討プロセスでも、
当初の、生活デザイン上の基本的な要望を満たしたプランでは
暖房負荷12.5kWh/m2、暖房用灯油使用量272リットルが
ただただ防御的なプランにしてなんとか基準をクリアさせたプランで、
暖房負荷5.0kWh/m2、暖房用灯油使用量106リットルとなっている。
灯油換算で、年間162リットル削減ということにはなる。
しかし15,000円程度の年間コスト削減、それも太陽熱・光利用など
よりエコロジカルな他熱源選択をすれば簡単に回収可能なコストのために
それこそ死んだようなプランを受け入れるしかない。
まぁ結局、基準を満たすためには、南面以外の窓をなくした
単純なボックスにしていくしかなくなってしまう。
そうすると、基準を満たすためだけに、
その「認定を取る」ためだけの家づくりになってしまう。
そうした自己矛盾と思えるようなプロセスが、表現されていました。
プロセスではドイツ側の方から、基準達成は
「そもそも、岩手県北上では、ムリですね」という指摘もあったとか。
日本では温暖地域しか、達成は難しいのが実際。
そういうことなので、北海道の大多数のみなさんは挑戦しようともされない。
「意味ないでしょ」というのが多数意見。
鎌田先生の発言でも、求めている方向性自体にはまったく賛同だけれど、
そもそもドイツと日本の気候条件の違いや、
ソフト上の気候条件についての判断基準への疑問提起もありました。
多額の「認定費用」を取って、住宅性能を担保する「認証」を与えることで、
より防御的な基準数値にならざるを得ない実態も語られていました。
ドイツは全国一様に、気温条件的には日本の「温暖地」であり、
仮にパッシブハウス基準をスウェーデンに持って行って当てはめると
「無暖房」レベルでようやく基準に合致するともされていました。
さて、このテーマ、
「住宅性能」についての今後の大きなテーマになりそうです。
パッシブハウスは、方向性は正しいけれど、
その地域、生活やデザインに似合ったものの追求というのが、
やはり自然な流れになって行くのではないか。
「原理主義」のような方向性では、やがて行き詰まるのではないのでしょうか?