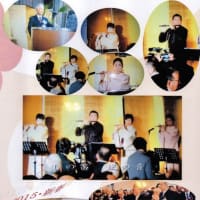播州室津に春を告げる行事が、国重要文化財・室津賀茂神社の小五月祭。
播州室津港は、千年以上の歴史を持つ、天然の良港。
風待ちの港、室の津、と呼びならわされてきた。
その歴史の豊かさは播州の他の地域とは、おそらく比べ物にならないだろう。
平清盛が厳島神社に参詣する途中に、二度、室津に立ち寄った記録が残っている。
その当時には、立派な構えの社が建ち並んでいたことが知られるので、その歴史は1000年以前ということになる。
源平の合戦の折り、室津・室山城に平家二万余騎が陣を敷いた。ここに五百余騎で攻め込んだ源行家は散々に蹴散らされ、浪速まで追い返されたという歴史もある。
また九州で兵を養った足利尊氏が兵庫に攻めのぼる際、軍議を開いたとされるのが、室津の見性寺と伝えられている。
また近松の好色十人女の第一番、お夏清十郎の、清十郎の生家は播州室津にある。
また戦国真っ最中の騒乱の時代に、赤松氏の夜襲により、婚礼の夜の室山城の落城という悲劇が起こる。
婚礼の夜に討ち死にしたとされる、悲劇の姫・志織姫は黒田如水の妹と伝えられる。
この事件が、今に伝わる、室津八朔のひな祭り の由来とされる。
そして、播州室津に春を告げる小五月祭では、無形民俗文化財・棹の歌 が奉納される。
これこそ源平の合戦の面影を残す行事なのだ。
義経に打ち破られた木曽義仲の、側室・山吹御前は落ち延びて播州室津にたどり着いたと伝えられる。
この山吹御前は歌舞・音曲で、港を訪れる旅人の心を慰め、義仲一門を弔う生涯を送ったとされる。
この女人が、室津遊女の元祖とされる、友君と伝えられる。
この友君が奉納したのが「棹の歌」と伝えられ、小五月祭で地元保存会の方々により奉奏される。
小五月祭では、室津の女子による友君行列も繰り出す。
室津の女性の自慢は、室津の女の子は全員が鼓が打てる、ということだ。
そんな雅な歴史を持つのが、播州室津なのだ。
4月2日(土)15:30~ 室津賀茂神社にて、宵宮・神事が催行される。
この場で、しの笛の演奏をさせていただく。
しの笛:城山如水、玉田麗水
曲目:室の波
さくら
室津~八朔の恋歌
ふるさと
荒城の月
他
歴史豊か、風光明媚な、室の社、国重分・室津賀茂神社の小五月祭に、お出かけ下さい。