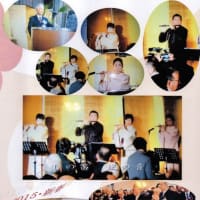「淡路人形座」の義太夫三味線の鶴澤知路さん99歳を初めて知った。
4歳から義太夫三味線を初め、その後、大阪で最高峰の師匠の下で修行。
27歳で独立を許され、現在まで公演と後進の指導に当たってこられた「人間国宝」
招かれた、カーネギーホールの公演では大好評を博した。
公演と全国からのお弟子さんに稽古をする毎日。
「三味線が好きやから。休んでるほうが疲れる」と語っておられた。
99歳でまだまだ現役。
仕事であれ趣味であれ、生涯続けられるものを持てた人は幸せだ。
天才とは、才能とは「好きな事をやり続けること」というのがよく分る。
しの笛の世界でも「早く上達するにはどうしたらいいですか!!」と、しきりに焦る人がいる。
自分は「焦らずに時間をかけて吹き続けることですよ」と言ってあげる。
「3年、5年、10年・・・と吹き続けた時に、いつの間にか上達している自分に気が付きますよ」と言ってあげる。
「先生のように吹けるように教えて下さい」という人も多い。
これは、実は「教えられるもの」ではない。
なぜかというと、それは「その人の感性を磨くしかないわけで、技術を教えることはできるが、感性は教えられない」からだ。
作曲についても全く同じことがいえる。
「作曲技法」は教えることはできても「創作」は作曲者の感性によるものだからだ。
作曲や即興演奏するに当たって重要なことは「教科書的作曲法を捨てることから始まる」ということなのだ。
「作曲技法や即興演奏法」というものはあるが、作曲し即興演奏をするのは創作者の「感性と研究」によるわけで、これだけは教えられる性格のものではない。
好きな演奏スタイルの先生について、先生と共に時間をかけて「先生の演奏スタイルを吸収する」ことなのだろうと思う。
淡路島の義太夫三味線には「楽譜」が存在しないそうだ。
「床本」というテキストに指使いが書き込まれたものが各曲に1冊存在するだけで、すべてが口伝えなのだそうだ。
これは「しの笛」も同じ。「しの笛」には幸いにも楽譜はあるが、楽譜は「記号」であって、どのように音を出し、どのように表現するかは楽譜からだけでは読み取れない。
クラシック音楽でもほぼ同じ事がいえると思う。
「技術」は教えることができる重要な要素だが、「感性」はさらに重要だが「教える」ことができないものであり、「吸収」するものであり「磨くもの」だということだろう。
淡路人形浄瑠璃・義太夫三味線の鶴澤友路さんのドキュメントを見て、そんなことを思った。