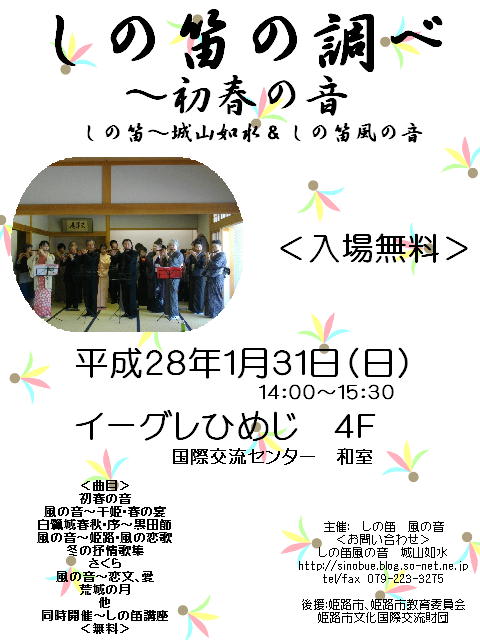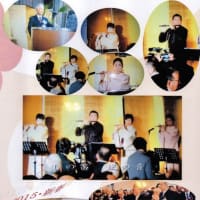「お通さん」は吉川英治の小説「宮本武蔵」に登場する創作人物である。
にもかかわらず、大原の里には「お通笛の会」があり、姫路城下には「お通像」が建っている。
小説「宮本武蔵」の、姫路城下「花田橋」の章に、武蔵とお通さんの出逢いと別れの名場面が切々と描かれている。
お通さんは、母の忘れ形見として「しの笛」を携えている。
お通さんが奏でる、しの笛は母を慕う音色でもある。
歴史物語には往々にして、尾ひれのようなものが幾つも付いて現在に至っているものが多い。
その典型が「平家物語」だろう。その他の戦国歴史物もほとんどが真偽入り乱れて、物語として現在に伝えられている。
したがって宮本武蔵の「お通さん」も、「そのような人がいたかも知れない」というロマンとしてとらえておけば良い事だと思う。
「お通さん」が実在しなかったとも言えないし、「お通さん」のような女性が実在したとも言い切れない。
歴史ロマンというものは、そういうものであり、歴史ロマンはそれで良いのだと思う。
歴史ロマンで確定できない事実として「義経の一の谷の逆落とし」の場所が神戸には二箇所あることだ。
しかし、どちらもが「義経の一の谷」として歴史ロマンを大切にしておられる。
この姿勢こそが「地元の歴史」に「ロマン」を吹き込むものだと思う。
姫路城下には高木橋(現在は小川橋)のたもとに旅姿で武蔵を慕う「お通さん」の像が建っている。「お通公園」だ。
そのお通さんの腰に短刀のような差し物がある。それが「お通さんの」母の形見の「しの笛」なのだ。
播州しの笛 は お通さんの笛でもある。
「風の音~恋文・愛(城山如水作曲)」は武蔵を慕う「お通」さんの想いを、しの笛で奏でる曲なのだ。
毎回の演奏会で必ず演奏するのが、この「風の音~恋文・愛」なのだ。
1月31日の「しの笛の調べ~初春の音」にて、播州しの笛の独奏・合奏により
武蔵を慕うお通さんの想いを情緒豊かにお聞きいただきます。
http://hyocom.jp/bbs/bbs_list.php?root_key=161848&bbs_id=14
播州城山流<しの笛 風の音>城山如水作曲
http://sinobue.blog.so-net.ne.jp