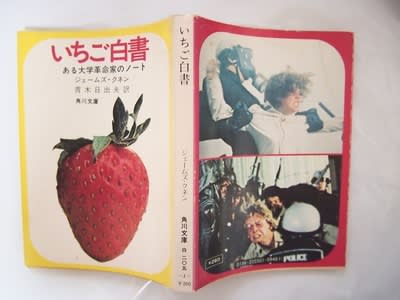この映画に物語は微塵もない。それは途方もなく感動的なことです。
映画について話しているとき、ストーリーはどうでもいい、こう口にすると強い反発を招くことがあります。
しかし実際、映画についてその物語の「内容」の良し悪しを語るのはほとんど意味のないことです。
クリント・イーストウッド監督/主演のこの「クライ・マッチョ」という作品は、その物語の無さについてこそ語りたくなる作品です。
いまじはじめてウィキペディアをみましたが「批評家からは舞台背景や映画音楽については高い評価を得たものの、脚本については酷評された」とあります。
あり得ない。まったくあり得ません。
これは脚本こそがすばらしい。そしてそこにある非-物語的な理念をほとんど完全に現実化した奇蹟のような作品であるはずです。
門外漢の私が映画について何か書こうとするのは大変に気がひける思いです。
(とはいえ、これまであらゆる文章を、門外漢としてしか書いてこなかった身ではあるのですが。)
また、これについて一気にまとまった紹介を書ける自信もありません。
ですから、ここにこんなふうにメモを書き連ねていって、と考えた次第です。
うまくいかなければ、いっそのこと消してしまうのがいいでしょう。
「クライ・マッチョ」
監督 クリント・イーストウッド
脚本 ニック・シェンク/N・リチャード・ナッシュ
原作 N・リチャード・ナッシュ『クライ・マッチョ』
製作 アルバート・S・ラディ/ティム・ムーア/ジェシカ・マイヤー/クリント・イーストウッド
音楽 マーク・マンシーナ
撮影 ベン・デイヴィス
編集 ジョエル・コックス/デイヴィッド・コックス
製作会社 マルパソ・プロダクション
配給 ワーナー・ブラザース・ピクチャーズ
公開 2021年9月17日
上映時間 104分
映画について話しているとき、ストーリーはどうでもいい、こう口にすると強い反発を招くことがあります。
しかし実際、映画についてその物語の「内容」の良し悪しを語るのはほとんど意味のないことです。
クリント・イーストウッド監督/主演のこの「クライ・マッチョ」という作品は、その物語の無さについてこそ語りたくなる作品です。
いまじはじめてウィキペディアをみましたが「批評家からは舞台背景や映画音楽については高い評価を得たものの、脚本については酷評された」とあります。
あり得ない。まったくあり得ません。
これは脚本こそがすばらしい。そしてそこにある非-物語的な理念をほとんど完全に現実化した奇蹟のような作品であるはずです。
門外漢の私が映画について何か書こうとするのは大変に気がひける思いです。
(とはいえ、これまであらゆる文章を、門外漢としてしか書いてこなかった身ではあるのですが。)
また、これについて一気にまとまった紹介を書ける自信もありません。
ですから、ここにこんなふうにメモを書き連ねていって、と考えた次第です。
うまくいかなければ、いっそのこと消してしまうのがいいでしょう。
「クライ・マッチョ」
監督 クリント・イーストウッド
脚本 ニック・シェンク/N・リチャード・ナッシュ
原作 N・リチャード・ナッシュ『クライ・マッチョ』
製作 アルバート・S・ラディ/ティム・ムーア/ジェシカ・マイヤー/クリント・イーストウッド
音楽 マーク・マンシーナ
撮影 ベン・デイヴィス
編集 ジョエル・コックス/デイヴィッド・コックス
製作会社 マルパソ・プロダクション
配給 ワーナー・ブラザース・ピクチャーズ
公開 2021年9月17日
上映時間 104分