最近ウオーキングしていないので散歩をする事にし、
目的無く歩くのも嫌なので近くの埼玉県入間市『高正寺』を訪ねることにしました。
このお寺は鎌倉時代初期に地元の豪族によって創建されたそうです。
その豪族は諏訪神を守護神としていたところから、「諏訪山萬齢院高正寺」と称しています。
前に紹介した「円照寺」より規模は大きいお寺ですが、やはり静かで素朴な雰囲気があります。
表通りから入った参道では両脇にお地蔵様が迎えてくれました。


門には「諏訪山」の名があります、門右前に「武蔵野観音霊場」「奥多摩八十八ケ所霊場」の石碑があります。


門を潜ると階段があり、昇りきった所に「鐘楼門」があります。1522年開山二百五十回忌に作られたそうです。
1階が門となっており2階が鐘楼となっている建物です、右側写真は境内側から見た鐘楼門です。


高正寺本堂

左は本堂の屋根瓦 右は鐘楼門の屋根瓦


寛元4年(1246年)の文字があり市内最古最大の板碑といわれています。(右から2番目)

境内には地蔵尊像や干支の絵が描かれた将棋の駒などがありました


次回鐘楼門前にあった羅漢像の幾体かを紹介します。
目的無く歩くのも嫌なので近くの埼玉県入間市『高正寺』を訪ねることにしました。
このお寺は鎌倉時代初期に地元の豪族によって創建されたそうです。
その豪族は諏訪神を守護神としていたところから、「諏訪山萬齢院高正寺」と称しています。
前に紹介した「円照寺」より規模は大きいお寺ですが、やはり静かで素朴な雰囲気があります。
表通りから入った参道では両脇にお地蔵様が迎えてくれました。


門には「諏訪山」の名があります、門右前に「武蔵野観音霊場」「奥多摩八十八ケ所霊場」の石碑があります。


門を潜ると階段があり、昇りきった所に「鐘楼門」があります。1522年開山二百五十回忌に作られたそうです。
1階が門となっており2階が鐘楼となっている建物です、右側写真は境内側から見た鐘楼門です。


高正寺本堂

左は本堂の屋根瓦 右は鐘楼門の屋根瓦


寛元4年(1246年)の文字があり市内最古最大の板碑といわれています。(右から2番目)

境内には地蔵尊像や干支の絵が描かれた将棋の駒などがありました


次回鐘楼門前にあった羅漢像の幾体かを紹介します。











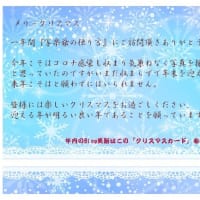








素敵な門ですね、近くで見ますと、細工や、
木組みなどが見えるのですね、一列に並んだ
お地蔵様も綺麗に手入れされてますね
神社仏閣を拝見すると、気持ちが落ち着きます
ご無沙汰しております 今年に入り始めてのPCの前に座って居ります 好きな事をするのが一番癒されるようです、
高正寺は写真を拝見したところ大部由緒あるお寺のようですね、曹洞宗のようですが我が家も曹洞宗です
珍しいお寺の紹介有難う御座います
今年も宜しくお願いいたします
すぐにお地蔵様が迎えてくれてほほがゆるみます。
1246年に彫られた板碑が未だに残っていてこういうのを見ると胸が騒ぎます。
屋根瓦には独特の形をしたものが上げられていて一見の価値がありますね。
地蔵尊像が多くほかの細かいところもじっくりと見たいようなお寺さんだと思いました。
羅漢様の表情もどんなかなーと見てみたいです。
藤岡へはご機嫌伺いなので散歩などできるかどうか・・・外歩きもしてみたいけど何しろ空っ風の上州だから考えただけでもぞ~っとします。
いつもウオーキングで歩く入間川沿いの散策路はこの時期川風が冷たくチョッとキツイ感じでついついサボってしまいがちでした。
散歩と言ってもあてどなく歩くのもつまらないのでカメラ片手に市内のお寺を訪れてみました。
こちらこそご無沙汰していました。
「高正寺」は鎌倉初期の創建のお寺で現在は曹洞宗だそうです、ちなみに我が家は浄土宗です。
市内にはまだまだ小さな寺院等があるのでできれば巡って見たいと思っています。
本年もよろしくお願いいたします。
羅漢様は多くはありませんでした、鐘楼門前の左右に6・7体づつ並んでいました。
市内には普通前を素通りしてしまう様な寺院等があります、こちらに引っ越してきた頃には市内散策もしたのですが最近はさっぱりでした、このところの寒さでウオーキングをサボり気味なので寺院巡りもいいかなと思っています。
こちらも寒さが厳しくなって今朝は庭の水道が凍ってしまいました、空っ風の上州路は更に厳しい事でしょうね。
写楽爺さんらしい写真ですね。
鬼瓦の写真など目の付け所が違いますね。
干支の将棋の駒も面白いですが、高正寺と将棋は何か関係あるのでしょうか。
鐘楼門も立派ですね。
ガイドブックに出てくるような寺院ではないので絵になるような建物や境内風景等はありませんが素朴な静かなお寺でした。
将棋の駒の形をした干支の石は本堂前に置かれていましたが見た目新しいものでした、特に云われなどは無いと思うのですが定かではありません。
被写体としての寺院とは言えません、散歩がてら記録に撮ったに過ぎません。
最近屋根瓦にチョット興味が出てきました。
霊場周りも色々有るようですね