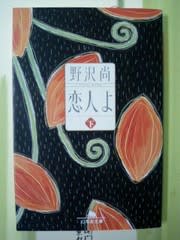[感想:★★★★-:ぜひ勧めたい!]
「宇宙創成(上、下)」 (サイモン・シン著、新潮文庫) これは面白い! 上巻を飛ばして下巻から読み始めたがそれでも十分面白い。宇宙はどうやってできたのだろう・・・、宇宙の果てはあるのか・・・誰もが一度は思うであろうテーマである。ここで「宇宙」とは「星」でも「銀河」だけでなく「宇宙全体」そのもののことだ。宇宙ができたところを見た人はいないのに、現在よく知られている「
ビッグバン理論」に誰が、どのようにしてたどり着いたのだろうか。
科学は、「理論(モデル)」と「データ(観測値)」からなる。「理論」はどんどん変わっていくが、「データ」は変わることなく事実として残り曲げることはできない。科学者は様々な「データ」からそれらを説明できる「理論(モデル)」を作り上げる。このため沢山の「理論」ができあがるが真理は1つだけだ。新しいデータを説明できない「理論」は捨てられる。
宇宙創生の研究には、極めて多くの分野の研究者がかかわっている。量子力学・物理学・数学・・・そしてある研究者は「データ」を提供し、ある研究者は「理論」を提供する。感動するのは、自分のデータの中でノイズや異常値とも思える結果を安易に捨てずにとことん追求する人たちの存在だ。それらは、必ずしも宇宙創生の研究のために行うものではないが、突然他の分野の理論やデータと結びつくのだ。「理論」でも壮絶なバトルが展開される。宇宙の始まりを「計算」して理論構築する人たち。この理論が正しければ・・・が観測されるはずだと予言する人たち。その予言をひょんなことから発見する人たち・・・とにかく面白いノンフィクションである。ぜひオススメしたい。
 [感想:★★★--:面白い]
[感想:★★★--:面白い]