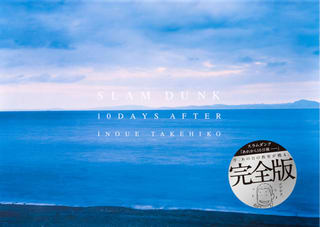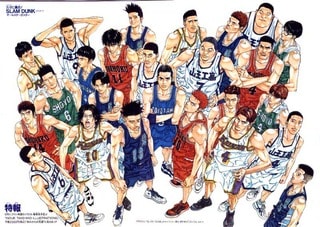『エヴァンゲリヲン』にハマって一週間。ついにTVシリーズ26話全話と劇場版 『DEATH & REBIRTH シト新生』劇場版『THE END OF EVANGELION Air/まごころを、君に』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』を見た。
TVシリーズについては、物語とキャラクターの設定、演出の仕方は当時としては斬新で画期的だなと思って観ていた。しかし、回が進むに連れて、物語の構成やテーマがだんだん複雑化して、設定を生かしきれていないし、何が言いたいんだか散漫で、独りよがり的な展開になってきた。TV版25話と26話などは止め絵と文字だけで、動画も背景も制作が間に合わなかったのかというような印象を持った。止め絵でキャラクターの口パクだけの動画、声優がセリフを読み上げ、文字だけがフラッシュする演出は、セリフの内容を強調し、登場人物の心理描写に視点を置いているつもりだろうが、アニメーションとしてはただの手抜きである。音声を消したら何も伝わってこない。これはアニメではなく、『紙芝居』だ。
第1話は、製作者側のすごい意気込みやら野望やプライドを感じる画質と演出だっただけに、25話と26話は尻切れトンボの無責任な終り方だなと思った。
劇場版(『シト新生』と『Air/まごころを、君に』)を見て、納得はしなかったけれど、25話と26話を一応映像化はしてみたんだな。とは思った。
それでも、やはり何が『人類補完計画』なんだかさっぱり分からなかった。
おそらく、制作者側も、「とりあえずはできたところまでで公開してしまおう」みたいな見切り発射的な公開の仕方と、不完全燃焼しか残らなかったのではないか・・・。
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』の『序』とは、『序破急』の『序』から来ているそうだ。『序破急』とは物語の“起承転結”、舞台の“三幕構成”と同義語であると言うことだ。
『新劇場版:序』は6話までの焼き直しと言うか、10年後対応リメイク版という感じった。
TVシリーズと言う低予算とハードスケジュール、テクニック不足でできなかったことを10年後の技術と予算でじっくりかかって制作することができたのだろう。
何度も同じ話をベースに作り替えながら、往年のファンを納得させ、新しいファンを獲得していくのは至難の業だと思う。
『序』で面白かったのは、背景動画だ。TVバージョンではあそこまで凝ったら、逆に怒られてしまう。でも、劇場版だからこそ、細部まで神経の通った『魅せる』背景、動く背景が出来上がったのだろう。
要塞都市『第3東京市』自体が1つの重要なキャラクターとして、『人格』と言うか、『意思』まで持っている感じがした。
リリスを守るために最後は使徒と刺し違えて自爆しても『サード・インパクトを未然に防ぐ装備と覚悟のある都市。
その都市を最終的に破壊するのが、皮肉にも18番目の使徒である『人類』とは・・・。(このラストを『急・FINAL』ではどう表現されるのだろう・・・)
TVシリーズでも、それまでの劇場版でも語られなかったエピソードとして、シンジが葛城ミサトに対し、エヴァに乗ることの恐怖と、ミサトたちは安全な場所で指示を出すだけなんてズルイと抗議するシーンが印象的だった。
ミサトはシンジを連れて、地下に眠るリリスに会わせる。
その時に、この要塞都市第3新東京市の地下空間(ジオフロント)と特務機関NERV(ネルフ)で働く全員が、使途を殲滅するのに命がけで取り組み、万が一使徒進入を許した場合は使徒と刺し違えてでも『サード・インパクト』を未然に防ぐための自爆装置を持っていることを告げる。
三度めのエヴァ搭乗を決意するシンジの手をミサトが強く握ったとき、それに応えるように握り返してくるシンジの指先の動きがとても印象に残るシーンだった。
TVシリーズでは謎のままだった渚カヲル君の活躍が期待されるようなラストシーンだった。
公開が楽しみだ。
『エヴァンゲリヲン』を見ながら、自分のときの14歳、息子や娘たちの14歳、今まで出逢ってきた生徒たちの14歳をずっと考えてきた。
思春期は『さなぎ』の時代とも言う。
さなぎはその硬い『殻』または『繭』の中で、劇的に進化し成長し変化しているのだ。
やがて、時が経ち、『羽化』のときを迎える。自分で殻を脱ぎ捨て、繭を溶かし、中から自力で出てくるのだ。
中には変体の最中に力尽きて、そのままの状態で絶命する者もいる。
せっかく出てこられても、不幸にも他の生物の餌食になってしまう者もいる。
また、奇形で生まれてきて、子孫も残せず排除され、その命を終える者もいる。
「さなぎを破って出てきたら、枝につかまってじっと外の世界の冷たい風に晒されるほどその羽根は力強く鮮やかに色付き、飛び立つときを待つ。
『大空を抱いて輝く』ためにはそういうプロセスを踏まなければならないのだ。
だが、その『時』を大人の都合で勝手に早めたり、待ちきれずに殻を破ったりすると中で幼虫は死んでしまうのだそうだ。
『さなぎ』の時は、周りの大人もじっと見守り、待つ覚悟と余裕と忍耐を試されているのだ。
14歳。その内に秘めた未知数の可能性と繊細で柔らかな感性、危ういバランス。
『逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ!!』(byシンジ)
『自己防衛』と『自己主張』、『自己欺瞞』と『自己肯定』、『自己達成』と『自己完結』・・・セルフコントロールって、難しい・・・。一番苦しいのは『自分と向き合うこと』。『自己満足』も『自己愛』もなければ、自分が生きている証を求め、『自傷行為』や『自暴自棄』に陥ってしまう。
自分を大切にできない人間は、他者を大切にすることはできない。
『自分が嫌い』で苦しむシンジ、それはアスカも同じ。
誰かに認められたい、必要とされたい、愛されたい。そのために人類の夢と希望と未来と命を背負って戦う14歳の姿は、あまりに痛々しい。
だから。
『あなたは死なない。私が守るから』(by綾波レイ)
『僕は君に逢うために生まれてきたのかもしれない』(by渚カヲル)
と言うセリフにシンジはグッとくるのだ。
完結編『急・FINAL』の制作はもう始まっているのだろう。
それに向かう「STEP」としての『破』が「HOP」の『序』を上回り、「JUMP」の『急・FINAL』で制作者も観客も充分に『補完』される作品として更なる進化を遂げていくことを祈る。

 <優しい気持ちになれた。
<優しい気持ちになれた。