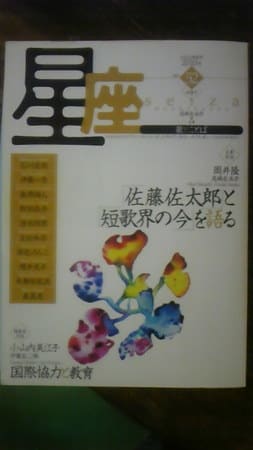ブナの木通信「星座88号」
(早朝に秋晴れの空を眺める歌)
昨年の夏は豪雨がたびたびあった。首都圏でも関西でも、大雨警報が何度も出された。その日に秋の空を眺める。雨は降りそうにない。「ぽかんと」眺める。オノマトペが一首を軽くせずに、独特の味が出ている。
(日傘の陰に自分の影を入れて歩む歌)
昨年は暑かった。耳をふさがれるという錯覚にちかいものもあったと思う。それを空間の厚みのある深い作品に仕上げた。
(映像の中で雪がしんしんと降る歌)
映像短歌は弱いと言われる。だが、この作品は、雪の降りようを的確に表現して、見事に美しい情景を映し出した。美しさも芸術表現の条件の一つである。
(蝉の鳴く夜の幻聴の兆す歌)
聴覚の効いた作品。この欄の二首目の作品と同じ、炎暑の日の感覚。だがそれは無音ではなく蝉声のなせる技だ。酷暑という条件が同じでも、着眼点と切り込みの方向が違えば、作者の独自性が出る。
(団栗の実生の芽吹きの歌)
実生の団栗とは、樹より落下して芽生えたもの。その全てが発芽するわけではない。おそらく周囲には、異種の植物が生育しているだろう。自然のなせるる偶然。その団栗が赤子のように、逞しい生命力を持っている。それが作品の見所。
(花柘榴咲く線路沿いに涼しい花が咲く歌)
皮膚感覚を活かした作品。何より清涼感がある。初夏に咲く花だが、昨年は初夏から暑かった。猛暑でも清涼感のある作品は作れる。要は作者がどこに目を付けるかだ。
(雨の多い地球で紫陽花が怪しく光る歌)
美は芸術の条件の一つと言ったが、これは怪しい美しさである。地球を惑星になぞらえることで深みのある作品となった。次の二首も佳詠。
(夕暮に明日の大嵐の予報を聞く歌)
(異常気象を地球の悲鳴と感じる歌)
今号は佳詠が多く、推薦に迷った。
*註① 「映像短歌が弱い」と書いたのは、斎藤茂吉や佐藤佐太郎が歌論の中で、「体験」を重視すると言っているのによる。
*註② 「推薦」とは投稿作品の中から、秀作を作ったと思われる作者を二人、主筆に推薦すること。四人の選者が二人ずつ、八人推薦するが、そのうち三人の作品が巻頭近くに掲載される。