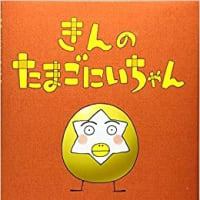新・向かい合うもの (その1)
《 君のペースで 》
…彼女が回復するためにはその支配が必要なのだ、
私にはそれがわかりはじめた。
けっきょく、完全に自分ではどうすることもできなくなり、
無力感を感じるというのが、トラウマ体験の要素の一つだ。
だから、トラウマになるようなストレス(※特別支援)に
対処するには、自分でコントロールできるという感覚を
取り戻すことも重要なのだ。
これはかつて「学習性無力感」という
現象の研究で鮮やかに示されている。
□ □ □
【2匹のラット】
2匹のラットが、隣あった別のケージにいる。
一方のケージでは、ラットが餌を得るためにレバーを押すと、
まず電気ショックが走る。
もちろんラットにとってとてもストレスになるが、
時間を経るにつれ、ショックの後に餌が手に入ることを理解し、
慣れて耐性ができる。
ラットは電気ショックを受けるのは、
レバーを押すときだけだとわかったので、
状況をある程度、自分でコントロールできるようになったのだ。
予測できてコントロールできるストレス源には、
時間が経つにつれて耐性が増すので、
それほどストレスを感じなくなる。
けれど、もう片方のケージでは、
餌をもらう仕組みは同じだが、電気ショックをうけるのは、
自分がレバーを押したときではなく、
隣のラットがレバーを押したときになっている。
つまり、いつ電気ショックを受けるかわからないので、
状況をコントロールすることができない。
(このラットは、ストレスに慣れるのではなく、感作される。)
どちらのラットも脳のストレスシステムに
大きな変化が見られる。
ストレスをコントロールできるようになったラットには、
有益な変化がおこり、
もう片方のラットには
有害な変化と調整障害が起こる。
電気ショックをコントロールできないラットたちは
潰瘍ができ、体重が減り、免疫系が弱るので、
病気にかかりやすくなる。
悲しいことに、
状況が変わってショックをコントロールできるようになっても、
長い間コントロールできない状況に置かれていたラットは
怯えすぎて、ケージの中を探って
身を守る方法を発見することができない。
~『犬として育てられた少年』ブルース・D・ペリー
紀伊國屋書店より~
最新の画像もっと見る
最近の「膨大な量の観察学習」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- ようこそ就園・就学相談会へ(504)
- 就学相談・いろはカルタ(60)
- 手をかすように知恵をかすこと(29)
- 0点でも高校へ(393)
- 手をかりるように知恵をかりること(60)
- 8才の子ども(161)
- 普通学級の介助の専門性(54)
- 医療的ケアと普通学級(90)
- ホームN通信(103)
- 石川憲彦(36)
- 特別支援教育からの転校・転籍(48)
- 分けられること(67)
- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)
- 膨大な量の観察学習(32)
- ≪通級≫を考えるために(15)
- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)
- この子がさびしくないように(86)
- こだわりの溶ける時間(58)
- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)
- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)
- 感情の流れをともに生きる(15)
- 自分を支える自分(15)
- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)
- 受けとめられ体験について(29)
- 関係の自立(28)
- 星になったhide(25)
- トム・キッドウッド(8)
- Halの冒険(56)
- 金曜日は「ものがたり」♪(15)
- 定員内入学拒否という差別(97)
- Niiといっしょ(23)
- フルインクル(45)
- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)
- ワニペディア(14)
- 新しい能力(28)
- みっけ(6)
- ワニなつ(351)
- 本のノート(59)
バックナンバー
人気記事