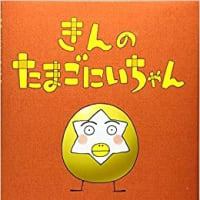《はじめてのおつかい 3》【能力じゃない、の話】
□
3歳の子にお金の「計算能力」はない。
言葉で説明する「能力」は未熟。
商品を「記憶する能力」もあいまい。
忘れないように復唱しつつ、転んで忘れることもある。
買った袋を引きずって破れたり、中身がぐちゃぐちゃになることもある。
でも、そんなことは「はじめてのおつかい」の主題じゃない。
□
元々「できない」ことがいっぱいあるけれど、視聴者は、その辺の「能力の低さ、未熟さ」は気にしない。
「理解できてないこと」「身体的にできないこと」、それを含み込んだうえでも、「はじめてのおつかいはできる」と信じている。らしい。
これって、何への「信頼」だろう?
「能力」への信頼ではないよね。
だって、「できない」ことだらけ、ってことはみんな分かってる。「頼りなくて見てられない」って、みんな思ってる。だけど、「それでも大丈夫な、安全なつながり」が、そこにはある、と信じている。
□
リップクリームの売り場がどこか分からず、アイスクリーム売り場で「食べたいなぁ」と思いながら、でも買うのはこれじゃない、と分かってる。
自分のほしいお菓子を買ってはいけない、ことも分かっている。
お母さんと一緒の時は「買ってほしい」と駄々をこねるとしても、一人のときは「買わないという、自分の納得」が、できる。
もちろん、たまに余計なお菓子を買ってしまう子がいるのは愛嬌の内。
お金の計算ができなくても、財布を開けてみせれば、相手がちゃんと取ってくれる。そこに、何の疑いもない。「信頼」しか、ない。
お金の価値、売買の理屈、いろんな知識を、3歳の子どもはまだ知らない。理解もできていない。
それなのに。全国の視聴者はそれが「問題」だとは少しも思わない。
「理解できていないこと」「身体的にできないこと」を、ある程度含み込んだうえで、《この子には、「はじめてのおつかい」が、できる》と信じて見ている。
これって、何への「信頼」だろう?
「能力」への信頼ではないよね。
だって、「できない」ことだらけ、ってことはみんな分かってる。「頼りなくて見てられない」って、みんな思ってる。だけど、「それでも大丈夫な、安全なつながり」が、そこにはある、と信じている。
□
《膨大な量の観察学習」による「知」と「信頼」》
私が思っているのは、3歳の子どもの「膨大な量の観察学習」への信頼。
親と一緒に買い物を繰り返したことで、「いつものお店」に行けば「かいもの」ができる。
その途中の道すがら、「親と地域とのつながり」を通して、「世界は安全だ」と全身で知る。
3歳の子が、全人生を通して学んだ「知」と「人間への信頼」。
「それさえあれば大丈夫」という、信頼こそが、あの番組を「成立」させているんじゃないかな。

写真:仲村伊織