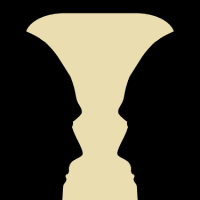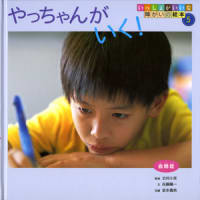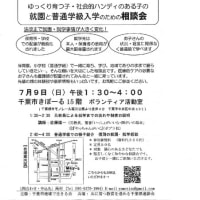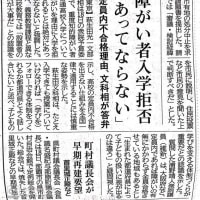人間の声には「あいだの音」がいっぱいあるという。
そうであるなら、子どもの声が行き交う宇宙には
「あいだのおと」が天の川のように流れているのだろう。
この子は見えないし、聞こえてない、
なにもわからないと言われる子が、
学校のなかで子どもたちの気配に顔を向けるのは、
きっとあいだの音が聞こえ、
その天の川が見えているのかもしれない。
「あいだの音」があるのなら、「あいだの言葉」もきっとある。
「おはよう」は、「お」「は」「よ」「う」の4つの音でできているんじゃない。
三十人の子どもがいれば、百二十の音があり、ときに重なり合い、ときに反発したり、音の組み合わせは無数にあって、子どもにはその世界が聞こえているのだろう。
音だけじゃない。
「おはよう」という声とことばを通して、伝わる気持ち、感情の流れもまた無限にある。
大好きな友だちとの「おはよう」
苦手な男の子への「おはよう」
今朝も会えてうれしいと返ってくる「おはよう」
照れくさそうにつぶやく「おはよう」
一人への「おはよう」に、三十人への「おはよう」
やさしい先生の「おはよう」
強面の先生の「おはよう」
髪の毛の一本もない校長せんせいの「おはよう」
「おはよう」の音も意味もひとつじゃない。
人と人のあいだの数だけちがった「おはよう」がある。
クラス初日のおはようの音と、一か月後のおはようは、ちがうハーモニーを奏でるだろう。
テストの日のおはようと、授業参観の日のおはよう、
遠足の日のおはようと夏休み後のおはようも、きっと違うハーモニーを奏でる。
はるか昔、大学で「言語」の勉強をしたときには、こんなこと聞いたことも、考えたこともなかったな。
「個別」の教室で教える「おはよう」は、何を教えているんだろう。
最新の画像もっと見る
最近の「こだわりの溶ける時間」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- ようこそ就園・就学相談会へ(494)
- 就学相談・いろはカルタ(60)
- 手をかすように知恵をかすこと(29)
- 0点でも高校へ(393)
- 手をかりるように知恵をかりること(60)
- 8才の子ども(161)
- 普通学級の介助の専門性(54)
- 医療的ケアと普通学級(90)
- ホームN通信(103)
- 石川憲彦(36)
- 特別支援教育からの転校・転籍(48)
- 分けられること(67)
- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)
- 膨大な量の観察学習(32)
- ≪通級≫を考えるために(15)
- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)
- この子がさびしくないように(86)
- こだわりの溶ける時間(58)
- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)
- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)
- 感情の流れをともに生きる(15)
- 自分を支える自分(15)
- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)
- 受けとめられ体験について(29)
- 関係の自立(28)
- 星になったhide(25)
- トム・キッドウッド(8)
- Halの冒険(56)
- 金曜日は「ものがたり」♪(15)
- 定員内入学拒否という差別(97)
- Niiといっしょ(23)
- フルインクル(45)
- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)
- ワニペディア(14)
- 新しい能力(28)
- みっけ(6)
- ワニなつ(351)
- 本のノート(59)
バックナンバー
人気記事