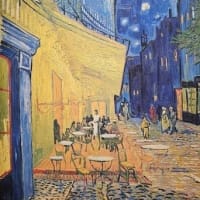【2011年8月11日】 京都シネマ
『ムッソリーニを愛した女』というタイトルから連想するのは、『ファシスト』の代名詞である《ムッソリーニを愛する女》を題材にする映画ってどんなだろうか、《見るに価しない》ような映画ではないのかなという疑問だった。
しかし、それは大きな誤解だった。
歴史上に実在した女性の物語である。
ムッソリーニに多くの愛人がいたという。ヒトラーと同じように、最後は愛人を道連れにして、パルチザンに銃殺された。そのときの愛人、クラレッタ・ベタッチを含め多くの愛人は自分の存在を主張して、独裁者に《反抗》することなどしなかった。
この映画の主人公イーダだけは違った。結婚して長男を設けたにも関わらず、ムッソリーニからその存在を、息子を含めて否定された。だから、クラレッタと違って、多くの国民にも知られておらず、この映画の監督のマルコ・ベロッキオも最近になってその存在を知ったという。
○ ○ ○
物語は、若き日のムッソリーニとイーダが偶然で会うところから始まる。社会主義者で教養もあり、戦闘的に国の改革に取り組むムッソリーニとの二度目の再会でイーダはムッソリーニに強く惹かれ、恋に落ちて彼を支える存在になる。子供ができ結婚をするが、その後ムッソリーニに別の妻がいることを知る。
一度は、子供を認知してもらうが、ムッソリーニが政権をとり独裁者の道を歩み始めるとイーダの存在が邪魔になってきたのだ。はじめは軟禁からしまいには精神病院に送り込み、その存在を抹殺しようとする。

この映画で精神病院が大きな役割を果たす。
知ってのとおり、イタリアでは「バザーリア法」によって、精神病院が廃止された。病気の治療というのは二の次で、第一に「社会にとっての《危険な人物》(それが病気に由来するものか、為政者にとって危険なものかを問わず)を社会から隔離し、人格を無視し、自由を奪い《治安を守る》のが精神病院だった。バザーリアは、劣悪な環境で強制入院・強制治療のまかり通る精神病院の実体を目の当たりに見て、イタリアから精神病棟・精神病院を廃止することを決意する。
1978年にその法律が通って、2000年には、ほぼイタリア中の精神病棟が無くなったというから、すごい。
「イタリアの精神病院とバザーリア法」の一端を知る関連ページ
○ ○ ○
精神病院が《治安》の一端を担っているというのは、ほかの映画の中でもよく見られる。
映画『T-2』でリンダ・ハミルトン演じる『サラ・コナー』が国家の機密を知ったばかりに、気ちがい扱いされ、精神病院に入れられ、自由を奪われ、息子を危険にさらされる。この母親のたくましさ、半端じゃない精神力には、何度見ても感動する。
映画『カッコーの巣の上で』では、ジャック・ニコルソンの演じる主人公のマクマーフィーが、刑務所の強制労働を避けるため、仮病を使って精神病院に入るが、そこでの《問題行動》で精神病院を抜け出せなくなる。患者の自由を訴えたり、非人間的な扱いに反抗したりするうち、看護師長ににらまれ、拘束されたり、強制治療をされられる。更に、ロボトミー手術で廃人にさせられ、最後は、ともに病院からの逃走を勧めた友達のチーフに安楽死させられる。チーフは、到底一人では持ち上げられなさそうな「水飲み台」を窓ガラスに放り投げ、そこから病院を出て行く。
ともに、印象に残る良い映画だ。
この映画の話に戻る。
映画の中に、昔のニュース映像やら当時の様子が入れられていて、効果的で臨場感がある。
また、チャップリンの「キッド」が劇中劇として上映されていたのにはびっくりした。息子を連れたイーダがそれを見ていて涙するシーンが印象的だ。それにしても、もうその頃にチャップリンの映画があったとは、驚きというか新鮮というか感動的である。
この映画の唯一の目に付く欠点は、ムッソリーニ役の男が一般によく知られた《傲慢で自己顕示欲の強く、憎たらしいムッソリーニ》の姿とは似ても似つかない《男前》ということである。


【 本物のムッソリーニ 】
イーダが強く引かれるた男性、自分の全財産を投げ打ってまで惚れ込んだ男としては美男子の方が分かりやすいかも知れないが、それだと話が浅薄になってしまう。
政権をとってからのファシスト・独裁者としてのムッソリーニでなく、若いころの一時マルクスにも傾倒し、社会党の闘志として、機関紙の編集責任者として、全エネルギーを社会変革に傾倒した《若き日のムッソリーニ》にイーダは惹きつけられたと思うのだが、それにしても、もう少し後年のイメージを多少なりとも連想するような骨格・風貌をもった役者はいなかったのだろうか。
『愛の勝利を-ムッソリーニを愛した女』-オフィシャル・サイト-既に無くなっています(存在しないページ)