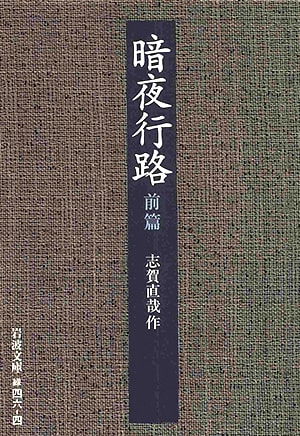木洩れ日抄 61 老人たちの光景

2019.10.6
高齢化社会ということが問題になって久しいが、当の自分がその問題の渦中にいるとなると、困ったもんだとうそぶいてもいられない。かといって、どうすることもできない。どうすることもできないままに、「横浜市敬老特別乗車証」などという代物に嬉々として申し込んでゲットし、用もないのに用事を無理やりみつけ、先日初めて乗ってみた。
上大岡駅始発の住宅循環バスである。この住宅循環に昼間乗る乗客のほとんどは高齢者で、まともに運賃を払って乗る人など稀だ。運転手も、運賃を払う人には思わず「ありがとうございます」なんて言ってしまう人もいるくらいで、まあ、老人の天下である。そういう老人も結構卑屈になっていて、パスを見せながら「よろしくお願いします」などとペコペコする人も多く、ぼくが「パス持ち」でないころは、もっと堂々と使えばいいのにと思ったものだ。それよりなにより、バスに乗り込んでから、パスをバッグから探す人もいたりして、ペコペコする前に、乗る前からちゃんとパスを出しておいたらどうなんだ、なんて内心ブツブツ呟くこともよくあった。
その日、無理やり作った用事を終えて、上大岡駅からいよいよ最初の「無賃乗車(もちろん、ほんとうは年額なにがしかの金を払っています)」のバスに、胸躍らせて乗り込もうとした。
上大岡駅には、大きなバスセンターがあって、ぼくらの住宅循環バスの乗り口には、「思いやりベンチ」という4〜5人掛けの木のベンチが置かれている。立ってバスを待つのが大変な老人とか具合の悪い人が、そこに座って待てるようにという配慮である。しかし、ベンチの脇に、立って待つ人が並んでいるわけだから、後から来た人がベンチに座ってしまうと、並んだ順番が分からなくなってしまう。そのことで、以前からたびたびトラブルが起きていた。
そこで、数年前からだと思うが、とにかくベンチに座っている人が、来た順番とは関係なく、先に乗車できるということにして(たぶんバス会社がそう決めたのだろう)、ベンチの側に「ベンチに座っている人の乗車を優先してください」というような張り紙が貼られるようになった。しかし、小さな張り紙なので、それを知らない人もいて、相変わらず小さないざこざが起きていたのである。
その日、ぼくが並んだ列はまだ人が少なくて、ぼくは前から2人目だった。ベンチには2人のバアサンが座っていた。そこへひとりのジイサン(といってもたぶん60代)がやってきて、ぼくの後ろに立った。その後、2〜3人のバアサンがやってきてベンチに座った。そのうち列も長くなって来たころにバスがきた。
当然のごとく、ベンチに座っているバアサンたちがよっこらしょと立ち上がり、バスに乗り込もうとした。すると、ぼくの後ろに立っていたジイサンが、「なんで後から来たヤツが先に乗るんだ」とバアサンたちに向かって言い放った。バアサンたちは、ハッとして立ち止まった。
「あ、それはいいんですよ。ベンチに座っている人を先に乗せろって、そこに書いてあるでしょ!」ととっさにぼくが大声で言った。ジイサンは納得できないという顔をしてぼくをにらみつけるので、「いいじゃないですか。ベンチに座っている人はたいてい具合が悪いんだから。」と言ったら、ジイサンは「おれだって具合が悪いんだ。」と反論してくる。「何言ってるの。オレだって具合が悪いよ。」とだんだんぼくもヒートアップしてきた。柄も悪くなる。それにぼくはちっとも具合なんか悪くない。でも、「老人」だというだけで、若者より「具合が悪い」ことは確かだ。だから嘘じゃない。
すると、さらにヒートアップしたジイサンは、「オレなんか、障害者だぞ。一級だ!」と叫んだ。変な「自慢」である。
「それならあんたもサッサとベンチに座りゃあいいじゃないか!」と声量マックスで叫ぼうとしたとき、ノロノロ進んでいた列はぼくの番になり、ぼくは無料パスを運転手に見せる段となってしまった。けれども、頭の中には、さっきのセリフが渦をまいていてワンワンいっているので、「最初に無料パスを見せる快感、あるいは感慨」などどこへやら。いったんの休止を経ては、そのセリフも行き場を失ってしまった。ぼくの前の座席に座っているそのジイサンの背中にむかって、そのセリフを言ってみても始まらない。なんとも憤懣やるかたない気持ちのままバスは発車した。
次のバス停で、バアサンが一人乗ってきた。席はもう埋まっていたらしく、いったん後ろの方へ歩いていったそのバアサンが、バスが走っているのに、フラフラと前の方に歩いてきた。すると、運転手がキレてしまって──キレた気持ちほんとよく分かる。だって、のっけからジイサン二人がワアワア喧嘩しながら乗ってきて、その挙げ句これだもんね──、「走っているときに、動き回らないでよ! 危ないから!」とマイク越しに怒鳴った。バアサンは照れ笑いをして手すりにつかまった。
次のバス停で何人かが降りようとした。運転手が「いいですか皆さん、バスがちゃんと止まってから降りましょうね!」と言った。さっきの怒鳴り声とはうってかわって冗談めかした明るい声だった。車内の老人たちは、顔を見合わせて笑った。「そうよねえ、わかってるんだけど、どうしても遅れちゃ悪いって思って立っちゃうのよねえ。」なんて会話がバアサンたちの間で交わされたことだろう。
ぼくの前に座っていた件のジイサンは、なんとぼくと同じバス停で降りた。ご近所さまだったらしい。見知らぬ顔だけど。
まったくやれやれである。こんなわけのわからぬ高齢者連中の仲間になり、これから生きていくのかと思うと暗然とする。高齢者パスなんて持ってなければ、「オレは仲間じゃないぜ面」できるけど、そんな面をしたところで、何の得にもならないし。
それにしても、あの近所のジイサンは、なんであんなことにムキになるのだろう。どう計算したって、自分が「前から5番目」で、その前に3人入ったって8番目なんだから座れることは明らかなのだ。自分が座れればあとはどうだっていいや、ってどうして思えないんだろう。自分が座れればそれでいい、なんていうのは自己中心主義で、彼の中では「後から来たヤツが前に行くのは許せない」ということなのだろう。そんなヘンテコな正義感みたいのから早く自由になって、お互いにいたわり合って暮らしていかなきゃこの先大変ですぜ、って、今度あったら話してみようかなあ。また怒鳴られるだけか。