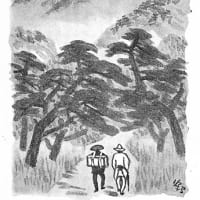木漏れ日抄 112 『光る君へ』──みとれてしまう

2024.10.5
『光る君へ』を見ていて、一番感じるのは、とにかく画面がキレイだということ。昨今のテレビの性能のせいもあるけど、とにかく美しいの一言だ。
誰かがどこかに『光る君へ』のよさは、「画面の明るさ」だということを書いていたけど、同感だ。ほんとは、当時の部屋の中などは、薄暗かったに違いない。御簾(みす)なんかおろしたら、電灯を消してカーテン閉めきってるようなもんで、部屋の奥なんてどうなってるかわからないほど暗くて、人の顔なんかよく分からなかったろう。まして、やんごとなき天皇のご尊顔など、うすぐらさの中にぼんやり見えた程度じゃなかろうか。
それが、一条天皇など、その超イケメンのお顔が、まるでレンブラント光線にでも照らされているかのように(これも誰かが言っていたっけ?)、やわらかく、しかも、はっきりと見える。照明スタッフの努力の結晶だ。しかも、それがちっとも不自然に感じられない。
ネット界隈では、きっと、「平安時代の部屋の中ってもっと暗かったんじゃね。」みたいな言葉が飛び交っているに違いない。そういうことをしたり顔にいう輩が最近多いが、じゃあ、当時と同じくらいの明るさ(暗さ)で画面を作ったら、それでいいのかってことだ。そんなの見ちゃいられないだろう。なんにでも、「そのころはそうじゃないだろ」って言わずにはいられないのは、昨今のネット民だが、そんなことより、そんなことは百も承知のうえで、では、どうしたらより美しく、また当時の現実感を再現できるだろうかと考えるところにドラマ制作の醍醐味があろうというものではないか。
まあ、そうはいっても、けっこう「うるさ型」のぼくだが、かのネット民ほどの違和感を感じないのは、あの明るさが、『源氏物語絵巻』の再現に違いないと思うからだ。『源氏物語絵巻』を見ると、どこにも影なぞない。部屋の隅々までくっきりと見える。あれだ。
そればかりではない。『源氏物語絵巻』は、斜め上からの構図をとることが多いが、それを意識したのか、ある回で、女房たちの「局(つぼね)」を、真上から移動撮影した。このシーンには驚き、感動した。そうか、「局」って、こういう構造になっていたんだとか、思っていたよりずっと狭くて、隣の女房のイビキまで聞こえてきたんだとかいったことが分かってすごくおもしろかった。この「局」の「思っていたより狭い」ということは、脚本家もびっくりしたのか、確か藤原道綱に、「へえ、ずいぶん狭いんだね。」みたいなセリフを言わせている。ぼくも道綱に共感した。
このドラマの美術スタッフは、『源氏物語絵巻』とか、その他の絵巻物を丹念に調べ、部屋の構造から、調度品や衣装まで、細かい時代考証をしてそれを丁寧に映像化していてとても貴重だ。いくつかのそうしたシーンを短い動画として、『源氏物語』などの授業で見せたいくらいだ。「図録」などより、どれだけ分かりやすいかしれない。
庶民の暮らす「郊外」の明るさも印象的だ。(『信貴山絵巻』とかいった絵巻物などを参照しているのだろうか。)「まひろ」が、ひょいひょいと出かける「郊外」では、芸能者たちが藤原氏をおちょくる歌を歌って舞う。それをおもしろがって見物する「まひろ」。貴族たちの住む邸宅の周辺には、そうした「郊外」が広がっていたことも、「室内劇」中心の『源氏物語』ではイメージしにくい。もっとも、「夕顔」の巻などでは、そうした「郊外」にある廃屋が舞台となるのだが、宮廷との物理的な距離感が、なかなかつかみにくいものだ。
そんな意味でも、平安時代の物語を読むうえで、とても参考になるドラマなのだ。
光があれば影もある。このドラマの影もまた美しい。「五節の舞」のシーンなどは、光と闇のコントラストが素晴らしく、まさに色彩の饗宴で、思わず見とれてしまった。道長と「まひろ」がともに過ごす月夜の晩とか、石山寺でであった二人が結ばれる夜とか、闇そのものも美しく表現されている。これもみとれた。
毎回「みとれる」、『光る君へ』である。