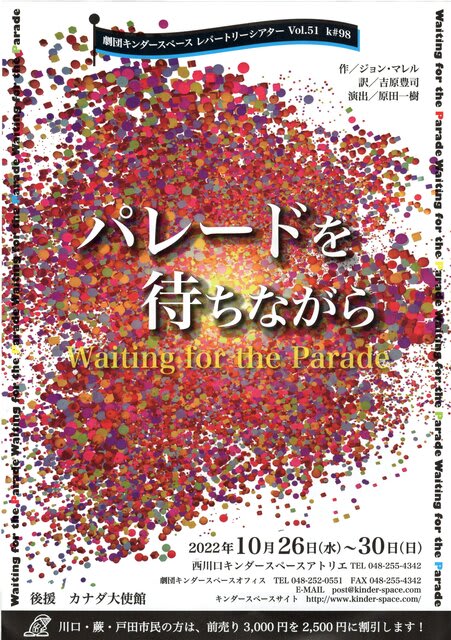日本近代文学の森へ 231 志賀直哉『暗夜行路』 118 「頼み方」の問題 「後篇第三 十三」 その2

2022.11.9
謙作と直子が、新しい家を探しにいって、これはよさそうと思った家の大家の息子とちょっとした諍いをする。その場面で、大家の息子が、天井からつるした電燈の位置を下げてくれという謙作に、けんもほろろの応対をするのだが、その不思議な論理について、「京都というところは、こういうところなのだろうか?」と疑問を呈してみた。
この疑問は、京都に住む旧友を念頭に置いたもので、こう書いておけば、あとで、必ずメールをくれるはずである。で、案の定、数日たってメールが来た。
それによると、彼の奥方が、知り合いに聞いてくれたというのだ。というのも、彼も彼の奥方も、京都の人間ではないので、確かなことは言えないが、さんざん「京都人」には悩まされてきたので、聞いてみる相手には事欠かないということらしい。
で、その返事はこうである。(転載の許可いただいたので。少々手をいれています。)
(1)そもそも京都人は、京都人(碁盤の目の内に住んでいる人)以外はバカにしている。
(2)頼み方が率直過ぎる。何でも遠回しに、相手に言わす。ちょっと針仕事するのに、暗(くろ)おすけど・・・(大家に)どないか、方法ありますやろか? なんて、頼み方をする。相手に主導権を。自分で決めない(ズルい)。
(3)壁の頼み方は、丸見えで困る、と言っただけ。塀を作ると言ったのは大家。要は、京都人特有の下らないプライド。困ったな〜、どないしよ? 二階で着替えられしまへんな〜。(大家に) どないしたら、宜しいやろ? と聞くのが、いわゆる「相手にするのがめんどくさい」京都人。
なるほど、ちょっとした「頼み方」が問題だったのだ。目からウロコである。
そういえば、大家の息子は、この直前までは機嫌がよかったのだ。
「此所がちょっと具合悪そうだな」二階の南向きの窓から首を出して謙作はいった。
「隣りから首を出すと、直ぐ向かい合いになる」
「本統に」と直子もいった。鍵を持って案内に来た大家の若い息子が、
「其所でしたら、その便所の屋根に小さい塀を立ててもよろしいです。西日除(よ)けにもなりますよって……」と心持よくいった。
「そう。そうしてもらえば上等です。それから、この電気の紐を部屋の隅に置く机の上まで引張れないと困るのですが、もし何だったら私の方で直してもいいけど……」
「へえ、それ位、私方でさせましょう」
ここでは、謙作も直子も、「直接」に、苦情を言っていない。大家の息子が来る前には、「具合悪そうだな」と謙作は言ったが息子はその言葉を聞いていない。やってきたら、二人が困っている。それを息子が「察して」、自分のほうから直そうと言ったわけで、「主導権」は息子にあるのである。だから機嫌がいい。
ところが、その後は、こうなる。
この辺まではよかった。が、それからまた階下に下り、茶の間になる部屋の電燈がやはり天井から二尺ほどしか下がっていないのを見ると、謙作は、
「これも少し困るな」といった。「これじゃあ針仕事に暗いだろう」
「延びるんじゃないこと」と直子がちょっと脊延びをしてそれを下げようとした。
「延びまへん」大家の息子は気色を害したような調子でいった。そして少し離れた所に立って黙ってそれを見ていた。
ここでの「問題点」は、まず、謙作も直子も、それぞれ苦情を言葉にした。これが、(2)に当たるわけだ。つまり、「頼み方が率直過ぎる。」ということ。「頼み方」というよりも、文句を言ってるわけだから、当然、息子にしてみれば、むっとする。更に、直子が「勝手に」電燈(のヒモ)を伸ばそうとする。これはもう絶望的にダメだ。息子が主導権をとられてしまったからだ。だから、「延びまへん」と突っぱねる。実際には「延びる」のかもしれないが、とっさにそう言うわけだ。
その後の、電燈を下げなくても「京都の者にはそれで事が足りとるさかいな。」というのは、もう、「売り言葉に買い言葉」で、意地を張っているということになる。実際に、京都の人間が暗くても平気である、ということを言っているというよりは、意地を張っていると考えたほうがいいだろう。
この部分については、横浜に住んでいる旧友とのやりとりで、彼が言っていたことだ。
ヘタに読むと、「手暗がりでも京都人は我慢するけちん坊だ」といったような結論に向かいかねないところだが、「頼み方が率直過ぎる」という観点によって、その結論は回避されることになるわけだ。
それにしても、「京都人」というのが、「碁盤の目の中に住む人」に限定されるというのも、スゴイなあ。まあしかし、「千年の古都」なんだから、そういうこともあるのかもしれない。「横浜人」と称するわけもわからない人間が、中区と西区と南区(いい加減です。まあ、中心部ぐらいの意味。)以外は「横浜」じゃないみたいなことを口走るのとはワケが違う。中区だろうが、西区だろうが、果ては、港区だろうが大田区だろうが千代田区だろうが、「碁盤の目の外」であるという点においてはなんの変わりもない。京都人、最強である。
とまあ、そんな嫌味めいたことも言いたくなる、「京都人」だが、その「京都人」の一面(あくまでも一面にすぎないだろう)を、志賀直哉は、ここもサッと見事に描きだしているのである。
さて、その後、二人は貸家探しをやめて、祝い物の返しの品を買いにいく。謙作の母方の伯母が嫁にいった陶工の店などに行き、「赤絵の振出し」(注:振出し= 茶道で、小型の菓子器。また、香煎を入れる器。)を買って、その店を出る。
二人がその家を出た時には既に日暮れ近く、寒い風が道に吹いていた。謙作にはその寒さがこたえた。
「早く何所(どこ)かで飯を食わないと風邪をひきそうだ」彼はこんな事をいって二重まわしの襟を立てた。
「きっと仙が支度をして待ってますわ」
「どうだか?」
「そう? そんなに平時(いつも)そとであがっていらしたの?」
「そうでもないが、出掛けた時間がおそかったから、そとで食って来ると思ってるだろうよ」
なだらかな五条坂を二人はこんな事をいいながら下りて行った。五条の橋はかけ更えで細い仮橋が並べてかけてある。二人はそれを渡って行った。
寒風の中、五条の橋を渡っていく二人の姿が印象的だ。
そして、ちょっとした会話から、結婚までの謙作の日常をふと垣間見る直子の心のうちも思いやられる。